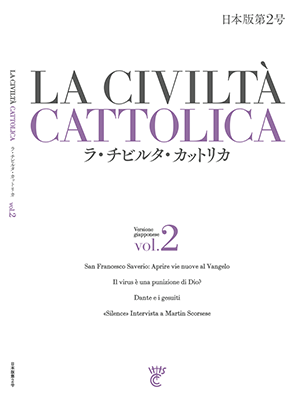La Civiltà Cattolica
日本版
(公財)角川文化振興財団バチカンプロジェクトから刊行!
ローマで発行された最古のカトリックジャーナルが史上初、日本版で刊行されました。
日本版創刊2号
聖フランシスコ・ザビエル
『福音への新しい道を開く』
San Francesco Saverio:
Aprire vie nuove al Vangelo
Giuseppe De Rosa S.I.
ジュゼッペ・デ・ローザ神父
日本に初めてキリスト教を伝えたことで、
キリスト教に縁のない人でも
その名を知っているフランシスコ・ザビエル。
その生涯はいかなるものだったのか、
布教活動における困難や戦略、
またその想いを丹念に辿ります。
La Civiltà Cattolica 2005 IV 541-554
2006年は聖フランシスコ・ザビエルの生誕500年記念の年である。1506年4月7日にナバラのハビエル城で生まれたザビエルは、おそらく近世において最も偉大な宣教師であり、教会に活力を与えるべき福音の精神を見事に体現した人物である。ここでは、10年ほどと短期間ではあるものの、人間の能力を超越した素晴らしい彼の福音活動に関して、簡単にたどってみたい。彼の成し遂げた活動は、今日においても若きキリスト教徒たちに、世界中に福音を伝えようという力強い呼びかけとなるだろう。
「はい、私がここにいます」
1525年、19歳にして、フランシスコ・ザビエルはパリ大学で教育を受けるためにパリへと向かった。そこで彼は11年の歳月を過ごし、アリストテレス哲学などの自由学芸を教える教授資格を得た。しかし彼の運命は哲学を教えることではなかった。彼の人生の転機は、同じくバスク出身で彼より年上の学生であったイグナチオ・デ・ロヨラとの出会いにあった。ロヨラもまた、パリ大学で自由学芸と神学の学位をとるためにパリに滞在していた。同じ部屋で生活するうちに、フランシスコはイグナチオの影響で、現世の成功や栄光に対する自身の野心を捨て、神や使徒に生涯をささげる決心をした。そうして、1534年8月15日に、イグナチオと他の5人のパリ大学の学生たちとともに、貞潔と使徒的清貧の誓いを立てたのだ。
7人は聖地エルサレムに行き、パレスチナでトルコ人に対して布教活動を行うことを決心した。もしパレスチナに行けなかったならば、ローマに行き、教皇が望む場所ならどこへでも教会のために赴くことを申し出よう、と。そしてまさにそうなった。聖地エルサレムに出発することはできなかったが、ローマに到着すると、イグナチオと仲間たちは教皇パウルス3世のもとに行き、教皇はすぐに彼らを宣教に派遣することにした。そして出発する前に、彼らはイエズス会を創設したのである。
フランシスコ・ザビエルに宣教の機会が訪れたのは、ポルトガル王ジョアン3世が教皇に、新しく創設されたイエズス会の神父を宣教師としてインドに派遣するよう要請した時であった。この時ポルトガル人のシモン・ロドリゲスと、スペイン人のニコラス・ボバディリャが選ばれた。しかし、ニコラスが病気にかかったため、イグナチオはフランシスコに彼の代わりに行くよう求めた。イグナチオの求めに対して、フランシスコ・ザビエルはただこう答えたという。「はい、私がここにいます」。そしてすぐに荷造りに取り掛かった。聖務日課書、教理書、聖書の引用集、2本の使い古したズボン、ボロボロの司祭の法衣1着、これが彼の荷物だった。
インドに向けて出発
1540年3月15日、フランシスコはリスボンに向けて出発し、1541年4月7日にテージョ川からインドに向けて出航した。彼は教皇パウルス3世が彼を教皇大使に任命した勅書を携えていた。船長にとって、王令に基づき教皇大使としての威信と権威を保つためには、フランシスコは召し使いを従えなければならず、船の端で自分で衣服を洗っているところや、食事の準備をしているところを人に見せてはいけなかった。しかしフランシスコは彼にこう答えたという。「あなたが私に提案した方法で獲得した威信や権威は、教会や司祭たちを今の状態まで衰えさせてしまいました。威信や名声を獲得する唯一の方法とは、衣服を自分自身で洗い、鍋を自分で沸かして、他人の考えに配慮して自分を合わせるのではなく、魂の救済にのみ専念することです1」。
インドへの旅は、死ぬ可能性のある恐ろしい冒険だった。フランシスコは、1542年1月1日にモザンビークからイグナチオに宛てた手紙で、次のように語っている。「私は2か月間、船酔いに苦しみました。ギニア湾の沖に出るための風を待って、我々は40日間耐えました。船にいる病人の世話をし、私は彼らの告解を聞いて、彼らに聖体を授け、穏やかな死を迎えられるよう助けました。[...中略...]最も厳しい状態の者に専念しています。[...中略...]道中の苦難はあまりにつらく、他のことのためでしたらあと一日たりとも立ち向かうことはできなかったでしょう2」。疲労から、彼は病に倒れ重症となり、9回も瀉血を受けることになった。
ケニアのマリンディにて、フランシスコは初めてイスラム世界と対面した。しかしこの時、彼は当時のカトリック文化の考え方の影響を強く受けていたため、初めて限界(おそらく唯一のものであるが)を示した。そしてこれが彼の布教に影響を与えることとなる。すなわち、イスラム教やヒンズー教、仏教といったキリスト教以外の宗教は、邪悪なものであり、それらを信じる者は、キリスト教に改宗しない限り地獄に落ちると信じていたのである。これは当時のキリスト教徒や神学者に共通する考え方であった。しかし、フランシスコが最も重い罪を犯し布教活動の障害となっているキリスト教徒たちに対しては、慈悲深い態度を示している一方で、非キリスト教徒の人々に対しては、「神は非キリスト教徒のもとにはおらず、彼らの祈りを聞くことはない」(p.122s)と考え、厳しい態度を示していたことには驚かされる。
ゴアやインドの海岸沿いに住むパラバスたちのもとで
1543年5月6日、13か月の旅の末に、ようやくフランシスコ・ザビエルはゴアに到着した。当時ゴアは、アフォンソ・デ・アルブケルケがイスラム教徒から奪った後、東洋から海路ヨーロッパへと向かう香辛料貿易の拠点として、ポルトガル帝国領インドの首都となっていた。ポルトガルの支配は、まだインドの海岸沿いの地域に限定され、内陸には及んでおらず、また支配に際して彼らはしばしば残酷な方法をとったため、住民たちに恐れられていた。
アルブケルケはゴアに病院を建てていた。教皇大使フランシスコ・ザビエルはそこに居を構え、彼の活動拠点とした。入院患者は、航海中の犠牲者たちであり、フランシスコは彼らの要求にいつでも応えられるよう、病人のベッド近くの地べたで寝ながら献身的に奉仕した。午後はいつも、ガレー船の奴隷たちが押し込められた悪臭漂う3つの牢獄を訪れ、彼は不潔な環境や病気感染の危険に少しも恐れを抱くことはなかった。
病院の近くの教会に、彼は宗教教育のための学校をつくり、そこでの教育は、歴史家ジョアン・デ・バロスの信仰の本をもとにしていた。彼は、「道や広場で、子供や大人たちに、教えを聞きに来るよう叫んでいた。教会では教えを彼が詩にしたものを歌うことから始まり、子供たちにそれを繰り返させていた。そして、最もシンプルな方法で、キリスト教の教義を説明し、聴衆が理解できる言葉のみを使用した3」。また毎週日曜日は、隔離病院に行き、ハンセン病患者のためのミサを行った。「私は彼らに秘跡と教えを授けます。彼らは私にとって信頼できる友となりました」(p.126)。
フランシスコのゴアでの滞在は5か月ほど続いた。インド総督アフォンソ・デ・ソーサの要請で、彼は「パラバス」という土着の民族に布教活動を行うために、コモリン岬に派遣された。彼らは真珠貝を求めて海に潜ることを生業とし、タミール語を話していた。フランシスコは、ゴアで学んでいた3人のパラバスたちを通じて、言葉を理解することができた。実はフランシスコは、「言語の才能」があったわけではなかった。東洋の言語のごく一部以外、彼が習得することはなかった。そのため、彼は生涯、常に協力者に頼る必要があったが、これらの協力者たちはポルトガル語の初歩的な知識しか持ち合わせていなかった。「この地のキリスト教徒たちのなかには、彼らに信仰を教える者がいませんでした。彼らは自分たちがキリスト教徒であること以外は何も知りませんでした。彼らのためにミサを行う司祭も、『信徒信経(クレド)』や『主の祈り』『アヴェ・マリア』などの祈りの言葉や十戒を教える者さえいませんでした。この地に到着した時、私はまだ洗礼を受けていない子供たちに洗礼を授けました。それはまだ右と左の区別もできないような大勢の子供たちでした。[...中略...]若者たちが私のもとに押し寄せるので、私は祈りや食事、寝るための時間さえもありませんでした。彼らは熱心に新しい祈りを教えるよう求めました。私は天の国が彼らのものであることを理解し始めていました」(p.147)。
フランシスコは、厳しい環境の中、2年間パラバスたちとともに過ごした。食料は乏しく、ほとんど寝ることなく、夜の大半は祈りに費やし、焼け付くような太陽や激しい雨の中、村から村へと絶えず移動した。彼はタミール語に非常に苦労した。たとえ主要なキリスト教の祈りや教えの翻訳を覚えられたとしても、それを聞き手に理解してもらうのは難しかった。しかしながら、彼自身が放つ情熱や、彼の活動を燃え上がらせる神への愛、そして困難や危険の中、布教活動を続けるその献身ぶり、病人や、貧者、子供たちに対する配慮によって、彼は人々の心をひきつけた。彼らはキリスト教信仰の基礎を習うと、おそらくそれを真に理解していなかったかもしれないが、洗礼を受けることを望んだ。なかには、これは集団洗礼であり、理解の伴わない洗礼だったと言う人がいるかもしれない。とはいえ、ザビエルが宣教活動を行ったインドの地域からも、素晴らしいキリスト教共同体が生まれており、それは今日も存在している。また、フランシスコの一番の懸念は福音を伝える人員の不足であった。「キリスト教を教えることができる人材が不足しているために、人々をキリスト教に改宗させることができないでいます」とフランシスコは1544年1月15日にローマのイエズス会士たちに書いている。「しばしば私は(ヨーロッパの)大学に行きたいという欲求に駆り立てられます。特にパリやソルボンヌへと。そして、そこにいる知識を持ちながらも、それを自身の利益のために使おうと考えている人々に、いったいどれほどの魂が天上の栄光を得られず、その怠慢ゆえに地獄に落ちるかということを、まるで正気を失った人のごとく、あらん限りの大声で叫びたいものです。[...中略...]何千、何百万という異教徒たちが、彼らを助ける司祭さえいるならば、キリスト教徒になるでしょう。キリストの信仰へ改宗しようという人々があまりにも多く、彼らに洗礼を授けるために、私はしばしば腕にしびれを感じ、何度も彼らの言語で『クレド』や祈りの言葉を繰り返しているために完全に声を失うこともあります」(p.106)。
インドからモルッカ諸島へ
フランシスコ・ザビエルがインド南部のサン・トメにいた時に、彼はマカッサル諸島(現在のインドネシア)にいるキリスト教徒たちには、司祭がおらず、信仰の助けがないことを知った。このことは一方で、この遠く離れた地域にも、福音活動によって多くのキリスト教への改宗者を得られる可能性を意味していた。この情報によって、フランシスコはこの地域へ赴きたいという衝動にかられた。そこで、1545年1月1日、コモリン岬から船に乗り込むと、東南アジアのマラッカへと向かった。この地は1511年にアフォンソ・デ・アルブケルケによって征服され、当時東洋からヨーロッパへの香辛料貿易にとっての最も重要な中継地となっていた。
マラッカまでの旅は、嵐や浅瀬の存在、そして海賊たちの横行によって特に危険であった。しかしフランシスコは、最悪な困難に立ち向かう時にも常に神を全面的に信頼し、それゆえいかなる困難も彼を制止することはできなかった。当時世界の最も大きな商業拠点の一つであったマラッカは、耐えられないほどの暑さで過酷な場所であったが、一方で、ポルトガル人の官僚や商人たちがマレー人の女性たちによる多くのハーレムをつくっていた放埒な都市でもあった。
マラッカに足を踏み入れるや否や、フランシスコは説教や、子供たちへの祈りの教え、病人の訪問や告解活動に取り掛かった。彼の布教活動は、マレー語を知らなかったために大きな障害に直面したが、彼は祈りやキリスト教の教えを、わかりやすい形に翻訳しようと努めた。この時、実はフランシスコの真の目的地は、マラッカから1740マイル離れたアンボン島であった。そのため、そのあと彼はマラッカからポルトガル船に乗って出発し、数々の危険の中、スマトラ、ジャワ、セレベスを通って、1546年2月14日にその地に到着した。アンボン島にて3か月間司祭の職務を務め、船乗りや兵士たちの告解を聞き、子供たちに洗礼を授け、日曜日にはマレー語にて説教を行ったのち、5月17日には、小さな船に乗って、モロタイへと向かった。
そこには司祭のいない小さなキリスト教共同体があったのだ。そして、危険な旅の末に、7月の初めに、活火山がそびえる小さな島テルナテに上陸した。
モロタイにて彼は、3か月間、説教を行ったり、告解を聞き、また子供たちにキリスト教について教えながら過ごした。彼を脅かす多くの危険の中、日々彼は死と対峙しなければならなかった。しかしながら、この期間は彼の人生の中で最も精神的慰めにあふれていた時期でもあった。「私はこの島で、これほどにも大きな精神的慰めを感じたことを忘れはしないでしょう。肉体的苦痛をこれほどまでに感じなかったことはありませんでした。私は常に敵がいて、信頼できる仲間の少ない島を通り、肉体的病の治療法がない土地を歩んでいたにもかかわらず[...中略...]。この島は、モロタイと呼ぶよりも、神への希望の島と呼ぶ方がふさわしいでしょう」(p.379)。
テルナテ島にさらに3か月滞在したのち、フランシスコはアンボン島に戻り、そこからマラッカに向けて出航した。彼は食料と睡眠の不足によってひどく消耗していたに違いなかった。しかし、それにもかかわらず、彼は船乗りや兵士、商人たちに対して聖務を続けた。マラッカには6か月滞在し、ここで1547年12月に初めて日本について話されているのを耳にすることになる。彼は過失で殺人を犯してしまったために国から逃げてきた日本人のアンジロウに出会った。アンジロウや日本に行ったことのあるポルトガル人たちから得た情報をもとに、フランシスコはこの遠い日本という国はキリスト教に改宗する可能性があり、彼、もしくはイエズス会の誰かがその地に福音を伝えに行かなければいけないと確信するに至った。しかしそれはすぐには実現しなかった。フランシスコは到着したばかりの8人のイエズス会士たちに職務を割り振り、セイロン島での布教活動を試み、マラッカやモルッカ諸島での活動をイエズス会に報告し、さらにイグナチオに新しいイエズス会士をインドに派遣するよう要請するために、インドに戻らなければならなかったのだ。特にポルトガル王に、ポルトガル人たちの悪しき習慣や、彼らが改宗キリスト教徒たちに対して行っている悪事、さらに彼らが宣教よりもまず第一に自身の政治や商業上の利益を追い求め、布教活動に害を与えていることについて報告しなければならなかった。
実際、これらの難しい任務を遂行するために、フランシスコは多くの時間を費やした。特に、ゴアにキリスト教の学院を創設し、ヨーロッパからやってくる若きイエズス会士たちを教育して、彼らを司祭が必要なさまざまな地域に派遣することに心血を注いだ。この点で、彼はなかなか満足することはなく、時に非常に頑固だったので、彼の指示に従わない者や、なすべき司牧活動を行うことができない者をイエズス会から追放するほどであった。彼は、イエズス会士に人々を神に導くという最も危険な試みに着手するために神に奉仕することを求めた。特に、清貧に生き、最も貧しい作業に従事し、誰からも何も受け取ってはならず、病院や牢獄で奉仕し、船乗りや兵士たちの告解を聞き、子供たちをキリスト教へと導くよう世話をすることを求めたのだ。
インドから日本へ
1549年の4月15日にフランシスコは日本に向けて旅立った。ゴアを出発し、3人の日本人改宗者とともに5月31日にマラッカに到着した。マラッカからは、彼を日本まで連れていくことを申し出た中国人のジャンク船で日本へ向かった。6月24日だった。フランシスコの3000マイルほどの危険に満ちた旅が始まった。彼は神のみを信頼し、運を天に任せていたが、中国人の中国の偶像に対する信仰に苦しめられた。何週間もの不便な船旅と、荒れ狂う嵐の末に、1549年8月15日、ジャンク船はアンジロウの故郷、鹿児島の港に到着した。そして、2か月もたたないうちに、彼はすっかり日本人に魅了された。「日本人は、今日までに発見されたなかで最良の民族です」。フランシスコはゴアに宛てた手紙でこのように書いている(1549年11月5日)。「そして、異教徒のなかに、日本人のような人々を見つけることはできないだろうと私は思います。神について聞くことを彼らは非常に好みます」。実は、彼は日本のことをよく知らなかったために、日本や彼らのキリスト教への改宗の可能性に対して幻想を抱いていた。実際に、改宗はそれほど多くなく、また改宗を進められたのは日本語を話すことができたアンジロウのおかげであった。一方でフランシスコはどんなに頑張っても、言語を習得できなかった。彼にとって日本語はマレー語よりもはるかに難しかったのである。そこでアンジロウにキリスト教の祈りを日本語に翻訳するように頼んだ。しかしアンジロウは日本の仏教の知識が乏しかったために、「神」を翻訳する際に、「大道」という言葉を使用した。これは僧侶にとっては、人を表すのではなく、道徳を表す言葉であった。このように、フランシスコは他の者が話す内容を理解することができず、彼が日本語を話そうとする時は、理解してもらえないか、僧侶たちの笑いの種となっていた。
フランシスコが一番熱望していたのは、天皇のいるミヤコに行くことであった。彼は天皇が日本全国に権限を持っていると信じ、それゆえ、彼から福音の許可を得られれば、日本全国で布教活動をし、改宗させることができると考えていた。残念ながら、フランシスコは天皇が象徴的存在であり、実質的権限は大名や将軍のもとにあることを知らなかったのである。そこで、フランシスコは鹿児島から平戸に向かい、そこからたどたどしいものの何とか日本語を話すことができたフアン・フェルナンデスと日本人の改宗者ベルナルドを引き連れて、彼の人生の中でも最も恐ろしいものとなる旅に出た。
海を旅すれば、当時横行していた海賊に襲われる危険があった。しかし陸を旅すれば、別の問題があった。フェルナンデスが語るところによると、「我々の災難は増すことになりました。我々は二つの袋にすべての荷物を入れていました。それは司祭の着る短白衣一つと、シャツ二、三枚、夜に暖をとるための古い毛布一枚です。と言うのも、日本の宿にはベッドがなかったのです。藁のマットや、木の頭置きがあればいい方でした。夜になると寒さに凍え、空腹でも、時には何も見つけることができず、休める場所がないこともありました。また時には、激しく雪が降っていたり、寒さが厳しいために、足が腫れ、危険で険しいでこぼこの山道に倒れることもありました。我々は貧しく、身なりもみすぼらしく、外国人であったために歓迎されず、子供たちに馬鹿にされたり、石を投げられることさえありました。そうして、何とか博多に到着したのです」。フランシスコとフェルナンデスは、どこに行っても、人々の無理解と、僧侶たちの嘲笑の中で説教を行った。
フランシスコは山口(原文ママ)を不毛の地とみなし、天皇のいるミヤコに行くために、すぐにその地をあとにした。これはフランシスコの人生で最もつらい旅であった。フェルナンデスによると「雪の高さは膝を超え、山からの急流の水は腰まで達していました。フランシスコは一日中裸足で歩いていたので、ある夜足が腫れあがり、血が出て、血の跡が雪の上に残っているのを目にしました」。しかしフランシスコは道中の苦痛などまったく気に留めていなかった。彼は彼の夢が実現しようとしていたことから、栄光の絶頂にいたのである。天皇のいる日本の首都に行けば、天皇がその深い思慮によって、天の王であるキリストに従い、日本の民を十字架のキリストのもとへと導くであろう、と。しかしこの願いはすぐに打ち砕かれることになる。彼は天皇に会えないうえに、貧しくみすぼらしかったために、彼がミヤコの5つの大学だと信じていた寺院にさえも入ることができなかった。そこには、裕福で、身なりの良い人しか入ることが許されなかったからだ。しかしこの失敗にフランシスコが意気消沈することはなかった。彼は日本を統治しているのは天皇ではなく、大内義隆だと知ると(原文ママ)、彼のもとに日本での福音の許可を求めるために赴いた。そして、大使としてスペイン貴族のように絹の衣服を身にまとい、従者を伴い、さらには豪華な贈り物を携えて、彼の前に現れた。義隆はフランシスコを歓迎し、彼に布教活動を許可した。こうして彼は、説教を行ったり、僧侶たちと議論することができるようになったのだが、そのことによってフランシスコは大きな問題に直面した。日本の仏教は中国から来たものである。それではいったいなぜ、中国の賢者たちは、フランシスコが説くこの教えを知らなかったのだろうか。
日本から中国へ
このような反論がフランシスコの人生に新たな転換点をもたらした。日本を改宗させるためには、中国を改宗させる必要がある。そしてこれ以降、彼の意識は中国に向けられた。彼を苦しめた日本を出発した際には、彼は日本に500人ほどのキリスト教徒を残しただけであった。しかし彼にとって重要なことは、新しい福音の道が開けたことだった。そのため、中国に行きたいという彼の思いが潰えそうになったときの失望は、道中や日本滞在中に受けた苦しみよりもはるかに大きかった。なぜなら中国は完全にヨーロッパ人に対して閉鎖的であり、そこに入り込むためには、夜中に中国の地に導いてくれる悪徳商人にお金を払うしかなかったからだ。
フランシスコはこの方法を試すことを望んだ。そうして、ポルトガル人自身がフランシスコにもたらした数々の困難を乗り越え、ようやく1552年10月に中国の海岸から10マイルほどのところにある、上川島に到着することに成功した。ここで、ある商人がコショウ20ピクルで彼を広東に連れていくことを申し出た。フランシスコは、連日彼を待っていたが、商人は姿を現さなかった。フランシスコは上川島から中国に行くすべは絶たれたのではないかと恐れ始めた。そこでシャムに行き、シャムの王の朝貢使節の一員に加わる方策を考えた。しかしこれもまた夢であった。そうこうしている間に、彼とともにマラッカからやってきた者は、アントニオ1人だけになってしまった。彼は中国人だったが、自身の国の言葉はほぼ忘れていた。この年の11月の上川島は非常に寒く、ポルトガル船が出航すると、フランシスコはアントニオと2人だけになった。寒さに凍え、食べるものもなかったために、現地に残っているポルトガル人の商人に少しの食料を恵んでもらうようにとアントニオに頼むほどであった。
このような状況では病気になるのも当然だった。11月21日にまだ上川島に残っていた唯一のポルトガル船であるサンタ・クルス号に乗船することを求めたが、そこで過ごしたのは一晩だけであり、彼は船の横揺れに苦しみ、寒さから身を守るためにもらったズボンと、熱の薬としてのアーモンド一握りを持ってぼろ屋に戻ってきた。しかし熱はどんどん上がっていったために、ポルトガル人の商人は彼に瀉血を施したが、これによって吐き気が悪化し、食べ物を受け付けることさえできなくなった。うわごとを言うようになり、イエズス会の仲間たちを思い出しては、大きな声で神との対話をし、「イエス、ダビデの子、私を憐れみたまえ」と繰り返した。11月28日には、話すこともできなくなり、3日間黙ったままで、人を認識したり、何かを食べることもなかった。12月3日の夜明けに、アントニオはフランシスコの死が近いことを理解し、小さなろうそくに火をともすと、彼の手にそれを持たせた。フランシスコは神の名を唱えながら亡くなった。
彼の死は寂しいもので、聖体を受けることもなかった。彼の遺体は木の棺に入れられ、肉体の融解を早めるために遺体の周りには石灰が詰め込まれた。棺は、深い墓の中に埋められたが、死者のための祈りを唱える者も誰一人いなかった。墓には、埋葬場所の目印として石が置かれただけであった。十字架さえも彼の墓に置かれることはなかった。1552年12月4日のことであった。フランシスコは46歳と8か月の生涯を閉じたのだった。
教皇から彼に託された「ミッション」を果たす
フランシスコ・ザビエルの生涯に思いをはせる者はみな、彼がわずか10、11年の間に成し遂げた偉大な功績に感銘を受けるであろう。陸や海での長い旅路、照り付ける太陽や激しい雨の中、また時には恐ろしい嵐の影響を大きく受けるもろい小舟の上で、空腹やのどの渇き、赤道直下の酷暑や、厳しい冬の寒さ、虫による苦痛、蛇や猛獣の危険にさらされながら、彼は、自由に使いこなせない言語で自分自身を表現するという困難の中でも、常にキリスト教の教えを伝え、告解を聞き、ヒンズー教のバラモンや日本の僧侶と議論することに専念した。
実際、フランシスコ・ザビエルの人生は、肉体的にも精神的にも苦悩に満ちたものであり、数年の間に彼の活力を消耗させたが、いかなる困難や、命の危険でさえも、教皇によって彼に託された「ミッション」を成し遂げることから彼を引き離すことはできなかった。なかには、フランシスコ・ザビエルに対して、絶えず国から国へと移動を続けたことから、彼は他の者に彼の始めた試みを深める任務を託し、彼自身が福音活動を深めるために一つの場所にとどまることができなかったと苦言を呈する者もいた。しかし、この苦言には議論の余地がある。彼は決して彼が福音を伝えた人々のことを忘れることはなく、常に彼らのもとに、彼が始めた試みを維持できる信頼に足る人物を派遣しているのだ。彼の「ミッション」とは、教皇が彼に託した広大な地域に福音の新しい扉を「開ける」ことであると彼は感じていた。実際、彼は経験から、不確かな情報しかない国、その国の言語も社会・政治状況、文化やメンタリティー、宗教さえもわからないような国で、福音活動を始めることがどれほど難しいかを知っていた。特にヨーロッパ人に対して不信感を持つような国の人々の心を福音に対して開くことは、死を意味する可能性があったのであり、そのような危険には、彼のもとにいる他のイエズス会士ではなく、自分自身を差し出すことを望んだのである。
「神の栄光の人」としてのフランシスコ・ザビエル
いったい何がフランシスコ・ザビエルに、福音への新しい道を開くため、これほどの大きな危険に立ち向かわせたのであろうか。その答えを「霊操」の中に見出すことができる。彼は1535年9月にイグナチオ・デ・ロヨラのもとで霊操を行っている。これは3つの柱に基礎を置く精神性である。すなわち、神の栄光を求めることであり、全世界を神や神の国、そして神の愛へと導くためにキリストとともに、キリストのために尽力し、苦しむことであり、イエスのメッセージを受け入れ、唯一の救済の道であるキリストの教えに改宗させることで、人々を救うために「助ける」ことである。つまり人々の犯した罪や、異教崇拝によって失われた栄光を神に与えることへの熱望こそが、フランシスコをキリスト教徒の罪や、異教徒の偶像崇拝に対する困難な戦いへと駆り立てたのである。
しかしフランシスコは特に自身の中に神の栄光を求め、彼の中に「住みついている」罪を自覚し、それゆえ彼は、神がすべてをなすのであり、フランシスコ自身は何もしていないのだと認識していた。彼はシモン・ロドリゲスに次のように書いている。「人々に道を開く恩恵を私に授けてくれるよう、神に願ってください。私は何もしていないのですから」と。それゆえ、彼は神にのみ全面的な信頼を寄せていたのであり、自身や、どれほど強力な人であろうとも他者に対して信頼を寄せることはなかった。彼の最も大きな懸念は、神への信頼を失うことであった。それは彼にとって神の栄光を奪われることを意味した。なぜなら神のみが「偉大」なのであり、栄光と名誉は神にのみ属し、それゆえ神のみが、最も大きな危険から人々を救うことができるのだから。
フランシスコの心の中では、神に最も大きな栄光を与えたいという願いと、悪と戦い、世界を神に導くためにイエス・キリストに従いたいという深い願いが結びついていた。それは力やお金によってではなく、謙虚さをもって、病人や奴隷たちへの奉仕や、貧困、空腹、暑さや寒さに苦しむことを通じて行われるべきものであった。「私は寒さで死ぬであろう」と彼は祈りながら過ごした夜に一度告白している。実際、祈りは彼の力だった。彼は自身の限界や欠点をよく理解し、それらが福音を伝える人々に対する神の恩恵の実践において障害となることを意識していた。それゆえに、彼は祈りに必要な助けを求めたのである。日々の生活の中で彼を直接知っている人はみな、フランシスコが夜の大半を祈りに費やしていたことを証言している。「フランシスコ先生は特に夜に祈っていました。彼が人に見られず、身近なものに対する配慮から彼が解放される時である夜に4」。まさにインドネシアのモロタイにて立ち向かわなければならなかった大きな「危険や苦悩」の中にこそ、先に述べたように、彼は最も強い精神的体験をしたのである。「私はこの島で、これほどにも大きな精神的慰めを感じたことを忘れはしないでしょう。肉体的苦痛をこれほどまでに感じなかったことはありませんでした」(p.379)。
「魂を救済する」
キリストへの愛が、誰にも頼ることなく、ただ神に対する無限の信頼のもと、イグナチオや、彼のイエズス会の仲間たちの祈りの中でフランシスコを日々死の危険に立ち向かわせていたのであれば、同時にキリストの十字架での死によって救われた人々を永遠の苦悩から解放したいという欲求もまた彼を突き動かしていた。誰一人として、洗礼を受けキリスト教徒になることなく救われることはないのであって、ヒンズー教や仏教のような異教は誤りであるだけでなく、偶像崇拝であり、むしろ悪魔的であるとみなす考えは、彼の時代のカトリック神学に共通のものであった。このことは、フランシスコが大人から子供に至るまで多くの人々に、キリスト教の簡潔な教えだけで、そして彼ができるだけ丁寧に説明した「クレド」に対する信仰へ
の同意を得るだけで、洗礼を授けることに尽力したことを説明している。また一方で、異教に対する彼の評価の厳しさも説明している。つまりフランシスコ・ザビエルは「彼の時代の申し子」だったのだ。
彼が彼の精神の奥底で感じていたもの、そして彼を恐ろしい犠牲や危険に立ち向かわせたものが、彼が死の直前に上川島で書いた手紙の中に記されている。「これらの場所で我々がしようとすることとは、人々をその創造主である我々の主イエス・キリストの知るところとすることです。我々は神を信頼し、彼が我々に力や恩恵、助けや、人々を導く力を与えてくれることを信じています。[...中略...]彼はそのことをよく知っておられます。なぜなら、魂を救うことを求める欲求は我々の心に現れているからです」。フランシスコ・ザビエルのすべてがこの表現の中に表れている。神の栄光とイエス・キリストへの愛のために、「魂を救済すること」。そして福音はまさにその救済の唯一のメッセージなのである。それゆえ、人々に福音をもたらすことは、彼らに対してなしえる最高の愛の行為であり、いかなる困難にも立ち向かい、自身の命さえをも捧げる価値のあることなのだ。これこそが、中国へ入ることを待ち望みながら1552年12月3日に極貧の中、究極の孤独のうちに死んでいったフランシスコ・ザビエルが我々の時代の人々に残したものなのである。
さらに同じ年の10月6日、その30年後に中国に入り、北京の皇帝の宮廷にまで到達することに成功した人物、マテオ・リッチがマチェラータにて誕生した。こうして、フランシスコ・ザビエルの最後の偉大な夢は、実現することになる。マラッカからポルトガルのイエズス会士に宛てて書かれた1554年12月3日の手紙にはこう書かれている。「中国を目の前にして死んだ一粒の小麦こそ、我々のフランシスコ神父です。我々が今その実を収穫できているのは、我々の主、神が彼のもとに多くの穂をもたらした証なのです」。中国の地に植えられた麦の一粒は、今日においても実を実らせ続けている。中国での宣教活動が今日イエズス会の司牧活動の重要なもののひとつであることは、決して偶然ではないのだ。
2 G. Schurhammer – J. Wicki, Epistolae S. Francisci Xaverii aliaque eius scripta, vol. I, Romae, 1944-45, 91-93(以後本文献の引用は本文内にページ数のみ記載)
3 MHSJ, Monumenta Xaveriana, vol. II, cit., 842-844.
4 Ivi, 859.
ウイルスは神の罰なのか?
Il virus è una punizione di Dio?
David M. Neuhaus S.I.
デイヴィッド・M・ノイハウス神父
世界中をいまなお震撼させている
新型コロナウイルス。
この禍に込められた神のメッセージとは。
La Civiltà Cattolica 2020 II 238-243
「『夜になった(マルコによる福音書4,35)』。現在、世界はパンデミックを引き起こしたウイルスによってまるで夜が訪れたかのようです。広場や道、町に深い闇が立ち込め、我々の命が奪われ、ウイルスは通る道にあるものすべてを麻痺させて、静寂と痛ましい空虚がすべてを埋め尽くしています。それは空気の中や、人々のしぐさ、視線の中にも感じられます。我々は恐れ、困惑しています。福音書の使徒たちのように、我々は予想もしていなかった恐ろしい嵐に突然襲われたのです1」。教皇フランシスコの感動的な説教の言葉は、人気のないサン・ピエトロ広場やサン・ピエトロ大聖堂をバックに響き渡った。それは多くの人の命を奪った新型コロナウイルスの蔓延によって混乱した世界を慰め、励ます行為であった。
聖書を操る「災いの預言者」
聖書を真に愛する者は、現代のコロナウイルスのような危機をほのめかしているともとれるような聖書の一節を、自分の都合のいいように使っている人がいることに困惑するだろう。つまり聖書が文脈から分離され、無理やり現実にあてはめられているのである。「災いの預言者」たちは、現在のパンデミックが罪深い世界に対して怒れる神の罰であると宣言するために、聖書を利用している。彼らは彼らの感覚に反するものすべてを攻撃するために、聖書を引用し、すでに傷ついた人々に対して聖書を武器に残忍にふるまっているのである。むしろ、罰せられるべき世界に対して、怒れる神によってもたらされた災害を記した聖書を引用することに、彼らは満足すら感じているようだ。
これらの神の怒りによって活気づく自称預言者たちとともに姿を現すのが、「だからそう言っていただろう(言わんこっちゃない)」と主張するモラリストたちである。彼らは世界に対して彼らが正しいと信じていることを主張するために、聖書を細かく検討し、彼らの信念がより良い世界を探求するための方法であるということが今こそ認められるべきだと感じている。このような「災いの預言者」も、「そう言っていただろう」と主張するモラリストたちも、コロナウイルスの危機は、聖書の世界に見られる神の罰にあてはめられると確信しているように思われる。
ダビデ王とペストの場合
聖書の中には、これらの「災いの預言者」たちが現在のパンデミック(この言葉は現代版のペストを思わせる)の状況を言い当てていると感じるような非常に痛ましい記述も存在する。なかでも最も明確なのは、『サムエル記下』24章の、ダビデの物語に付随する記述である。この章は恐怖を誘う言葉で始まる。「主の怒りが再びイスラエルに対して燃え上がった」(『サムエル記下』24,1)2。なぜなのか?ダビデが軍司令官のヨアブの反対にもかかわらず、人口調査を命じたからである。抜け目ないヨアブは、この行為が主の言葉に反するものであることを自覚していたと思われる。と言うのも、人口調査は神殿のための金銭徴収と密接に結びついていたからである。実際、『出エジプト記』に次のように書かれている。「あなたがイスラエルの人々の人口を調査して、彼らを登録させる時、登録に際して、各自は命の代償を主に支払わねばならない。登録することによって彼らに災いがふりかからぬためである」(『出エジプト記』30,12)。
実は繫栄した民を数えることは、先祖との間に結ばれた契約をかなえてくれた神に対する感謝の行為に通じるものであるはずだった。「私は、あなたとの間に私の契約を立て、あなたをますます増やすであろう」(『創世記』17,2)。しかしダビデは、おきてを無視して人口調査を命じ、かつて神が望まなかった神の家をつくらせることを望み(『サムエル記下』7章参照)、バト・シェバを自分のものとするために彼女の夫を殺すよう仕向けた時に見せたのと同じように(『サムエル記下』12章参照)、自身が神に代わりうる存在であり、彼こそが民の力の源であることを誇示しようとしたのだ。
ダビデは人口調査を行ったのちに後悔するものの3、聖書は神が恐ろしい代償を求めたことを告げている。神はダビデに7年間の飢饉か、3か月間敵に追われて逃げることか、3日間の疫病から選ぶよう告げる。ダビデは自分が敵の手に落ちることだけはないよう神に懇願した。「主は、その朝から定められた日数の間、イスラエルに疫病をもたらされた。ダンからベエル・シェバまでの民のうち7万人が死んだ」(『サムエル記下』24,15)。主の御使いがその手をエルサレムに伸ばした際、ようやく主は御使いにこう告げる。「もう十分だ。その手を下ろせ」(『サムエル記下』24,16)と。神が考えを変えたのは、ダビデが自身の罪の責任を自身で引き受けようとしたからである。「ご覧ください、罪を犯したのは私です。私が悪かったのです。この羊の群れが何をしたのでしょうか。どうか御手が私と私の父の家に下りますように」(『サムエル記下』24,17)。
誤った読み方から正しい解釈へ
まさにここがポイントである。ここには罪と怒り、冒瀆と不吉な結果がともに存在している。しかしこの部分を文脈から引きはがし、先に述べた「災いの預言者」たちは、現在の危機は(それ以前は洪水やハリケーン、火山の噴火や津波、エイズ、その他さまざまな自然災害や人的災害に対して)まさに聖書の中に記されているように、罪と怒りのしるしなのであると主張しようとしている。しかしこの結論は、文脈(歴史的な文脈であれ、物語の文脈であれ)、書き手の意図、そしてそこにある神学的メッセージを無視して、誤った解釈をもたらすであろうことを強調する必要がある。人口調査の話は、『ヨシュア記』で神との約束の地に入ったところから始まり、エルサレムの神殿の破壊まで途切れることなく続く長い話の一部をなすものである。この長い物語は、紀元前6世紀中ごろに書かれた。これが書かれた当時の喫緊の問題とは、ソロモン王によって建設された神殿やエルサレムの町の破壊、そしてその結果生じたバビロン捕囚という災難について考察することであった。つまりこの物語が答えるべき問題とは、いったいなぜ神がヨシュアに与えた土地が、バビロニアの侵入によって奪われるようなことが起きてしまったのか?というものであった。
これらの物語は、すべて破壊の文脈の中で書かれている。つまりすべては失われてしまったということを背景にしているのだ。民はその責任を負って、神に許しを請うために自身の歴史を読まなければならなかった。聖書の記述は、神の罰として疫病を肯定しようとしているのではない。むしろ、民がダビデのように、エルサレムからの追放をもたらした一連の出来事の自身の責任を認めることの必要性を説いているのである4。
もちろん、聖書の中の創造主神の理解に基づいて、すべての原因を神に結び付け、個人、あるいは集団によってかつてなされた罪と不幸な災害を結び付けようとする宗教的メンタリティーがまだここには存在している。その後、預言者たちによって(例えば『エゼキエル書』)、各々が自分自身の罪の報いを受けるというように「修正」がなされたのち、イエス自身がこの罪と罰との間の密接な因果関係に対する宗教的倫理に反論することになる(シロアムの塔(『ルカによる福音書』13章/訳者注)や生まれつき目が見えない人(『ヨハネによる福音書』9章/訳者注)のエピソードが示しているように)。
新約聖書における災い
ダビデの人口調査のような破壊的な聖書の物語は、旧約聖書にとどまるものではない。『ヨハネの黙示録』の中にも、疫病のイメージは使われている。
16章では、エジプトのそれを思わせるような恐ろしい疫病の数々が、罪深き民を襲っている。天の声が、7人の天使たちに命じる。「行って、7つの鉢に盛られた神の怒りを地上に注ぎなさい」(『黙示録』16,1)。そこで地上には、「悪性のはれ物」(同2)がもたらされ、海は「死人の血のように」(同3)なり、「川と水の源に注ぐと、水は血になった」(同4)のであり、「人間は、激しい熱で焼かれ」(同9)、「闇に覆われ」(同10)、「(ユーフラテスの)川の水がかれて」(同12)、「一タラントンの重さほどの大粒の雹が、天から人々の上に降った」(同21)。
これが『ヨハネの黙示録』第16章で描かれる天変地異の様子である。このことからも、信仰のない世界にふりかかった神の罰と推論することができるかもしれない。実際、この文章は現在の「災いの預言者」たちが、自分たちは関係ないと感じている世界を非難するために何度も使っている多くのイメージを含んでいる。しかし本当に、この文章が現在パンデミックに苦しむ世界に言おうとしていることなのだろうか。
もしこれを文脈から取り出してしまうと、この文章の本質的な意味は失われてしまう。『ヨハネの黙示録』の中では、旧約聖書の終末的預言と同様に、3つの要素、すなわち認識、明確なビジョン、答えとが密接に絡み合っている。
この記述では時間、つまり過去と現在を見極め、この世界に配置された力関係や、神の側についたものの立場を明確に認識している。
この認識のもとに、未来の輪郭は思慮され、形作られていく。すなわち、この文章はキリストが戦いにすでに勝利し、たとえどんなに長くかかろうとも最終的には必ず悪が打ち負かされるであろうという深い信仰に基づいたビジョンを提供しているのである。
そして最終的にこの記述は、災いの預言では解決できない答えを求めている。むしろすべては、どのようにしてキリスト教徒が自身の生を光へと、すなわち最終的にはキリストが勝利するという意識へと転換できるかにかかっているのだ。彼らは積極的に証言し、世界を変えるよう努力しなければいけない。世界を救うために自身をささげたイエスにならって、神の王国を構築するために行動することが求められている。
正典の最後である『ヨハネの黙示録』は、我々により深い信仰、深い改心、そして神の王国へのより深いノスタルジーを感じさせるよういざなっているのだ。
今日の試練のためのミッション
『ヨハネの黙示録』は、まさに現在、恐怖や非難、閉鎖や孤独に満ちた文化を広げないよう教会が求められていることを思い出させる。もし世界が恐怖の上に構築された未来のビジョンを示しているのであれば、教会はそれに対して、聖書や黙示録のメッセージをもとに、それとは異なるビジョン、つまりキリストの勝利という良き知らせによって構築されたビジョンを提供しなければいけない。すべてが闇だと思われる時、闇の時代は終わり、神の到来が近いこと、そして教会が祈りによってこの神の到来を準備していることを伝えるために、イエスの弟子たちは呼ばれたのである。聖書の中の神の言葉は、良き知らせを伝えるように読まれなければならないのであり、危機的状況の世界に改心を求め、道徳的評価を下したり、災害の預言を伝えることではないのだ。神の言葉は、「作り上げ、慰め、励ますために」宣言されるべきであり、誤った解釈によって精神を虐げたり、抑圧するためのものではないのである。
聖書の最初から最後までを貫く一つのテーマが存在する。それは、罪や闇、死が勝つことを、過去においても、現在、そして未来においても、神が決して許すことはないということである。2020年3月27日の「ことば(ローマと全世界へ)」において、教皇フランシスコはこの良き知らせを人々に告げ、危機を神の罰とみなす傾向を覆した。コロナウイルスに襲われている我々の世界から主と向き合い、こう述べている。「我々はこの試練の時を、選択の時として受け入れるよう求められています。あなたの判断の時なのではなく、私たちの判断の時です。何が重要であり、何が去っていくものかを選ぶ時であり、必要なものを必要ないものから引き離す時です。主や他者に対して分断してしまった生を再び考え直す時なのです(コリントの信徒への手紙114,3参照)」。
2 まるでこれだけでは十分ではないかのように聖書はさらに次のように続く。「主は『イスラエルとユダの人口を数えよ』とダビデを誘われた」(『サムエル記下』24,1)。この記述は、その2、3世紀後に同じ歴史を書いた歴代誌作家を驚かせ、それゆえ歴代誌ではこの提案は神ではなくサタンによるものであると記されている。「サタンがイスラエルに対して立ち、イスラエルの人口を数えるようにダビデを誘った」(『歴代誌上』21,1)。
3 「私は重い罪を犯しました。主よ、どうかしもべの悪をお見逃しください。大変愚かなことをしました」(『サムエル記下』24,10)。
4 さらに、聖書はここで終わっていないことを強調するべきであろう。キリスト教の正典において、これらの話はすべて歴代誌の中で再度語られている(さらに話は『エズラ記』や『ネヘミヤ記』において追放後の帰還や、神殿の再建まで続いていく)。またこれらは本質的には同じ出来事を語っているとはいえ、今回の紀元前4世紀の著者は悔い改めの教訓を目的としているわけではない。物語全体が、まったく異なる目的のために書かれている。というのもここでの教えとは、死や破壊、追放に決して敗れることのない神の恩恵に対する感謝に関するものであるからだ。乾いた骨は復活によって生きた肉によって覆われ、キュロス2世が追放者たちにエルサレムに戻り、神殿の再建を認めた時、民は再び正義の中に生きる機会を得た。さらにカトリックの聖書では『トビト記』から『マカバイ記2』までを正典とし、これらの出来事のさらに続きを提示している。最初の2つが許しを請い、感謝することを中心としているならば、3つ目以降は信仰の英雄たち、トビトやユディト、エステル、マカバイ、そして『マカバイ記2』の中の2件の殉教者たちを紹介する内容となっている。彼らは神や人に対する愛のもとでの正しい生き方の模範例を示している。
ダンテとイエズス会士
Dante e i gesuiti
Giandomenico Mucci S.I.
ジャンドメニコ・ムッチ神父
ダンテに対して批判的だった
といわれるイエズス会。
2021年はダンテの没後700年です。
それを記念して、
イエズス会のダンテへの
敬意を改めて考察します。
La Civiltà Cattolica 2020 IV 291-296
1965年のダンテ生誕700年を記念して、本誌では2つの論文を発表した。これは、ダンテの『神曲』に対するイエズス会の見解として、イタリア人が持っているステレオタイプな考え方を論破することが目的だった1。というのも、18世紀にダンテに対する否定的意見を述べたことで知られるイエズス会士サヴェーリオ・ベッティネッリ神父以降、彼の意見をまるでイエズス会全体のものであるかのように取り上げるイタリア文学史の概説書(マニュアル本)や、批評家たちは枚挙にいとまがないからだ。すなわち、イエズス会士たちがまるでこの詩人を破門しているかのような意見である。
確かにイエズス会の学校において、ダンテは古代の作家のようには生徒たちに奨励されなかったことは事実である。しかし、これは学校のカリキュラムで、イタリア語教育にあてられた時間が非常に少なかったことにもよる。また、これらの学校において、いわゆる「アカデミー」を形成していた選り抜きの若者たちには、その後のLecturae Dantisへとつながるような様式で『神曲』を読むことが認められていた。
擁護目的
イエズス会士の教師たちが、ダンテの詩を奨励することに戸惑いを感じていたこともあるかもしれない。それはイエズス会の学校が発展していた時代であると同時に、まさに西洋のキリスト教が批判によって分裂していた時代であり、ヨーロッパの大部分において教皇庁の組織自体が批判にさらされていた時代であった。そして偉大な詩人ダンテの詩のなかには、何人かの教皇の悪徳や弱さを公然と批判しているものがあり、それゆえ当時の若手の心にとってこれらが良い影響を与えるとは思われるはずがなかったのだ。
そのような状況下で、まさに聖ロベルト・ベッラルミーノこそ、ダンテを評価した最初のイエズス会士の一人であり、擁護目的でこの詩人の研究を始めた人物である。彼はダンテの作品の価値と、ダンテ自身のカトリック信仰の正統性、そして時に預言的な態度を帯び、歴史的な教皇の業績とは相いれない彼の政治思想を表明する際に用いた辛辣さというものを区別した。ベッラルミーノは純粋に詩人としてのダンテの才能に基づく解釈を打ち出し、教皇庁や教会の敵として、またマニ教徒やカバラ主義者、言葉の真の意味を隠すためにわざと秘教的な言葉を使うような秘密結社のメンバーとしてダンテを拒否していた人々に道を示した2。これは二重の意味で擁護的な方法だった。つまり詩人としての素晴らしい技術を称賛することでダンテ自身の擁護であり、また同時に教皇庁が信仰の教えを否定しようとしているという批判から詩人を解放することで、教皇庁自体の擁護でもあったのだ。
そしてこれは、ダンテに対してその後のイエズス会士がとった方法でもある。例えば19世紀のイタリアで、国家統一を目指す自由主義者たちがダンテを彼らのシンボルとし、ダンテの反教皇的発言を教皇の聖俗両権限に対する自由主義の闘争に利用した際、本誌の創設者であるジョヴァンニ・バッティスタ・ピアンチャーニ神父やカルロ・マリア・クルチ神父のようにダンテの『神曲』に精通していたイエズス会士たちは、詩人の信仰の正統性を擁護した。クルチ神父は詩に最小限のコメントのみを付け、“散歩や旅行にも”持っていくことができ、どこでも読めるようないわゆる文庫版の『神曲』を一般向けに出版している。
イエズス会士たちがダンテを重要視し、愛していた証拠として、17世紀の2人のイエズス会士の名前を挙げることができる。一人目はダニエッロ・バルトーリ神父だ。彼はレオパルディが「イタリア散文のダンテ」と称した人物であり、ダンテの考え方や表現を広く引用することを好んだ。もう一人はカルロ・ダクイーノ神父であり、彼は『神曲』のほぼ全文をラテン語のヘクサメトロン形式の詩に翻訳している3。
イエズス会の文学史研究者たち
イエズス会士における文学史研究者の中で、まず最初に挙げるべきなのは、フランチェスコ・サヴェーリオ・クアドリオ神父であろう。彼は18世紀に7巻本で出された『すべての詩の歴史と原理について』の著者であり、この本は世界中の文学作品の百科全書のようなものだった。その中で彼は世界中のあらゆる時代の詩の起源、性質、歴史を研究している。ダンテに関してはそれぞれの巻の中でさまざまな作品が引用されているが、なかでも『神曲』とその初版の歴史が取り上げられている。
さらにジローラモ・ティラボスキ神父の名前も挙げられるだろう。彼はフォスコロや、デ・サンクティスらが高く評価した記念碑的作品である『イタリア文学の歴史』の著者である。ダンテはその中で、「非常に鮮やかな空想力、鋭い天賦の才能、そして生き生きとしたイメージや、優しく情熱的な様相、その他のさまざまな装飾が現れては消えていくような卓越した、時に哀れを誘い、時にエネルギッシュなその様式」が称賛され、「そのことが彼の中にある欠点を十分補っている」と記されている。そして例の悪名高い『ウェルギリウス的書簡』を書いたサヴェーリオ・ベッティネッリである。詩人ヴィンチェンツォ・モンティは、小さな復讐として、彼について次のように記している。「ここにベッティネッリが眠る。自分が書いたことを忘れ去られるのを見た人物が」。しかしこの預言は一部しか実現していない。なぜならこの18世紀のイエズス会士は、過激で行き過ぎていた面もあるものの、彼の時代のイタリア文化に大改革をもたらし、文学史に大きく貢献したことだけでなく、ダンテを酷評したことでもいまだに記憶されているからだ4。
すでに言及したように、ベッティネッリのアンチダンテの態度はあくまで彼の個人的な考えを表明していたのであり、そのようなポジションをイエズス会全体がとっていたわけではない。実際、ベッティネッリがこの文学的過ちを犯すとすぐに、イエズス会は彼をパルマの学校の教師の職から、ヴェローナで霊操を指導する職へと異動させている。一方で何人かのフランス人のイエズス会士たちからはベッティネッリに賛辞が寄せられることもあった。なぜなら当時のフランスはアンチダンテで有名なヴォルテールが君臨していたからである。またイタリアでは、『ウェルギリウス的書簡』はチェザロッティや、ジョーヴィオ、ヴェッリなどによって称賛されていた。
ダンテの賛美者として、18世紀のもう一人のイエズス会士、アンドレア・ルッビ神父も忘れてはいけない。ヴェネツィア出身の彼は、56巻にわたる『イタリアの詩人たち』の著者であり、そのうちの3巻分で『神曲』と、詩人ダンテの生涯、彼の作品のリスト、そしてダンテとミケランジェロとの比較が取り上げられている。
19世紀の中ごろには、オルヴィエートの学校の文学教師であったヴァレリアーノ・カルデッラ神父が、生徒が使用するための『神曲』の本を出版し、彼らが「詩の奇跡の中にあふれる智」を味わえるよう促した。
イエズス会士の注釈者
19世紀から20世紀にかけて、イエズス会士の中には『神曲』の注釈者たちも存在する。イタリア人イエズス会士たちがダンテに対して関心を持っていた証拠として、ここに何人かの名前を紹介したいと思うが、その前にまずは18世紀の著名な先人についても触れておこう。それはポンペオ・ヴェントゥーリ神父であり、彼のダンテの詩に対する注釈は1870年までに30版以上にも及んだ。この注釈の編集の歴史は波瀾万丈なものであるが、これに関して詳しく知りたい方はモンドローネの研究を参照してもらいたい。ここではヴェントゥーリの著作が、ヴィーコの称賛を得ていたことだけを触れるにとどめたい。またクローチェも、このヴェントゥーリの著作に「ヴィーコが称賛するものすべてが含まれ、逆に彼が省略する方がいいと判断したものは含まれていない」5と記している。
ヴェントゥーリの1世紀半後に、ジョヴァンニ・コルノルディ神父による『神曲』の注釈が出版された。それはまさにレオ13世がカトリックの学校にトマス主義を復活させようとしていた時であり、ローマにダンテを教える教師の職ができた時であった。また逆の立場から、詩人の教皇庁への悪口を脚色し、教皇庁に対する武器にしようとする明らかな意図のもと、フリーメーソンも同様のダンテ専門教師の職を「ローマ・サピエンツァ大学」に創設し、その職をカルドゥッチに提案した。しかし、彼はフリーメーソンではあったものの拒否した。ボヴィオ大臣の名のもとに彼に要請していたフリーメーソンの偉大な師アドリアーノ・レンミに対して、彼は政府の目的に異議を唱え、ダンテは明らかに完全なるカトリックであったと答えている。まさにこの時、カトリックの側でも、『神曲』に対して、この作品の偉大な作者の真の精神にもとづいた注釈を行う必要を感じていたのだ。
その任務を引き受けたのが、コルノルディであった。彼は「ラ・チビルタ・カットリカ」の執筆者の一人であり、当時のトマス主義の立場から、詩の哲学、神学、歴史、倫理、政治、禁欲主義の立場を明確にして注釈を作成した。しかしダンテの注釈者たちによって議論されていた問題にあまりにこだわりすぎているために、彼の著作はダンテ研究者にとっては有益であったものの、学生には向かなかった。実際ダンテ研究者たちはこの著作を非常に評価しているのであるが。
それから約10年後、グレゴリアン大学の神学者ドメニコ・パルミエーリ神父によって、トマス哲学ではない立場からの注釈が出された。3巻にわたるその著作において、著者の関心は詩人としてのダンテに直接向けられたのではなく、彼のカトリック教義や反教皇派の考え(ギベッリーニ主義)、その他の教義の問題や中世の哲学的潮流に対してであった。そのためこの注釈はすぐにダンテ研究者たちの議論に貢献することになるのだが、その一方でこれも教育にはあまり向いていなかったと言える。
19世紀に「ラ・チビルタ・カットリカ」に関わっていたダンテ研究者の中で、言及すべきはカルロ・ピッチリッロ神父とフランチェスコ・ベラルディネッリ神父であろう。彼らこそ、本誌で定期的に出されていたダンテの評論を書いていた人物である。またティート・ボッタジジオ神父は、バチカン文書館で教皇の記録を用いて、ボニファティウス8世とケレスティヌス5世やダンテ、フィレンツェ、フランス王フィリップ4世との関係を研究し、ダンテや、彼の作品をドイツ語に翻訳したスカルタッツィーニらによる批判から教皇を擁護することに努めた。
20世紀には、「ラ・チビルタ・カットリカ」の執筆者メンバーの中に偉大なダンテ研究者であり、今日においても専門家の間に名の知られているジョヴァンニ・ブスネッリ(1866-1944)が現れる。最も著名なダンテ研究者であるフラミーニ、グラブマン、パローディ、マンドネ、ピエトロボーノ、ドヴィーディオらはみな彼の友人や同僚であり、場合によっては彼らの解釈の敵でもあった。文学の分野の博識者であった彼は、特にフォスコロやレオパルディ、マンゾーニを研究していたが、ダンテ研究を自身の専門とし、哲学や言語学、神学的観点からではなく注釈者としてダンテ研究を行った。ダンテに関してイタリア内外で出版されたものはすべて、彼の関心や洗練された批判、広い文化的知識の対象であり、他者の研究としてとらえるだけでなく、それらを自身の研究にも貢献させていた。また彼は「ラ・チビルタ・カットリカ」や、「ダンテ新聞」に普段からよく協力していた。
著作や論文(時に内容の点で本にも匹敵するものであるが)の中で、ブスネッリは彼の時代のダンテ研究者たちが議論していた問題の大部分を扱っている。しかし彼が最も専念し、その類まれなる力を発揮した作品は、『饗宴』であった。彼はジュゼッペ・ヴァンデッリとともに注釈を書き、ミケーレ・バルビの巻頭論文を付けた2巻本の形で、『饗宴』を1934年にル・モニエ社から出版している。
中世の教育的作品であり、哲学的示唆に富んだ作品である『饗宴』は、ダンテの作品の中で、研究者たちが最も彼らの精神や関心から遠いと感じている作品である。しかしブスネッリはさまざまな作品を研究してきたが、この作品に『神曲』に劣らない関心を寄せ、身近に感じていた。少なくとも全2巻のうちの3分の2にわたってびっしり詰まった彼の注釈を見た者は、そこに表された博識に驚くであろう。彼は1925年からヴァンデッリとともに注釈を作成していたが、これは2人のダンテ研究者の密接な書簡を通じて行われており、この書簡集もまた、ダンテの作品の言語学的考察におけるブスネッリの重要な資料である。
我々は本稿において、ベッティネッリから出発し、彼のダンテに対する意見が3世紀もの間、イエズス会がこの偉大なフィレンツェの詩人とその作品に対して敵対しているという中傷のもととなってきたことを取り上げた。18世紀にイエズス会を取り巻いていた状況は、強力な敵の存在に対して仲間の力が弱かったこともあり、イエズス会が一時解散することにつながった。まさにその中で、これらの中傷が根付いてきたのである。さらに時間がたつにつれ、それが人々の無意識の中に溶け込んでいった。純粋に主観的な意見であったものから、議論の余地のない客観的な真実へと変化してしまったのである。
しかし本稿では、イタリアにおいてイエズス会がダンテに絶えず寄せてきた敬意について言及してきた。まさにこの詩人の死後700年を記念する今こそ、イエズス会が、優秀なイエズス会士たちの研究を通じて、その偉大な才能により教会とカトリック信仰を照らしていたダンテに対して常に関心と尊敬を表明してきたことを、本稿が証明できれば幸いである。
2 A. Valensin, Il cristianesimo di Dante, Roma, Paoline, 1964, 11を参照。
3 P. Chiti, «Un insigne latinista ammiratore e traduttore di Dante. Il P. Carlo D’Aquino (1654-1737)», in La Civiltà Cattolica 1960, I, 250-267参照。
4 G. Natali, Il Settecento, Milano, Vallardi, 1929, 1157参照。
5 B. Croce, «Il “Giudizio su Dante” di G. B. Vico e il “Commento” di Pompeo Venturi», in La Critica 25 (1927) , 407-410.
『沈黙─サイレンス─』
マーティン・スコセッシ監督への
インタビュー
«Silence». Intervista a Martin Scorsese
Antonio Spadaro S.I., direttore
アントニオ・スパダーロ 編集長
遠藤周作の名作小説『沈黙』。
それを『沈黙─サイレンス─』として
見事に映画化したスコセッシ監督に、
La Civiltà Cattolica編集長の
スパダーロ神父が対峙。
作品の意味、また彼自身の思いを、
精緻に追った
ロング・インタビュー全文を公開。
必読です。
La Civiltà Cattolica No. 2016 IV 565-586
2016年3月3日、私はニューヨークのスコセッシ監督の家の呼び鈴を鳴らした。それは寒く、晴れた日のことだった。13時に、キッチンに迎え入れられた。その上、おいしいコーヒーはどうかと勧めてもらった。正確には「イタリア式コーヒー」を。もちろんありがたくいただいた。私は寒さに凍えていた。スコセッシ監督の家には約束の時間よりも早く着いていたので、一人で近くを散歩していたのだ。温かいコーヒーの申し出は、――それもイタリア式の――魅力的だった。居間で迎えてくれたのは、マーティンの妻のヘレンだった。私はまるで家にいるかのように感じた。彼女の夫が来るまで、私たちはしばらく話をした。私は彼女に1冊の本を渡した。『親愛なる教皇フランシスコ』、それは世界中の30人の子供たちから教皇に寄せられた質問とそれに対する教皇の答えを集めたものである。私は彼女にそのプロジェクトに関して、どのようにしてそれを実現したのかを話した。ヘレンは感心しながらページをめくり、挿絵に夢中になった。私は彼女を見ていた。私たちは同じソファーに座っていた。彼女は私に夫や、17歳の娘、映画のことを話した。私は『沈黙─サイレンス─』がある意味で、家族全員が関わった家族の作品であるのだと理解した。
そのうちに、マーティンが足早に、笑顔で現れた。映画の話をする前に、私たちは共通の出身地について話した。私たちは、ある意味「同郷人」なのだ。彼は私がメッシーナ出身であることを知っていた。彼は私に、シチリアのポリッツィ・ジェネローザ出身だと言った。いや、正確には彼の父がそこ出身だったのだ。しかし彼にとっては、彼の起源がそこにあった。ポリッツィ・ジェネローザは、文学者で政治批評家のジュゼッペ・アントニオ・ボルジェーゼや、レオ13世の国務長官であり、教皇に選ばれる可能性も高かった枢機卿マリアーノ・ランポッラの出身地である。マーティンはヴィンセント・スキアヴェッリやドメニコ・ドルチェ、ミケーレ・セッラと遠縁だった。
しかし我々はこのような同郷の有名人ではなく、ニューヨークにやってきた移民の息子としての彼の人生について、ミサで司祭の補佐をする侍者役をしていた彼の子供時代について話した。そこから、血や暴力と聖なるものの絡まりが浮き彫りとなった。教会での侍者としての記憶は、無意識のうちに彼の映画人生の第一歩を歩み始めた子供時代の記憶と混ざり合っている。つまり彼の想像と夢の世界と。いや、まだ私はインタビューを始めてはいなかった。我々の会話は友人間のものであり、今となっては録音していなかったことが悔やまれる。しかしだからこそ、この自然な会話の流れが維持されたのだ。その時に私は、彼にとって聖なるものと暴力とがはるかかなたで起源を同じくしていることを理解した。彼にとって宗教とは天使たちによるものではなく、人間のものなのだ。彼が私に話す内容には恩恵が宿っている。そして彼の眼は揺らめきながら、それを示している。「私はある種の恩恵に包まれているんです」。彼は笑顔で言った。そして妻を見た。彼が私に話す恩恵とは、埃や影なくしては決して理解できないものであろう。彼は私に映画の写真をいくつか見せた。それはとても美しかった。
こうして『沈黙』についての会話が始まった。質問と返答が飛び交った。まさに、事前の8か月の間のメールのやり取りや、彼の発言の書き起こしから進められてきた2人の実験がスタートしたのだ。これはインタビューと言うよりも、良識の糾明、感覚の実験だった。彼のおかげである。また、私は自分がある種のきっかけとなっていたことに気が付いた。時々私は、私の神父としての立襟を、マーティン・スコセッシは、インタビューの中で語っていたプリンチペ神父の襟と同じものとみなしていたのだろうかと思うことがあった。彼の家から出たのは3時半だった。外は来た時に比べて寒さがましになっていた。家に帰るために、私はセントラルパーク沿いを進んだ。
私が再びスコセッシ監督に会ったのは、11月25日、ローマでのことだった。午後5時だった。彼のホテルに時間より早く着いた私は、まるで印象派の画家が描いたかのような夕焼けの空を楽しんでいた。まもなくヘレンが帰ってきた。彼女の顔を見ると、不思議と彼女にしばらくぶりに会ったとは思えなかった。我々は紅茶を飲むために座った。いや、実際には紅茶を飲んだのは私である。彼女は水を飲んでいた。私たちはそこで話し込み、私は彼女の夫に会いにそこに来ていたことをすっかり忘れていた。「帰ってきました」。彼女は私に言った。「誰がですか?」私は立ち上がり、スコセッシ監督に近づいた。彼はいつものように黒っぽい服を着て、眼鏡はかけずに手に持っていた。彼の握手は彼の笑顔のように温かかった。我々が腰掛けると、パンやグリッシーニ、オイル、塩、おつまみや彼のミルク入りアメリカンコーヒーが運ばれてきた。皆それぞれ何かをつまんだ。そうして、私たちのために準備されたエレガントだがシンプルな部屋の隅のテーブルで、会話を再開した。我々の会話はいつも家族や娘のことから始まった。『沈黙』は以前感じたように、彼にとって本当に家族的な作品なのだ。我々は恩恵のことを再び話した。私は彼に、もしまだ読んでいないのであれば、フラナリー・オコナーの短編を読むよう勧めた。そして私は、彼女の話の中に入るために3度もミレッジヴィルの農場を訪れたことを話した。彼女はいつも恩恵を「悪魔の領域」で見たのであり、私もそれを学んだ。彼は微笑むと、彼がニューヨークタイムズの記事でポール・エリーにインタビューされた時に、彼からもオコナーを読むよう勧められたことを話した。私はエリーをよく知っているので、彼が同じ印象を持っていたことに驚きはしなかった。スコセッシ監督は、実は『烈しく攻むる者はこれを奪う』は読んだことがあり、動揺したことを語った。彼は物語の中に入り込んだのだ。「そしてあの言葉遣い!」そう叫んだ。アメリカ南部訛りの言葉が、まるで鞘を求めて急所を探しているナイフのように切り込む。私は彼に続けるよう、そうすれば何かが生まれるかもしれないと言った。そして書簡集を読むように勧めた。『存在することの習慣』、それが書簡集のタイトルだ。
そして彼はまた、最近インディアナポリスで目の手術を受け、長い間文字を読むことができなかったことを話した。そこで、オーディオブックを手に入れ、ドストエフスキーを全力で聴いたという。彼は私にカラマーゾフについて話した。そして聴きながら、空想でいかにそれを楽しみ、また苦悩したかを語った。私は教皇フランシスコもまたドストエフスキーが好きだと告げた。「面白い」彼はそう言った。「特に彼が好きなものは何ですか?」と尋ねた。私は教皇にとって最も好きな小説が『地下室の手記』であることを聞いた時に驚いたことを話した。彼は飛び上がった。「僕もです。『タクシードライバー』は僕の『地下室の手記』なんだ」。
私たちは、劇的なストーリーや観念ではなく、人生を反映した小説の重要性について語った。観念では、良識は身につかない。私は2013年のインタビューで教皇フランシスコも私に同じことを言っていたとは彼に言わなかったが、しかし私にとっては印象的だった。映画監督の人生と教皇の人生を形作る文学的知性が存在するのだろう。しかしこれは、驚くべきことではない。我々は記憶の話題に戻った。彼は私に路上で見ることを学んだと言った。映画を撮りながら、彼は見ることを学び続けた。「これもまた恩恵ですね」彼は言った。「そうですね。実際、恩恵に触れることは、物事を異なる方法で見ることを意味します」私は答えた。「奇跡は起きますが、時に奇跡は人生におけるひとつの出来事なのであって、奇跡を受ける者とはそれを認識できる者であり、それを正しい目で見ることができる者なのです」。つまり何年も、場合によっては何十年もかけて、目を訓練する必要があるのだ。
『沈黙』の計画はどのようにして浮かんだのですか?これは何年も、ひょっとすると20年、30年もの間あなたの中にあった情熱だったと思いますが......。
遠藤周作の小説は1988年にプレゼントされました。私は1989年の8月、黒澤明の『夢』でゴッホを演じた後、東京から京都に向かう電車の中で読み終えました。その段階でこれを映画にしたいと思っていたかどうかはわかりません。物語は私の心をかき乱し、あまりに深く突き刺さったので、それと向き合うことができるかどうかさえわかりませんでした。しかし時がたつにつれ、私の中で何かがこう言い始めたのです。「試してみなければいけない」と。私たちは、1990年から91年にかけて権利を獲得しました。1年ほどたって、私の友であり同僚の脚本家ジェイ・コックスとともに、草案に取り掛かりましたが、実際、私はまだ挑戦する準備ができていなかったのです。いずれにせよ、それは長いプロセスの始まりに過ぎず、最終的に最初の具体的な草案は2006年12月にできました。その時に私たちは具体的な映画の構成を考えだしたのです。それまで、私はずっとこの映画の実現を想像することすらできませんでした。私にとって、おこがましいことのように感じていたのです。どのようにテーマと向き合ったらいいのかがわかりませんでした。そのうえ、草案を具体的な計画にするのはとても難しいことでした。あまりに多くの法的、経済的問題が生じたので、問題全体が徐々にゴルディアスの結び目のような難問の様相を呈し、それをほどくために、多くの人と時間を必要としました。さらに、俳優の問題もありました。私のお気に入りの、「当たる」俳優がいて、彼らはすでに映画を撮ることを承諾していたのですが、時間がたつにつれて、「当たる」俳優ではなくなってしまったり、年をとりすぎてしまったり、もしくはその両方によってふさわしくなくなってしまったのです。映画を撮るために必要な興行収入を保証でき、かつ役を演じられる俳優はなかなか見つかりませんでした。それは非常に長いプロセスであり、正確には、19年もの間、立ち止まっては再スタートを繰り返しながらのものでした。
今振り返ってみると、この長いプロセスは、私の人生の一部、人生を生きる方法となっていたように思います。本の中に書かれている考えとともに生きる。その考えが、信仰の問題についてさらに深く考えるきっかけとなりました。振り返れば、私の記憶の中にあるすべてが、ある種の巡礼のように一体となっていたように思います。まさにそうして進んでいったのです。人生のまさにこの段階で、この映画をつくることができるという恩恵を受けたことに、私は驚いていますよ。
この映画をつくりたいという思いはあなたの中でどのように作用したのですか? いつか実現したいというものだったのですか? それともこの映画をつくりたいという欲求は何らかの形であなたがその間に作成した作品にもインスピレーションを与えたのですか?
先ほども話したように、この気持ちは私とともにあったのであり、私はそれとともに生きてきました。ですから、私がしたことすべてに含まれていると思いますよ。私がした選択や、その間に私がつくった他の映画のシーンを構成する方法においても。言い換えれば、一方ではこの映画を撮りたいという思いがあり、一方では遠藤の小説が、信仰や人生、つまり、どのように生きるべきか、恩恵とは何であり、どのように受けるものなのか、また最終的にそれらはみな同じことであるのか、といったことを考察する一種の刺激として存在していたのです。私が思うに......これが映画に取り組むための具体的な力を与えてくれたのです。
私の理解が正しければ、あなたにとって神を信じることとカトリック教徒であることは別とのことですが、これはどういうことでしょうか?
私は人がどのように神を感じるのかという点に興味があります。つまり、触れられない世界をどのように認識するのかということです。さまざまな道があります。そしてどの道を選ぶのかは、その人が属している文化によるのだと思います。私の道は、カトリックという道でした。私は長年さまざまなことを考え、いろいろ試した結果、カトリック教徒であることがしっくりきました(居心地がよいと感じました)。私はカトリックの原則を信じています。私は三位一体について論じられるような教父でも神学者でもありません。もちろん組織の政治にも興味はありません。しかし、復活や受肉の考え、愛や憐れみの強いメッセージ......これがカギです。秘跡は、それらに接近することができれば、つまりそれを経験できれば、神に近づくための助けとなります。
今ここで、ある疑問を生じさせることに気が付きました。私は実践的で敬虔なカトリック教徒なのかということですね。もし、「習慣的に教会に行くのか?」という質問であるならば、答えはノーです。しかしながら、子供の時から私は常に、宗教の実践とは、聖別された建物(教会)の中で、ある儀式のある時間にだけ起こるものではないことを確信してきました。実践とは、常に起こりえるものです。実践とは、よいことであろうと悪いことであろうと、あなたが行うことに対して考察することです。これは挑戦です。いずれにせよ、私が若かった時はカトリック教会による慰めや深い感動を感じていましたし......それは常に、基準点でした。
このあなたの映画、『沈黙』のような小説を選ぶことは、キリスト教の精神世界に入ることのように思われます。ある意味、「ベルナノス風」の映画のようにも思われますが、それに対してどう考えますか?
確かにキリスト教の精神世界に入るということには同意しますが、ベルナノスとの比較に関してはわかりませんね。私にとっては、すべてが恩恵の質問に行きつくのです。恩恵は、人生の中に起こるものです。それは予期していない時に訪れます。もちろん、私は戦争や拷問、占領を体験したことのない者として言っています。このような経験をしたことはありません。ジャック・リュセランのように試練を与えられた人たちもいます。彼は、フランスのレジスタンス運動の盲目のリーダーであり、ブーヘンヴァルトの強制収容所に送られた後も、捕らえられた仲間の中でレジスタンスの精神を保ち続けました。実は私たちは長年彼の日記をもとにした映画をつくろうとしていました。またディートリヒ・ボンヘッファーや、エリ・ヴィーゼルやプリーモ・レーヴィのように他者を助ける方法を見つけられた人たちもいました。とはいえ、何百万もの人々が大量に虐殺されてしまった中のどこに神がいたのか、という問題に対して、確固たる答えを彼らの例から提示しようとしているわけではありません。しかし、実際にたぐいまれなる勇気と憐れみを示した人がいたのであり、彼らのことを闇を照らす光として私たちは思い出すのです。
私たちは他の人の経験を通して物事を見ることはできません。自身の経験を通してのみ物事を見ることができるのです。そのため、矛盾しているように思われるでしょうが、私は日本人である遠藤の小説に何か通じるものを感じたのです。それはベルナノスには感じないものでした。ベルナノスは強靭で非常に過酷な人です。それに対して、遠藤には慈しみや憐れみが常に存在しています。いつも。それは、遠藤の小説の中の人々が慈しみや憐れみがあると気づいていない時にさえもです。むろん私たちにはそこに慈しみや憐れみがあることをわかっているのですが。
あなたにとって神とはどのような存在ですか?罰や恐怖の源ですか?それとも喜びや調和の源ですか?教皇フランシスコは神を憐れみの存在と語っています。彼は罰を与える存在としてのイメージを取り去ることを望んでいます......神は罰を与える存在であることは決してないのでしょうか?
ロベール・ブレッソンによる『田舎司祭の日記』のベルナノスを思い起こします。私がこの映画を初めて観たのは60年代の中ごろでした。当時私は20歳になったばかりで、子供のころに養われたカトリックの教えを乗り越えようとしているところでした。多くの子供たちと同じく、私は教えられてきた神の厳しい側面に衝撃を受けていました。神は何か悪いことをした時に罰する存在であり、雷鳴の神。まさにこれはその当時、同じく私に強い衝撃を与えたもう一つの作品である『若い芸術家の肖像』でジョイスが描いたものです。
もちろん、国は当時非常に劇的な状況でした。ヴェトナム戦争が始まり、「聖戦」と言われ始めていたころでした。つまり私の中には、当時の他の人と同様に、日常生活の一部として混乱や疑い、悲しみがあったのです。まさにそのころにブレッソンの『田舎司祭の日記』を観ました。それは私に希望を与えました。この映画のすべての人物は、おそらく老司祭を除いて、皆苦しみを感じています。すべての人が罰せられていると感じ、彼らの多くが何らかの罰を互いに課していました。ある時、司祭は教区の女性の一人と会話し、彼女に次のように言っています。「神は死刑執行人ではありません。彼は我々が私たち自身に憐れみを感じることを望んでいるのです」。これが私にとってある種の啓示でした。それがカギだったのです。なぜなら神が我々を罰していると感じている時、そのことについて考える時間を持つことさえできれば、死刑執行人なのは私たち自身なのであって、私たちが慈悲深くなければいけないのは自分たちに対してであるということに気が付くのですから。私は一度パリでブレッソンに会いました。そしてその時に私にとって彼の映画が何を意味していたのかを直接彼に伝えました。『レイジング・ブル』の後で、私はまさにこれが、私が心に描いていたことだったのだということを実感しました。これこそがまさに映画のテーマだったのです。私たちは明確な意図をもって映画をつくったわけではありませんでした。ただ、私たちが知っている世界で、私たちが知っている人生を歩んでいる誰かについての映画をつくっただけでした。主人公のジェイクは周りにいるすべての人を罰しますが、本当に罰しているのは彼自身なのです。つまり、最後に鏡を見る時に、彼は自分自身に憐れみを持たなければいけないことを知るのです。別の表現をするならば、自分自身を認め、自分自身と一緒に生きていかなければいけないのです。そうすれば、おそらく他の人とともに生きることができ、彼らのやさしさがより受け入れやすくなることでしょう。
若かったころの私は本当に幸運でした。なぜなら素晴らしい司祭、プリンチペ神父がいたからです。彼から多くのことを学びました。とりわけ自分自身に対して、そして他者に対しての憐れみを。もちろん時には彼は厳格な道徳的指導者となることもありましたが、彼の場合は他とは異なっていました。彼は真のガイドだったのです。厳しく話すこともありましたが、私に何かをするよう強いたことは一度もありませんでした。導き、注意し、納得させる。本当にたぐいまれな愛を持った人でした。
ある批評家が「スコセッシ監督の霊的なことに対する強い関心」について書いています。あなたは自身が精神的領域に固執しているという考えに同意しますか?
マリリン・ロビンソンの『心の不在』の中で、彼女は私にとってこの質問への核心に迫ることを書いていました。「たとえ私たちが、私たち自身を余すところなく描写するために『自然界の首位にある』という言葉を使ったとしても、私たちの本質は――例えば私たちは見事なまでに創造的であると同時に、破壊的でもあるというような――、残るのであり、そのことを考慮に入れなければいけないのです」。これは確かに正しいです。すべてのことに説明を見出せるという考えは、ばかげているというよりも、非常に無垢なものに思われます。私たちが我々の存在や生と死といった神秘的なものを考察しようとする時、科学によってすべてが解明されうるという考え自体、根拠がないように思われます。まさにこのことを、ロビンソンは彼女の論文の中で書いているのです。彼女が「精神や心」と呼ぶものは、私にとって、真のカトリック教会なのです。精神や心とはまさに我々がなすすべてです。私たちがなす善や、私たちがもたらす悪なのです。他者とともに、特に愛する人とともに、挑戦することなのです。私の挑戦とは、仕事や自分自身にとらわれすぎないよう、愛する者のために存在するよう心がけることです。実際、私はこのインタビューで私たちが話してきたことすべてを、映画の中に表現しています。有名人としての名声や、野心や競争の世界に生きることは、私にとってのもう一つの挑戦です。しかしながらもちろん、この世界の一部をなしている限り、──私はこの世界の一部であることをある程度は認めなければいけませんし、それに関する映画もいくつかつくってきましたが──人生の中の精神的領域と彼女が呼ぶものは、いつも存在しています。カール・ユングはスイスの自分の家の扉の上に、ラテン語の銘文を掲げていました。「Vocatus atque non vocatus deus aderit (呼ばれると呼ばれざるとにかかわらず神は存在する)」これがすべてを物語っています。
あなたは喘息を患っていましたが、教皇フランシスコも肺に問題を抱えています。私は呼吸器の弱い方は感受性がより豊かなように感じるのですが、あなたはこのことから何か学びましたか?
喘息に関しては、それがひどい時には、本当にもう二度と息ができないかのように感じます。まさに文字通り、今にも死んでしまうのではないかと、死に瀕しているように感じます。本当に息ができなかったことが何度かあります。呼吸困難の状態があまりにひどかったために、こう考えました。これがこの先も起きるのであれば、どうやって人生を続けていけばいいのだろうか。安らぎが欲しい、という考えが頭をよぎりました。
私が若かったころ、1950年代くらいには、医者との付き合い方というものがありました。少なくとも私の両親のような人たちにとっては。つまり医者の言うことすべてに耳を傾け、セカンドオピニオンを聞くなんてことは考えもしませんでした。別の考えを聞きたいと思っている時ですら、おそらくそれを口にすることはできなかったでしょう。医者たちは喘息に対する彼らの考えを持っていました。薬や治療法もありましたが、生活習慣を整えることに、より重きを置いていました。スポーツをしてはいけませんでした。体を動かすことは一切。笑う時ですら、節度を保つよう見張られていました。さらに私は、動物や木、草といった周りにあるものに対するアレルギーを持っていたので、田舎に行くこともできませんでした。
その結果、私は孤独な生活を送らなければいけなかったのです。私は他の人から孤立しているように感じていました。これは私が多くの時間を大人たちと過ごしていたことからも来ています。そしてこのことが私に大人の世界を意識させ、それをより理解させたように思います。私に人生のリズムや大人の悩み、正しいとか間違っているという議論や、他者に対する義務といったことを意識させたのです。人の感情や、しぐさ――言葉と行動の違い――など、大人たちの感受性をより意識することで、これが私の中で自分の感受性を磨いていきました。より敏感になったといえるでしょう。
私は窓から世界を見ながら......多くのことを見たことを覚えています。素敵なこと、恐ろしいこと、言葉では表せないもの、私にとってはすべてでした。
このことのもう一つの側面は、仕事をしている時、大切なことに集中力を保つことができるということです。孤立していたこと、孤独や私の自覚は、注意力をそぐいかなるものをも取り除く力を私に与えたように思います。これは映画をつくっている時にも起こります。ある意味、矛盾していますね。なぜなら感受性を守る集中力であり、それがある種の無関心をもたらすのですから。
あなたは死の淵を経験したとおっしゃいましたが、あなたにとって救いとは何ですか?
自己破壊の中には欺瞞が隠れています。破壊を知るためには、自身を破壊しなければいけないという。つまりこれはある種の傲慢さなのであり、最終的に自身を破壊するのです。私の場合、人生の自己破壊の瞬間から何らかの方法で脱しました。おそらく無意識のうちにその中に入ってしまい、そして同じく無意識のうちに出てきたのだと思います。
私は子供のころ、教会で侍者としてお葬式や死者のための土曜日のミサに奉仕してきました。私の友達は、墓掘り人の息子でした。私は今世紀の初めにシチリアからやってきた古い世代の人々が亡くなるのを見ました。私にとっては、深い経験でした。ですから私は死の運命についてたくさん考え、考えすぎてつらくなるほどでした。しかしその後、そこから抜け出し、最初に撮った作品が、『レイジング・ブル』です。
つまりこの質問のもう一つの側面は、この映画に関してすでに話した内容でもあります。自身を受け入れ、自身とともに生き、人々の人生にプラスの影響を与えるよう努力すること。それが「救い」の定義だと思っています。私たちが愛している人々、家族や友人、大切な人に与える。できるだけよくあるように、できるだけ良識的でまた憐れみ深くあるよう努める必要があります。
しかし道を歩みながら、人は別のことも学ぶでしょう。サム・ペキンパーの『昼下りの決斗』の中で、エドガー・ブキャナン演じる酔った判事がマリエット・ハートレイとある男性を結婚させるシーンで、次のように言うのです。「あなた方は結婚についてあることを学んだことでしょう。人は変わるということを」。これはすべての関係性において生じることです。仕事仲間との関係においても生じます。時間がたつと、よく知っていて、その人と長い間一緒に働いているような人でも、彼らにとって他に重要なことが生じた際には、そのことを認める必要があります。彼らをありのままに、彼らの変化も含めて受け入れ、そのよいところを引き出す必要があります。時には、彼らの道を歩むために彼らが離れていくことを認める必要もあります。昔はそれを裏切りだと思っていました。でも今はそうではなく、変化なのだと理解するようになりました。「救い」という言葉は興味深いものです。実際、誰一人知ることができないものです。死の瞬間、もし意識があるのであれば、救いに到達したのかを知るかもしれません。でもどのように知るのでしょう。確かなことは、生きている間に知ることはないということです。私たちができる唯一のこととは、できる限り気高く生きることだけです。もし倒れたら、再び起き上がり挑戦しなければいけません。陳腐な表現ですが、でも真実です。私にとって昼夜、浮き沈みはあります。興奮と闇が交互に訪れ、自己批判への疑念が生じます。しかしこの点に固執する必要はありません。ここでもやはり、我々は自分自身を認めなければいけないのです。つまりこれは常に続くプロセスだということですね。
『レイジング・ブル』の後、あなたはローマに行って、聖人たちの生涯のドキュメンタリーを撮影しようと考えたそうですね。この考えはどのようにして生まれたのですか?
1980年か81年、『レイジング・ブル』を撮り終えた直後は、私はこれが私の最後の劇場版映画だと真剣に思っていました。その当時、ベルトルッチやタヴィアーニ兄弟などの監督がライ(イタリア放送協会)のために制作した映画や、特にロベルト・ロッセリーニの映画の影響で、私はテレビが映画の未来だと思っていました。より正確に言うと、映画とテレビの混合が。それはエンターテインメントですが、より深いエンターテインメントの要素を持ったものです。それに映画も、何かを人に教えられるものです。この考えも、ロッセリーニが私にもたらしたものです。彼の映画は「教育的映画」と言及されることがありました。私はライこそが私を常に悩ませているこのテーマに本腰を入れて取り組むべき場所になるだろうと思っていました。それは聖人とは何なのかということでした。私の構想は、聖人たち、中には民間伝承にだけ伝わる存在しない聖人をも含めた、さまざまな聖人に対する映画のシリーズをつくることでした。この人物たちはどこから来るのでしょうか。これはユダヤ・キリスト教時代に先立つ時代まで私たちをいざないました。なぜ聖人というとりなしが必要なのでしょうか。どうして、旅人の守護聖人、聖クリストフォロスは実際には存在しなかったことに行きつくのでしょうか。私たちは旅をする時、危険にさらされています。そのため、守ってくれる存在を必要とします。それならば真の聖人とはいったい何なのでしょうか。聖人たちは人々と、精神的観点においてどのような関係を有しているのでしょうか。彼らの日常生活とはどのようなものであり、何に根拠があるのでしょうか。このことが、プリンチペ神父が私にくれた本を読むきっかけとなりました。この本は、マイルズ・コノリーの『ミスターブルー』という題で、近代の聖フランチェスコについて書かれており、映画とテレビのためにつくられたものでした。現代世界において、物質的意味ではなく、尊厳の意味においてもよき人生を送れることを示そうとしたものです。それはドロシー・デイがカトリックの労働者たちと一緒にしたことと同じでした。プリンチペ神父は、朝の集まりに来て老人たちと話すよう、彼女を招待したことがあり、私は帰りがけの彼女を見かけたことがありました。
つまりこれらのことが、私の中でちょうど『レイジング・ブル』を撮り終えた時に膨らんでいき、先ほども言ったように、私は『レイジング・ブル』が高額の製作費を費やした私の劇場版映画の最後だと思っていました。そのころ、私はロッセリーニのもう一つの映画からも強い影響を受けました。それは『ヨーロッパ一九五一年』です。私はこの映画のショートヴァージョンを観ました。ロッセリーニは現代世界において聖人であるという問題に対峙しました。フランチェスコやカテリーナ、テレーズ(テレーズに関しては、アラン・カヴァリエが映画を作成している)といった人々がいますが、彼らは「行動主義的聖人」と呼べるような人ではなく、聖ピオ神父のような人とは大きく異なっていました。彼らの本質――愛、憐れみ、キリストの行いをまねた人生――、そして現代の世界で似たような人生をどのように生きるのかという問いこそが、ロッセリーニがこの映画で取り組んだことなのです。当時私は、彼がシモーヌ・ヴェイユからインスピレーションを得ていたことを知りませんでした。彼女は何よりも、自分自身に対して情け深い人ではありませんでした。『ヨーロッパ一九五一年』の最後で、主人公アイリ-ンは自身に対する安らぎを見出し、自分が役に立っていると感じます。つまり、あの映画は私にとってとても大切でした。また彼の『神の道化師、フランチェスコ』もそうです。これは、私が観た聖人に関する映画で最も素晴らしいものです。
実際にはその後、事態は別の形で進みます。私はニューヨークに戻り、ロバート・デ・ニーロと『キング・オブ・コメディ』を制作しました。その後私は『最後の誘惑』の制作を試み、もともとの計画は保留となりました。制作会社も変わり、もはやあの映画、聖人たちの生涯に関する映画をつくることは不可能なように思われました。しかし、キリストをまねた生涯を生きようとした人々に対する私の関心は決して衰えることなく、いつの日か再びそこに戻ることを確信していました。最終的にその2年後に『最後の誘惑』を完成させた時、それまでのエネルギーや議論の多くが、この作品に注ぎ込まれました。当然、先ほど言ったように、私が『沈黙』とともに生きた年月の中ですべては起こり、進んでいったのです。
遠藤の小説とあなたの映画の中で最も心を打つ人物とは誰ですか? そしてそれはなぜですか?
若かったころ、司祭であることに関する映画をつくることを考えました。私自身プリンチペ神父の道に続きたい、つまり神父になりたいと思っていました。私は神学校に通いましたが、最初の年だけでやめてしまいました。15歳の時に、修道生活への召命は特別なことであり、獲得するようなものでも、誰か他の人のようになりたいという理由だけで得るものでもないということを自覚したからです。それは本当に呼ばれなければいけないのです。
しかしもし本当に召命を受けた場合、自身のプライドに立ち向かうにはどうしたらいいのでしょうか。もし本質的変化をもたらすような儀式を実行することができるのならば問題ないとはいえ、それはかなり稀なことです。何か別のものも必要でしょう。私が見て、経験してきたことから考えるに、よき司祭は、才能や能力を持っていることに加えて、まず第一に自身の教区民たちのことを考えなければいけません。つまり、神父はいったいどのようにして自身のエゴ、プライドを乗り越えられるのか、ということです。私はそういった映画をつくりたいと思っていました。そして『沈黙』によって、ほぼ60年たった今、その映画をつくっていたのだということに気が付きました。ロドリゴはまさにこの質問に直接対峙するのです。
しかし一番魅力的でドキドキさせるのは、キチジローでしょう。撮影している時に、時々私は彼が「『少し』イエスのようだ」と感じました。マタイによる福音書の中で、イエスは次のように言っています。「私の兄弟であるこの最も小さい者の一人にしたのは、私にしてくれたことなのである」。歩みの中で我々をうんざりさせる人に出会うことがあります。それがイエスです。もちろんキチジローは常に弱く、自身や家族といった他の多くの人に損害をもたらします。しかしながら、最後にロドリゴのそばにいたのは誰でしょうか。キチジローです。彼がロドリゴの偉大な先生であったことに気が付くのです。彼の助言者、いわゆる指導者であったということに。だからこそロドリゴは最後に彼に感謝するのです。
私が作成した映画を改めて観て、キチジローが『ミーン・ストリート』のジョニー・ボーイだと気付かせてくれた人がいました。ハーヴェイ・カイテル演じたチャーリーは自身のプライドに打ち勝たなければなりません。精神性や宗教実践は教会の建物の中に文字通り限定されたものではなく、外の世界に出てこなければいけないことがわかります。しかし当然、自身の悔悛の時を選ぶことはできません。彼はそれをできると考えるのですが、悔悛は思いがけない時に、予期せぬ方向からやってくるのです。これが、ジョニー・ボーイとキチジローが私にとって魅力的な理由です。彼らは破壊と救済のもととなるのです。これらのことの多くが、私が子供のころに実際に見たことからきています。特に私の父チャーリーとその弟ジョーの間で起こったことから。
ロドリゴ神父とフェレイラ神父は同じコインの二つの側面を表しているのでしょうか? それとも全く違う、比較できないものなのでしょうか。
私たちは歴史上のフェレイラ神父が実際に何を信じ、何を信じなかったのかを知ることはできません。でも遠藤の小説の中では、信仰を失ってしまったかのように思われます。おそらくもう一つの見方は、たとえ人の命を救うためにしたこととはいえ、彼は自身の信仰を放棄したという恥を克服することができなかったということです。
ロドリゴは一方で、信仰を放棄しますが、のちにそれを再び取り戻します。これはパラドックスです。簡単に言うならば、ロドリゴは彼に語るイエスの声を聞いたのであり、フェレイラにはそれがなかった、これが違いなのです。
前にあなたはあなたのお父さんを思い出しながら、彼が言うことには常に道徳的な判断が込められていたと言っていましたね。例えば、誰が間違えた? 誰が正しい? 誰が善人で誰が悪人? 世界には善人と悪人がいるの? といったように。
私の両親はともに、大家族出身でした。私の父は4人兄弟でジョーは末っ子でした。彼はエリザベス通りの私たちの家の下の階に、妻と子供たちと一緒に住んでいました。私の父方の祖父母は私たちの2階下に住んでいて、私の父は毎晩彼らに会いに行っていました。彼らは家族の問題や、スコセッシ家の名誉といった、私にはまったく理解できないようなタイプのことを話し合っていたのでしょう。それはまさに昔の世界のことであり、私は新しい世界に生まれたのです。彼らは正直な人たちで、正直な生き方を求めていました。しかしながらあの世界には組織犯罪というものが存在し、人々は危ない橋を渡る必要があったのです。彼らに与することはできなかったのですが、しかし抵抗することもできませんでした。私の叔父は、彼らとともにいようとしました。彼は無鉄砲で、まさにジョニー・ボーイのような人でした。いつも問題を起こしては、何度もつかまって、いつも高利貸しにお金を借りては、暴力的な雰囲気を醸し出していました。私の父は、彼の面倒をみていました。毎日、アパートで私は父がこれらの問題に取り組んでいるのを目にしました。どのように正しい方法で彼に対処するか、すべてが父にかかっていました。私の母は時に腹を立てて、次のように言っていました。「あなたの他の兄弟たちは助けてくれないの?」と。彼らはある程度は手を貸してくれていたものの、ある時点でみな地区の外に出て行ってしまいました。私の父とジョーが唯一残った人たちでした。だから私の父は一人ですべてに対処しなければいけなかったのです。そしてこのことは、すべてに関わるということを意味しました。つまり議論や交渉、仲介、叔父の保証をしたり、時にはお金を与えたりといったこともしていました。まさに叔父のために何でもしました。彼は自分の弟の面倒を見ることを義務だと感じていました。他の家族のメンバーは、手を引いたり、別のところに行ってしまったので、すべてが私たち家族にかかっていたのです。それは本当に難しいことでした。私はジョーが好きでした。しかし彼の近くにいることは本当に大変でした。すべてが一つの疑問を生じさせるのです。「私は弟の守護天使なのだろうか?」まさにこれが『ミーンストリート』で私が扱ったテーマでした。
『沈黙』はキリストの顔を内面で発見する話だと思われます。他の人を助けるために、そしてそれこそまさにキリストがこの世にやってきた理由ですが、自身を踏むようにロドリゴに言っているかのようなキリストの顔を。あなたにとってキリストの顔とはどのようなものですか? 遠藤が書いているような踏絵のイメージですか? それとも、栄光ある荘厳なイメージですか?
私はキリストの顔として、エル・グレコの描いたものを選びました。なぜなら私はピエロ・デッラ・フランチェスカのキリストのイメージよりもより憐れみ深いと思ったからです。若いころの私にとって、キリストの顔は常に慰めや喜びでした。
『キリストの最後の誘惑』は別にして、あなたにとって映画史の中で最もキリストの真の顔を表している映画とはどれです か?
私にとってキリストに関する最も素晴らしい映画は、パゾリーニの『奇跡の丘』です。若いころ、私は現代版のキリストの生涯を、ニューヨークの中心の庶民の家を舞台に撮りたいと思っていました。でもパゾリーニの映画を観た時、そういった映画はすでに存在することを知ったのです。
あなたは神の存在を、たとえ沈黙のままだったとしても、近くに感じた経験がありますか?
私が若いころ、ミサで奉仕していたころは、聖なる感覚を感じることに疑いはありませんでした。私はそれを『沈黙』の中の、五島の農民の家でのミサのシーンで伝えようとしました。いずれにせよ、私はミサが終わったあと、外に出て、こう自問したことを覚えています。「一体どうして人生はまるで何も起こっていないかのように進んでいけるのだろうか?どうして何も変わらないのだろうか?なぜこの世界はキリストの体と血によって揺り動かされないのだろうか?」これが私が若かったころの神の存在の経験です。
1983年に私は『最後の誘惑』を撮影する舞台を探すためにイスラエルにいました。小さな飛行機に乗っていったのですが、私は元来空の旅は好きではなく、特に小さな飛行機は嫌いでした。ですから機中では、私の母が数年前にくれたお守りを手にしながら、とても緊張していました。テルアビブからガリラヤ、ベツサイダからエイラートを行き来しているうちに、聖墳墓教会に行きました。私は、製作のロバート・チャートフと一緒でした。彼は最近亡くなったのですが。キリストの墓で私はひざまずき、祈りました。私がそこから出た時、ボブ(ロバートの愛称)は「何か少し違うような感じがするか」と尋ねました。私は「いいや」と答えました。私にとってはその場所の地理と、その場所に対してさまざまな修道会が権利を主張してきたということだけが印象的でした。そこから私たちは再びテルアビブまで飛ばなければいけなくなり、また飛行機に乗りました。私は落ち着きなく、母からもらったすべてのお守りを強く握りしめていたのですが、飛んでいる時に突然、もうそれらは必要ないと感じたのです。私は全面的な愛を感じ、もし何かが起こるはずだったとしても、もう起きないだろうという感覚を感じました。それは何か特別なものでした。私は人生でこのような経験ができたことを幸運だと思っています。
娘のフランチェスカが生まれた時のことも話したいと思います。彼女は帝王切開で生まれました。私はそこに立ち合い、起きたことすべてを見ていたのですが、突然退室するように言われました。私は別の部屋に連れていかれ、長方形の窓越しに見ていました。私は事態が非常に切迫していることを感じ、生気がまったく感じられない体が出てくるまで、すべてを見ていました。その後、看護師が出てきて、泣きながら私に言いました。
「きっと彼女は乗り越えるでしょう」と。そして私を抱きしめました。私はそれが妻のことなのか、子供のことなのかわかりませんでした。その後、医師がきました。壁によりかかると、そのまま下にしゃがみ込み、言いました。「すべて計画通りでしたが、20秒の恐怖の瞬間がありました。しかし乗り切りました」。あと少しで2人とも失うところだったのです。次に私が覚えているのは、私の腕の中に小さな包みが置かれた時でした。私が彼女の顔を見ると、彼女は眼を開けました。その瞬間にすべてが変わったのです。
私が『沈黙』を撮影していた間に読んだマリリン・ロビンソンの『ギレアド』という小説に次のような一節があります。死にゆく老牧師が初めて自分の娘の顔を見た時に感じた驚きを描写しているところです。「この世を去ろうとしている今、私は人間の顔以上に特別なものなどないということがわかりました。[...中略...]これはキリストの受肉に関わります。あなたが子供を見た時、そしてその子を抱いた時、その子に対する義務を感じます。どんな顔もあなたに何かを感じさせます。なぜならその人の唯一性、勇気、孤独を理解しないことなどないからです。そしてこれは特に生まれたばかりの新生児の顔を見た場合に言えることです。この経験はある種のヴィジョン、神秘的なことだと思います」と。私は個人的経験から、まさにこれが事実だと言えます。
憐れみとは、本能でしょうか。それとも愛でしょうか?
カギは、自我を否定することだと思います。『ミーンストリート』でチャーリーはジョニー・ボーイの面倒をみることは彼の贖罪であり、彼の個人的な救済に役立つと考える罠に陥っています。このことは、私が知っているよき聖職者は完全に自我をわきに置いていたことを思い起こさせます。その場合、必要──他者の必要――のみが残り、選ぶべき贖罪に対する質問や、それが憐れみであるかどうかといった質問は出てきません。そのような質問は意味のないものになるのです。
『沈黙』の話には、たくさんの肉体的、精神的暴力が見られます。暴力表現の中にあるのは何でしょうか。あなたの映画において、暴力がたくさん見られます。この映画の中の暴力は何を表しているのでしょうか?
あなたが前にした、私がまさに精神的なものに固執しているという質問に合わせて、まさに私は、私たちとは一体何であるのかという問いに固執しているのです。これは我々自身を近くから見ることを意味します。私たちのよい点、悪い点を見ることです。我々は人類の発展において、将来的にはよい面を育てあげ、暴力が存在しなくなることも可能になるのかもしれません。しかしいずれにせよ、さしあたりこの世界には暴力が存在します。暴力とは私たちがすることです。それを見せることは重要です。まさに暴力は他の人がする何かだと考える、つまり「暴力的な人」がすることであり、「当然私は決してそれをやらないだろう」と考える過ちを犯さなくなります。実際には、あなたもそれをなしうるのです。我々はそのことを否定することはできません。時に自身の暴力に動揺し、興奮する人もいます。それはまさに絶望的状況での一つの表現方法であり、面白いものではありません。ある人は『グッドフェローズ』は面白いと言います。たしかに登場人物は面白いですが、暴力は決して面白いものではありません。多くの人が、暴力からあまりにかけ離れた文化のもとにいるために、暴力を理解していないだけなのです。しかし私は暴力が生活の一部であり、非常に近いところにあった世界で育ちました。
70年代初頭とは、私たちがヴェトナム戦争時代から抜け出した時であり、古きハリウッドの豪華な世界が終わろうとする時代でした。『ボニーとクライド』、そして『ワイルドバンチ』はまさに新星でした。これらの映画は私たちに常に好ましい方法で語りかけるわけではありません。暴力は私が思うに、人間の一部です。私の映画では、ユーモアは人々や人間の思考からくるものです。暴力と卑俗。卑俗とわいせつは存在し、それもまた私たち人間の一部をなしています。しかしこれは、その結果として私たちが本質的にみだらで暴力的であることを意味するわけではありません。これが人間のふるまい方の一つの可能性であるということを意味しているのです。決してよい可能性ではありませんが、一つの可能性として存在しているのです。
あなたにとって、映画をつくることは絵を描くようなことです ね。映像はこの映画にとって重要な役割を担っています。どの ようにして映像によって我々に精神性を見せるのでしょうか?
イメージによって雰囲気をつくるのです。映画とは、別世界を感じられる雰囲気に身を置くことであり、映画から引き出されるのはまさにこれらの映像や考え、感情なのです。言葉では表すことのできない、触れることができないものも存在します。つまり、映画の中で映像を別のものと一緒にして組み立てる時、心の中に完全に異なる第三のイメージ、感情や印象が生まれるのです。私は雰囲気が重要であり、これは映像によるものと考えます。そしてそのイメージをつなげることで、映画が我々を魅了し、我々に話しかけるのです。それが編集作業であり、映画をつくるということです。
『沈黙』はどこで撮影しましたか? 私が聞いた限りでは台湾ということでしたが。その場所を選んだきっかけは何だったのですか?
『沈黙』を実現させるまでに多くの年月がかかりましたが、それは多くの理由によります。台湾を選ぶ前に、世界中のさまざまな場所を検討しました。遠藤周作の小説の舞台となった日本の実際の場所、長崎、外海、雲仙から出発しましたが、最終的にそこでの撮影は費用の面から断念しました。日本以外で、私の舞台美術家のダンテ・フェレッティはニュージーランドやバンクーバー、北カリフォルニアを探し、最終的に台湾を割り出しました。そこには素晴らしい景色や、人の手の入っていない海岸があり、まさに小説の舞台に似た光景が広がっていました。私たちはすぐにこここそ、この映画を撮影するにふさわしい場所だと決断しました。
この映画は他の映画から少なくとも部分的にでもインスピレーションを受けていたりしますか? もしそうなら、どの部分ですか?
本質的にはこの映画は私一人でつくったものです。私は自分の道を見つけなければなりませんでした。しかし概して私は多くの映画からインスピレーションを受けています。多くのアジア映画、ヨーロッパ映画、アメリカ映画、それらが私の中に混在しています。最終的にこの映画、あの映画ということではありません。中には何度も観たものもあります。例えば『捜索者』もしくは『めまい』、『82/1』などの映画です。それにロッセリーニの映画、『無防備都市』『戦火のかなた』『イタリア旅行』も。それに対して『奇跡』は一度しか観ていません。あれは二度観ることなどできませんでした。あまりに純粋で美しく、衝撃的だったので。これらの映画それぞれにおいて、心の中が揺り動かされ、変化を感じるでしょう。どれ一つとして、単なるエンターテインメントにとどまるものではなかったのです。
あなたにとって『沈黙』に並べられる、比較できるような自身の作品はありますか?それは似た意味の映画だからでしょうか。それとも逆の意味においてでしょうか。
『レイジング・ブル』は似ているといえるでしょう。また『ミーンストリート』も。おそらく『ディパーテッド』は『沈黙』の逆の映画です。ウィリアム・モナハンの台本は非常に印象的でした。なぜならボストンのアイルランド系カトリック教徒の視点から書かれたものであり、それは私が育った環境とはまったく異なっていたからです。『ディパーテッド』の最後で、人は上以外のどこにも行く場所がないような、内面のグラウンド・ゼロのような場所に自分自身を見出すでしょう。そして人々の犠牲に対して、特にレオナルド・ディカプリオ演じるビリーの犠牲に対して、ロジャー・エバートはまるでビリーが告解室で次のように告白しているのが聞こえるようだと言っていました。
「神父様、悪いとはわかっていた。でもそれしかできなかったんだ。間違っているとはわかっていたとしても、だからと言って何ができたって言うんだ」と。私にとって、これらすべてが9.11に関わるものでした。つまり新しい光の下で私たちの文化や人生を再検討することが必要だったんです。おそらくあの時点で我々は道徳的に最初から再出発する必要があったように思います。でもそうはしませんでした。『レイジング・ブル』でジェイクはすべてと戦います。場所など関係ありません。リング、ジム、道、寝室、リビング......どこであろうと、自身を罰し、すべての人に対して怒りを感じています。どこでも何度でも。それはキチジローのようです。キチジローとの違いは、キチジローがすることは強いられているのに対して、ジェイクはそうではないというところです。
この映画の準備中に、特に考えさせるような状況や出来事はありましたか?
先ほどもお話ししたように、私は長い間この映画とともに生きてきました。何度も出てきては延期するという状況。ですから、考えをうながしたのは、まさにこのことでしょうね。
あなたの近くにこの映画を実現するうえで支えとなった人はいますか?
すべてがニューヨークのポール・ムーア大司教と、セント・ジョン・ザ・ディヴァイン大聖堂にて始まりました。彼が80年代に、この小説を読むことを勧めてくれたのです。我々は彼のために『最後の誘惑』の上映を企画しました。彼がどのように反応するかはまったくわかりませんでしたが、私たちは映画に関して素晴らしい会話を交わしました。別れ際に、彼は私に一冊の本をプレゼントしたいと言いました。それがまさに『沈黙』だったのです。
アンドリュー・ガーフィールドと一緒に働き、彼に霊操を紹介したイエズス会士ジェイムズ・マーティン神父も私たちにとって非常に重要な人です。
制作中、私たちは台北のたくさんの聖職者たちに励まされました。それは映画の制作技術の顧問たちとは違う形であり、彼らのおかげでアンドリューとアダムが行う秘跡が本物となりました。中でも、イエズス会士のジェリー・マーティンソン神父とアルベルト・ヌニェス・オルティス神父(輔仁大学からの紹介)、大司教ポール・ラッセル神父、そして台北の教皇大使イヴァン・サントス神父の名前を挙げたいと思います。
私たちのもとには歴史考証の顧問もたくさんいました。中でも2人のイエズス会士、ジョージタウン大学の歴史家デイヴィッド・コリンズ神父と上智大学の川村信三神父は、映画のための研究をする上で貴重な助けとなりました。
ブリガム・ヤング大学の日本語教師ヴァン・C・ゲッセル氏は、遠藤周作の作品の多くを英語に翻訳し、我々を遠藤と直接結びつけたことで映画にとって大きな助けとなりました。我々は2011年から彼に頼ってきました。
2009年に私が長崎の日本二十六聖人記念館を訪れた時、私はアルゼンチンのイエズス会士、レンゾ・デ・ルーカ神父に会いました。彼は映画に出てくる「雪の聖母」の写本を快く提供してくれました。最初の段階で、私たちはイエズス会士アントニ・ウセレル神父とも会いました。
我々の歴史考証の重要な顧問2人は、ともにカトリックの世界で育ち、2011年から映画に参加しています。ユルギス・エリソナスは近世の日本の権威であり、フェレイラの歴史的人物像に関して多くを書いた人物であり、リアム・ブロッキーは17世紀の宣教師の変遷とアジアにおける彼らの存在について研究し、現在はアメリカ・カトリック歴史学会の会長を務めています。
これらの人々の名前を最後に、私のインタビューは終了した。私はマーティン・スコセッシ監督と彼の妻ヘレンに11月28日、私がソウル行きの飛行機に乗る前に再び会った。彼は私に「明日映画の上映のためにイエズス会士たちに会うのですが、何を言ったらいいだろうか」と尋ねた。私は彼にこの映画の経験や、この映画とどのように生きてきたのかを話すよう勧めた。この映画をつくることを選んだ理由だけでなく、それに伴う感情、それらが湧き起こってくる深い「穴」に関して。この穴こそ、まさに彼の声を聴くこの会話のために私自身が降りていったところなのである。