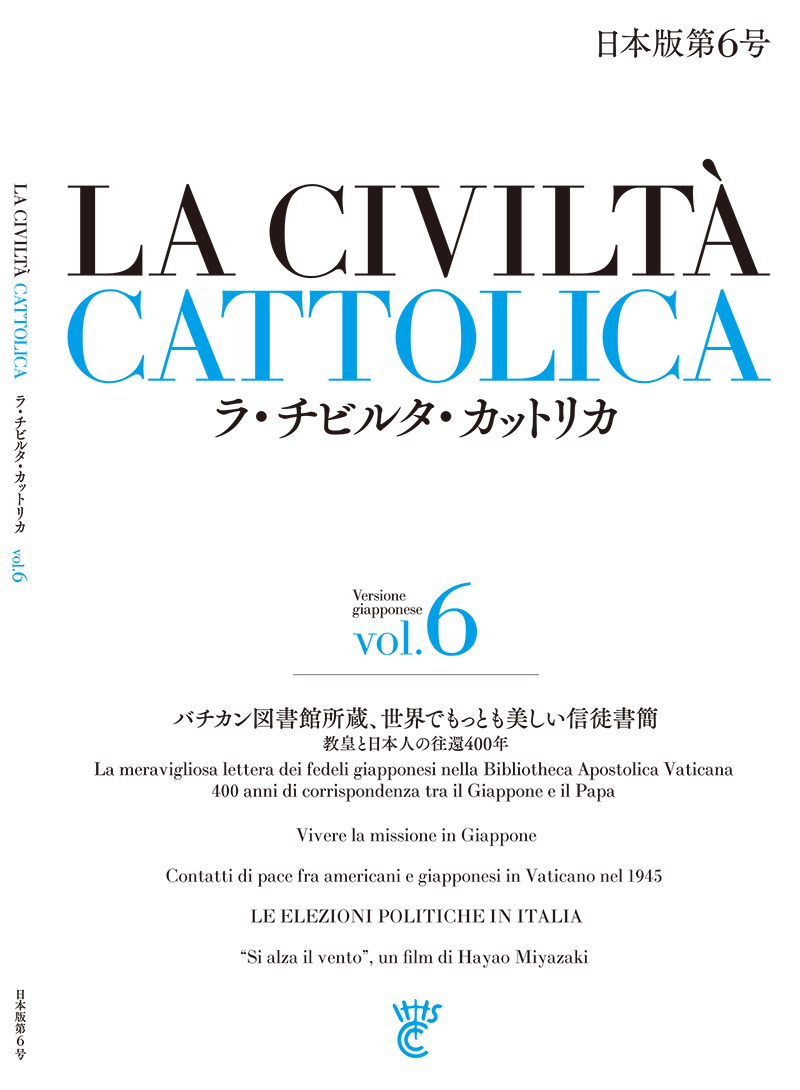La Civiltà Cattolica
日本版
(公財)角川文化振興財団バチカンプロジェクトから刊行!
ローマで発行された最古のカトリックジャーナルが史上初、日本版で刊行されました。
日本版6号
日本で宣教に生きるとは
Vivere la missione in Giappone
Adolfo Nicolás S.I.
アドルフォ・ニコラス神父
上智大学で長年教鞭をとり、
日本での長い宣教経験を持つ、
アドルフォ・ニコラス神父(2020年没)によって書かれた記事。
日本人の精神性や、国家としての背景を理解したうえで、
敬意、感受性、希望、
という3つの言葉をキーワードに解説、
そして、 またこれからのカトリックの
在り方をも考えさせてくれる素晴らしい考察です。
La Civiltà Cattolica, 2014, III, 449-454
はじめに
1549年に聖フランシスコ・ザビエルは日本から5つの手紙を書いているが、おそらくもっとも有名なのは最初の手紙であろう。その中で彼は日本人に対する印象を次のように記している。「今までに我々が会話した人々は、我々が今までに出会った中でももっとも素晴らしい人々です。そして異教徒の中で、日本人に勝る人々を見つけることはないだろうと思います」。聖フランシスコは、日本人の礼儀正しさ、誠実さ、そして名誉を重んじる点を称賛していた。
おそらく今日、同様のことを断言するのは「政治的に正しい」とは言えないだろう。しかし、聖フランシスコの言葉を反響させることについて、お話ししたい。私は30年以上もの間、日本にて生活し、働く機会に恵まれた。日本人は私が出会った中でももっとも思慮深く、教養があり、調和のとれた人々であると思う。彼らが秩序や組織、法の順守を重んじることはよく知られている。また、危機的状況や緊急事態において、実際に最近の福島の危機の際に我々が目にしたように、彼らは深い同情と思いやりを示す。
ここでさまざまなエピソードを話す時間はないが、日本人が危機に際して自尊心や規律、犠牲の精神をもって対応したことが世界を驚かせたことを思い出していただきたい。
敬意
まず第一に、本質的な姿勢から我々の考察をはじめることが重要であろう。それは「敬意」とも言えるものである。つまり教会や宣教師たちの到達以前から、神はその地の人々や彼らの文化の中にすでに作用していたという根本的な確信である。これは第二バチカン公会議にとっても重要な考えであり、過去の我々の宣教の歴史では、この前提が必ずしも出発点となっていなかったこと、そして現在においても、我々と異なるものに対する敬意が不足していることを考えると、そのことを今一度強調するべきであろう。
第二バチカン公会議の「教会の宣教活動に対する教令」に関して思い出してもらいたい。これは、「真実や恩恵は、まるで神の隠れた存在であるかのように、すでにさまざまな国の中に存在している」ことを強調している。この教令の11章のような美しい言葉の中で、宣教師たちは、「その国の伝統や宗教を根底からよく知る」ため、そして「そこに隠れている神の言葉の種を喜びと敬意をもって発見する」ために、派遣された土地の文化にどっぷり浸かることが奨励されている。彼らは「真摯で忍耐強い対話を介して、寛大な神が人々に与えた豊かさを知る」のである。
この教令に使われているすべての言葉、すなわち「喜び」や「敬意」「真摯で忍耐強い対話」、そして「知る」ことに対して開けていること、これらすべてが、相手に敬意を持つよう奨励していることに注目するべきである。
我々がどんなことを言い、議論したとしても、私は日本やアジアの人々の文化の中に神がなしたものに対して敬意を持つという、この本質的態度が常にあることを願っている。
感受性
我々はまず方向を定めるうえで不可欠な態度からはじめてきたが、次に、日本やアジアでの宣教における二つ目の展望を提示したい。それは「感受性」と呼べるもの、すなわち人間のもっとも奥深くに「隠れた」側面における感覚である。これは何を意味しているのだろうか。日本人は世界の中でももっとも音楽的な人々である。イギリスの音楽評論家イヴァン・ヒューイットが主張するように、「21世紀初頭のクラシック音楽の中枢」は、ウィーンでも、ベルリンでも、ロンドンやニューヨークでもなく、東京である。それはこの街が世界のどの大都市よりもコンサート会場を持ち(ベルリンよりも多い!)、9つのオーケストラを持っているということが示しているように、東京の人々がクラシック音楽に対して「情熱的愛着」を持っているためである。「観客は熱烈としか言い表せないような沈黙の中で聴いている」。さらに彼はこう続けている。「東京でのコンサートの間、私の隣の人は、バッハの『マタイ受難曲』の3時間の間中ずっと、まったく動くことなく、目を閉じたまま座っていた。リズムに合わせて小さく動く小指だけが、彼がまだ生きていることを示していた」(デイリー・テレグラフ、2006年5月20日)。
このことが宣教とどういう関係があるのだろうか。私は、宗教とはまず、説明による合理的システムというよりも、この「音楽的感覚」に非常に似ていると思う。宗教は第一に、我々の経験に対する超越性や深さ、無償で、美しい側面に対して開ける感覚である。しかし、これは今日では、現実よりも深い側面へと到達することを妨げるような経済的、物質的メンタリティーによって脅かされている感覚なのである。
日本の音楽界の著名人で、世界でも最大規模のコンサートホールの一つである水戸芸術館の主任学芸員、矢澤孝樹が、日本人が音楽的感覚を失っていることを心配していたことは注目に値する。大きなコンサートホールの中で、彼は音楽評論家イヴァン・ヒューイットに次のように言った。「このホールで静寂を感じますか? これこそが音楽が真に必要としているものです。しかし我々の生活の中に静寂は今やほとんどありません。私は若い世代が音楽を聴くことができるのか、と疑問を感じます」。
そして矢澤は日本の古い概念である「間」に言及し、音楽が「静寂との絶え間ない会話によって成り立っている」ことを主張する。音楽の感覚が、現代そしてポストモダン世界の音やスピードによって侵蝕され、衰えているように、同様のことが「宗教的感覚」すなわち神との出会いが可能となる現実のもっとも深い側面に対する感覚においても起こっているのである。
しかしまさに「音楽の感覚」が失われるのと同時に、それが取り戻され、学習されることも可能である。ユーチューブ上で、ベンジャミン・ザンダーのTEDでの有名なスピーチを見ることができる。彼はそこで、識者たちにクラシック音楽をどのように鑑賞するのかを教えている1。それはまさに信じられないような授業であり、観客を熱狂させ、それ以前は真の意味で聴くこと、「感じること」ができなかったショパンを素晴らしいものだと評価できるようにさせるのである。これと同じ方法で、日本やアジアにおける今日の宣教活動もまず第一に、この「音楽の感覚」「宗教の感覚」、すなわち人生の物質的概念よりもより深いところにある次元を意識する感覚を、人々が発見ないしは再発見できるよう手助けをする必要があると考える。
特に、日本人にこの「感覚」を取り戻すことを意識しているのが、上智大学である。おそらく教育こそが、日本人の「宗教観」を保持するための最後の可能性となるだろう。残念ながら「今日多くの著述家や研究者たちが世界中の大学教育の危機について語っている。批評家の中には、大学が市場の必要性によって支配され、若者たちが良い収入を得て、市場が与える良いポジションにつけるよう、働くための訓練をする場となってしまっていると言う人もいる。また研究も、経済によって方向付けられ、産業や商業に奉仕するだけのものとなっている。競争、出世欲、経済的な利益を追求することがいくつかの大学では自身の牽引力になっているのだ」という。
大学が、我々のこの実利主義的社会に対する人間の合理性や自己理解を詰め込むことに限定されてしまったら悲劇であろう。教育機関のとるべきプロセスはまったく異なる。つまりここでは宣伝のための教育ではなく、変容のための教育を言っているのである。我々は新しい人間のタイプ、音楽的であり、美や善、他者の苦しみや憐れみに対する感受性豊かな人物を形成することを求めている。だから我々は「キリスト教教育」を提供するのだ。なぜならキリストこそ、経済や物質的生産物に限定された関心を超えた視野を我々に与えてくれると確信しているからだ。キリストはより豊かな人間の視野を提供してくれる。それは他者に対する配慮や心配のもとに人が自分自身を超えることを促す。キリストは世界に蔓延している情報を単に与えるのではなく、知恵や配慮を与えるのであり、それこそ真に人間的なものであり、まさに日本人が伝統的に敏感に感じていたものなのである。
それではいったいどのようにして、ある種「音楽的感覚」と私が定義したこの「宗教観」を促進することができるだろうか。私はこれが今日の日本やアジアにおける宣教の本質的な挑戦であるように思う。この挑戦は、神学的考察と創造的な司牧を求めている。上智大学は、学生や教師が、存在の本質的側面に向けられたこの感覚を保持し、深めるためにしていることを、徹底的に問うことができるように思う。
日本の詩人であり多方面で活躍している新井満が、上智大学の創立100周年記念の際にリリースした『神様のシンフォニー』にて、アッシジの聖フランシスコの祈りを訳す際、「わたしを[あなたの祈りの]楽器にしてください」として、あえて「道具」という言葉を「楽器」としたことは非常に興味深い。このようにして彼は、ここまでに言及してきた「敬意」と「感覚(音楽的感覚)」という二つの概念を一つにした。そうすることで、我々は我々とは異なる人々とともに、神のシンフォニーを奏でる新しい可能性を得るのである。
希望
私の三つ目にして最後のポイントは、「希望」に関わるものである。今日の日本には、たくさんの問題が存在していることはよくわかっている。福音が告げられてから400年たった今も、教会はまだ少数派のままであり、急速に老朽化している。何よりも、私はほとんど絶望的なトーンで「日本での福音は失敗した」とする評価を聞いたこともある。
霊操の魂の衝動のもとに考えてみれば、今日の日本に見られると言われる「教会の苦悩」について話せるかもしれない。そのようにこの衝動を定義すると、それが思慮と行動をいかに必要としているかということに気が付く。霊操において、聖イグナチオは苦悩に立ち向かうための思慮を我々に与えてくれる。苦悩の中にいる人に、「神の助けは、それをはっきり感じない時でも、常にその人の近くに存在する」(320)ことを思い出させてくれる。そして「苦悩の中にある人は忍耐するよう努力する」(321)ことを助言し、慰めは「信仰を獲得したり保持したりすることは我々によるのではなく、いかなる精神的慰めでもなく、すべては我々の主、神の恩恵によることを心の奥底で感じない限り」(322)我々から離れていくと断言している。そして我々に苦悩とともに耐えることを奨励しているのだ。なぜならそれは我々の愛を清める方法であり、「慰めや恩恵の支えなくして主の奉仕や称賛にどれほど進むことができるかを我々に感じさせるための」(同)方法なのだ。
さまざまな方法で、イグナチオは苦悩の中にいる人に、神の意図に対するより広い視野のもとに克服するよう促している。そしてこれもまた、日本やアジアでの宣教を語る際にとるべき重要な態度であろう。
2009年にこの世を去った日本の有名な神学者小山晃佑は、『時速五キロの神』という非常に興味深いタイトルの本を書いた。小山は我々の焦りや、最新のテクノロジーのスピードを求める欲求、そして我々の宣教について語っている。我々はすぐに成功が手に入ること、そしてすぐに結果が出ることを求める。しかし彼は、これは神の歩みではないと強調している。神は、「時速5キロ」で進む。これは人間の歩く速さである。小山はこれが神のスピードであると説明する。なぜならこれが愛のスピードであるからだ。彼はこう書いている。「愛にはスピードがある。それは精神的なスピードである。それは我々が慣れているテクノロジーのスピードとは異なるタイプのスピードである。愛は我々の人生の奥へと時速5キロのスピードで進んでいく。我々が気づくと気づかないとにかかわらず。それは歩くスピードであり、それゆえ神の歩く愛のスピードなのだ」。
ヨーロッパ人たちがいわゆる「アフリカの探検」に専念していた時代があった。これらのヨーロッパ人の一人がある時、広大な平野と丘を重い道具を肩に担いで運ぶためにアフリカ人の集団を雇ったことがあった。するとある時点でこのアフリカ人たちはみなそろって休息のために止まり、一方でヨーロッパ人たちはできるだけ早く進むことを望んだ。ヨーロッパ人が何をしているのか彼らに尋ねたところ、彼らのうちの一人が答えた。「私たちは私たちの心が体に追いつけるように、進むのをやめたのです」と。彼らは人間のあるべき正しいスピードを知っていたのである。
私は日本やアジアにおける宣教が、そこにいる人々や文化に対して神がなした御業に深い敬意を表明し、人々の宗教観を忍耐と希望をもって目覚めさせるようなされることを願ってやまない2。
[原田亜希子訳]
2 東京の上智大学創立100周年を記念して3月14日にローマグレゴリアン大学にて行われた国際シンポジウム「過去から未来へ アジアにおけるカトリック教会の使命:上智大学の貢献」でのイエズス会総長の開会の辞より。
1945年のバチカンにおけるアメリカ人と日本人の和平交渉
Contatti di pace fra americani e giapponesi
in Vaticano nel 1945
Robert A. Graham S.I.
ロバート・A・グラハム神父
終戦から78年目を迎えるいまなお、
明らかになっていない歴史が
たくさんあります。とはいえ、
究極の事態の中、奔走した多くの
日本人、イタリア人、
そしてアメリカ人たちがいたことは事実。
これは1971年に書かれた記事ですが、
東京とワシントン、そしてローマを拠点に
どのような動きがあったのか、
いまとは違って情報伝達方法も
限られていた中、錯綜する情報と
政治的な圧力が、原爆投下を防ぐに
至らなかった経緯を
詳細に解説しています。
La Civiltà Cattolica 1971, II, 31-42
1945年の5月の半ば頃、当時の日本の最高責任者たちはアジアにおける戦争に負けるであろうこと、そして最小限の犠牲で名誉ある講和を得ることを模索する以外にもはや道は残されていないことをすでに確信していた。しかしながら、交渉は1945年8月の広島への原爆投下後になって初めて開始されることになる。歴史家たちはこの致命的な遅れに関して多くの議論を重ねてきた。数週間の違いが大きな意味を持ったことだろう。元駐日アメリカ大使のエドウィン・O・ライシャワーは「日本が降伏した日が2週間遅くても早くても、戦後の世界に重要な結果をもたらしたことであろう」と述べ、もし降伏がもっと早くなされていたならば、原爆が暗い記憶を残すことはなかったであろうと指摘している1。
スイスの日本人とローマのアメリカ人の試み
しかし太平洋戦争は、8月以前に本当に終結できたのであろうか。もちろん、天皇による無条件降伏は非情な歴史のプロセスにとって避けられない結末であった。盲目的で狂信的な者だけが、日本の終わりの前兆を無視できていたにすぎない。我々は、日本人が和平交渉をはじめるよう東京を説得するため、スイスにて非公式の試みを少なくとも二度にわたって事前に行っていた事実を知っている。二度目はベルンの海軍中佐、藤村義朗が行ったものであり、彼は5月8日から、当時スイスのアメリカ戦略事務局の支局長を務めていたアレン・ダレスとの交渉を開始するよう、上層部に何度も要請している。結局藤村は彼の努力もむなしく、同盟国側の罠にかかったと後悔することになった。
二度目の試みは、チューリッヒにて岡本清福中将によってなされたものであり、彼はスイス人の仲介者を通じて、フランクフルトにてアレン・ダレスとの接触を試みた。これら二つの試みは二人の日本人による個人的なイニシアティブに過ぎず、政府からの支援もなかったために失敗に終わることになる。その一方で、日本の指導者たちは悲劇的な過ちに向かって進んでいた。モスクワ経由で和平工作を行おうとしていたのだ。しかし彼らはスターリンがヤルタ会談にて、ビュートーが表現したようにまさに「最高入札者に彼らを売ろうとしていた」ことなどまったく知る由もなかった。駐ソビエト連邦大使の佐藤は、数週間にわたる試みの末にようやく外務人民委員のモロトフとの会見にこぎつけたものの、彼から宣戦布告を通知されることになる。
一般的に、この決定的な数週間の間、アメリカは消極的な態度にとどまり、和平に向けての外交的交渉を進めるようないかなる行動も起こしていなかったように思われている。おそらくアメリカはイタリアやドイツに対してなされたような「無条件降伏」の道にとらわれていたのであり、日本の名誉ある形での降伏など、誰一人真剣には考えていなかったのである。しかしその例外が当時ローマで活動していたOSS(戦略事務局)の局員の活動であり、この人物は教皇庁に派遣されていた日本の外交官との接触を図っていた。このVessel計画の歴史や、どのような作戦だったのかということに関しては、それに関わる人物たちの秘密主義のため、今まで語られたことはない。私が知る限り、Vesselという名前自体、今まで公になったこともない。戦時中になされたこの手の他の多くの試み同様に、この計画もいかなる結果ももたらすことはなかった。地上にまかれた種が、水不足のために花を咲かせないようなものである。しかしVessel計画は、戦争末期の悲劇的な歴史の中に確かに存在したのであり、日本に「降伏の決定」をもたらした一連の劇的な流れの中で言及されるに値するものである。
1945年6月、ローマで活動していたOSSの局員が、ウィリアム・ドノヴァン大佐の指示のもと、仲介者を介して教皇庁のもとにいた日本の特命全権公使、原田健との接触を図り、もし日本が望むのであれば、ローマを介して(バチカンとは無関係に)ワシントンと直接コンタクトをとる可能性があることを提示した。この情報を仲介したのが、現枢機卿[原文ママ]であるエジディオ・ヴァニョッツィ猊下であり、彼は当時バチカン国務省で特別任務を担当していた。
その後、原田と東京の外務省との間で電報が交わされた。しかしながら結果はNOであった。東京はこの件に関して何ら興味を示さず、原田から仲介者を通じてもたらされた返事とは、もしワシントンが何か伝えたいことがあるのであれば、彼自身がそれを日本に伝えるというものだった。ワシントンからの動きのないまま数週間が経過し、そうして8月になった。皮肉なことに、2か月前のバチカンでの接触の際に提案されたものと同じ条件のもとでの降伏がなされた。現在、この一件に関与していたアメリカ人は以下のように述べている。
「今となってはこの出来事は短い脚注にまとめられることでしょう。もし実現していたなら! 東京の側からほんの少しでも動きがあったならば、原爆投下の1か月前に和平の可能性が期待できたでしょう。現在の世界はどれほど変わっていたことでしょうか!」
主張されたが実際には実現されなかった介入
このアメリカ人の局員に関しての詳細は後程述べることにして、まずいくつかの誤りを指摘しておきたい。それは少なくとも2名のアメリカ人の著述家が述べていることであり、日本人が1945年の1月から教皇に対してアメリカへの仲介となるよう求めていたという情報である。
この根拠なく主張された日本側からの試みをもっとも明白に述べているのが、『Secret Missions: The Story of an Intelligence Officer』である。その著者である、アメリカの海軍情報局次長で海軍大佐であったエリス・M・ザカライアスは次のように書いている。
「その当時から(1945年6月)、ワシントンには大量の和平工作に関する情報が送られていた。もっとも多かったのが、バチカンを通じてなされたものだ。とはいえ、バチカンはメッセージを伝えるだけであり、バチカン側からのいかなる助言もなかったのだが。それによると、天皇自身が、元外務大臣松岡洋右の兄弟であった(原文ママ)東京大司教を介して教皇の仲介を得ようとしていたという。バチカンは、大司教が天皇の要請に従って行動していたこと、そして彼が仲介者であったことをはっきりと認識していた。ただ時には彼自身が、天皇の訴えに自分の訴えを付け加えることもあった。中には、切迫した悲痛な訴えもみられ、教皇に『何か行動を起こす』ことを嘆願している。これらの試みは、4月にバチカンに届き始め、5月の間中続いた。そこでは心理戦から、強い関心と無関心とが交互に現れ、日本の決定と力を褒め称えるかと思えば、直後に日本が完全に敗北していることを認めたりもしていた2」
元情報機関の職員で、特に日本関係の専門であった人物も、だいたい同じ内容のことを、1949年8月のUnited Nations Worldに掲載された記事「原爆は必要ではなかった」の中に書いている。ザカライアスはさらに1950年6月6日に出された雑誌Lookにおいて、「日本の降伏を我々はどのように処理するべきだったか」と題された記事の中で別の詳細やコメントを書き加えている。彼は弁明しながらも、アメリカ合衆国政府はもっと慎重になるべきだったのであり、もっと早く日本人の絶望と降伏する意思に気付くべきであったと主張している。「その方向での最初の試みであり、うまくいっていたことが確認できるものこそ、日本の天皇が教皇庁に、我々との交渉に介入し和平交渉のために教皇ピウス12世自身が仲介者となって我々の条件に関して情報を得るよう要請したことである」と続ける。
「この試みには、教皇だけでなく、枢機卿ピエトロ・フマゾーニ・ビオンディ猊下も参加していた。彼は布教聖省、つまりバチカンの諜報機関(原文ママ)の長官であった。さらに東京大司教・ペトロ土井辰雄や、東京の枢機卿の二人の代理人、そして当時イタリアでバチカンを介してこの二国の連絡回路として活動していたOSSの特別委員のメンバーが参加していた」。しかしワシントンはこの接触を取り合わなかったと、ザカライアスは後悔を込めて指摘している。「もし東京が本当に和平を結ぶ心持ちであるという証拠が必要だったのであれば、まさにバチカンへの訴えがそれを示していたのだ。残念ながら海軍省とOSS以外で誰一人としてこのことを真剣に取り合ったものはいなかったようだ。実際、国務省はこれらの試みをすべて抑制し、アメリカの世論はローマのカトリック教会の助けによって得られる和平を決して認めないだろうからとして、OSSに対してこれらを断ち切るよう指示している3」
ラディスラス・ファラーゴは彼の著書『Burn After Reading』の中で別の詳細について言及している。彼はザカライアスの補佐として海軍の諜報部門の調査を担当していた。彼は、後の大使であり、その当時ピウス12世のもとにルーズベルト大統領によって派遣されていたマイロン・チャールズ・テイラーの補佐を務めていたハロルド・H・ティットマンと、フマゾーニ・ビオンディ枢機卿が連絡を取り合っていたと主張している。ファラーゴはこの件に関するティットマンの報告書は国務省ではなく、OSSの管轄であったと述べ、さらに次のように書いている。
「私は、もっとも高位にあるドノヴァンの助手の一人による最高レベルの伝令によって報告書が届いたことをよく覚えている。この試みに天皇が参加した時、我々の希望は再び高まった。しかしこれがバチカンを介して行われたものであったことを理由に放棄するよう命令が下された。いかなる方法であれ、日本の降伏を早める試みに教皇庁を介入させることは、当時のアメリカの世論を憤慨させることへの恐れから、考えられないことであったのだろう」。さらに彼はこう続けている。「バチカンは日本が降伏の途を模索していたことを天皇自身の介入から直接知っていたのだが、この問題を公式に扱うことを拒否した。それは当時アメリカ合衆国との間に公式の外交関係を持っていなかったためである(原文ママ)」4と。
これらの著者たちが戦争中に務めていた役職のおかげで特別な情報にアクセスできたことは認めるとしても、そしてまた彼らの善意を尊重するとしても、ザカライアスとファラーゴの日本に関するこれらの情報は完全に誤った情報に基づいたものと言える。今までにこれらの情報が真実であるという証拠は存在していない。一方で、当初から何らかの「バチカン専門記者」による巧妙な詐欺の痕跡ははっきりと現れている。また近年米国務省によって公開された外交書簡でも、1945年の初頭にOSSが間違った情報を得ていたことが示されている。すでに1945年の1月にOSSは国務省に例の教皇庁への日本の和平の試みについての誤情報を送っているのである5。
国務次官のジョセフ・グルーへの報告書の中で、極東部門の局長であったジョセフ・W・バランタインは次のように1月30日付で書いている。
「OSSよりバチカンからの情報として、1945年の1月の初頭から日本の交渉に関する一連の報告が届いた。それによるとバチカンは太平洋戦争に対して教皇による仲介を準備しているという」。その後、さらにそのアプローチや想定される大まかな和平の合意に関する記述が続く。そしてバランタインは次のように結論付けている。「OSSの報告はかなり詳細なものであり、細部も正確であるために、信頼に値するものである。極東局はこの件に関して細心の注意を払い、いかなる進捗情報をもつぶさに報告するだろう」
この見通しでは、日本からの「接触」はバチカンへの申し出からアメリカ人との直接交渉へと移っていった。原田はテイラーに会ったというが、しかしこの時国務省はようやくこの情報ルートを調べている。というのも間違いなく、これはこの当時多くの怒りの原因にもなっていたであろうからだ。実際、ワシントンの国務次官グルーと、バチカンのマイロン・C・テイラーとの間の書簡では次のようなやり取りがなされた。
「ワシントン、1945年2月21日、13時
政府の秘密の情報筋ではあなたが原田健と最初の会話をしたというが、もしこの会話が本当になされたのであれば、当然あなたがそれに関する報告をしているだろうと推察する」
「バチカン市国、1945年2月23日、11時
国務省からの2月21日13時の内容に関して、私は原田健とは会っていないし、彼と話したことすらない」
OSSの情報に対するこの矛盾が発覚した結果、国務省がOSSのバチカンに関する報告書を慎重に扱わなくなったとしても当然と言えよう。しかしOSSは間違いなく、バチカンで信頼していた情報元によって判断を狂わされていたのだ。
この一連の誤った情報のもとが一体誰だったのかはまた別の問題であり、そしておそらくこれに関しては確実に突き止めることは不可能であろう。しかし少なくとも当時ローマにはこのような大量のウソをつくり出していたであろう人物が一人存在した。OSSの報告書の形式には、ヴィルジリオ・スカットリーニという、バチカンの誤った情報を流していた人物による間違えようのない独特の刻印が見て取れる。1939年から1948年の彼の逮捕と判決までの間、スカットリーニの情報は教皇庁の情報を求めていた当時のさまざまな諜報員の間で大成功を収めている。ただ彼の情報を安易に信じてしまったことをOSSが恥じる必要はない。すでに1941年の段階でナチスによって送られたスカットリーニの偽情報はヒトラーのもとにも届いていたという6。裁判でスカットリーニは、1944年7月以降、彼は自分の情報をAssociated PressやUnited Press、Inter-national News Serviceといったジャーナルだけでなく、軍事機関やイタリアの軍事諜報機関にも売っていたことを証言している。これら販売された情報のどれか、あるいはそれらとは別の何かによって、OSSのエージェントが秘密の情報を入手していた可能性が考えられるのであり、そしてそれがワシントンに大きな印象を与えたのだろう7。
Vessel作戦
Vessel作戦は、これまでに述べてきたものとは一切関係ない。ザカライアスやファラーゴがこれに関する情報を得ていたかどうかに関してはいかなる言及もしていない。当然OSSはその機密情報すべてをアメリカ海軍情報局に打ち明けていたわけではないだろう。Vessel作戦を担当したエージェントは現在会社経営者であり、アメリカにて生活している。彼はそのミッションについて次のように述べている。
「1944年、OSSの長官ウィリアム・J・ドノヴァンの指示のもと、私は情報部門のイタリア担当に任命された。私は戦争の最後まで名目的にはこの部門の一役職者にすぎなかったが、実際には完全な自由裁量のもとに活動することができていた。私の主な目的は、イタリアの軍事、政治活動と特に関わらないような情報であり、指令は長官のドノヴァン自身から与えられ、私の任務はバチカンやその他のローマにあるカトリック施設を通じて、アメリカ合衆国の戦争に役立つような情報活動を発展させることにあった。ドノヴァン長官との会談の際に一度、彼はバチカンがドイツや日本との交流の場となり得る可能性をほのめかしていた8」
このエージェント、これ以降はこの作戦の名前で彼のことを呼びたいと思うが、このVesselは1944年の末に表向きはイタリアの民主改革のための助言者としてやってきた。彼は自分の真のミッションを必要ならばいつでも明かすことができる特別な権利を有しており、最終的に彼の真の正体を知ることになるのはバチカンの3人の人物であった。一人はアメリカ人聖職者で、現在はすでに亡くなっている。もう一人はエンリコ・ガレアッツィ伯爵であり、そして3人目がこのあとみるようにヴァニョッツィ猊下である。彼は当時バチカンのサンタ・マリア宮で生活をしていた。
Vesselは別のセクションではあるが、同じ建物内に原田健の非公式の相談役であり、その後札幌の司教を務めたベネディクト冨澤神父が住んでいることを知った。
「ドノヴァン長官からの指示に基づいて、私は新しいコミュニケーション回路を開くことを決めた。この回路は、多くの問題を避けることができるであろうものだった。というのもこれは直接的、個人的なものであり、いかなるジャーナリストやその他の情報機関の干渉を受けることなく、バチカンの保護のもと、バチカン市国内に住む者の自由を利用したものであり、かといって教皇庁に決して負担を強いるようなものでもなかったからだ。私が考えた計画とは、コミュニケーションのためにヴァニョッツィ猊下と冨澤神父との間の友好関係と、両者が同じ建物内に住んでいる状況を利用したものであり、それに関するすべての詳細をワシントンに報告していた。この方法では、教皇が当時尊重されることを望んでいたバチカンの中立性を危険にさらすこともなかったし、また日本人のカトリック教会に対する反感についてはよく知っていたので、彼らに教皇庁を通じて和平を提案するようなものでもなかった。ローマとワシントンとの間のコミュニケーションは秘密裏に行われたのだ」
この試みに、Vesselはワシントンからの全権委任大使との会合の機会を計画することを期待していた。「私はドノヴァン長官との、そして彼を介してホワイトハウスとの直接のコミュニケーションを頼りにしていた。数日のうちにドノヴァンと大統領の代表がローマ、もしくは近郊の秘密の場所にて日本の代表と会談することができるはずだった」
6月4日にVesselはヴァニョッツィ猊下に彼の家で午後を一緒に過ごすよう提案した。仕事に追われ、使える時間は少なかったものの、Vesselは彼に協力を説得し、彼がこの接触を設けることができる唯一の人物であるということを認識させなければいけなかった。
「何年もたった今でも、はっきりとあの二つのバルコニーのある小さな食堂でのやり取りを覚えている。私の人生の中でもっとも重要でもっとも難しい対談だった。しかしながら午後の終わり頃には、ヴァニョッツィ猊下は彼の外交官としてのキャリアを危険にさらすことを認識しながらも、最終的に同意に至ったのだ」
それでは今度はヴァニョッツィ猊下の証言に移ろう。
「ある日、私は冨澤神父に話したい旨を伝えた。彼はそれを受け入れ、私をお茶に誘った。私は直接原田氏のもとには行きたくなかった。初め冨澤神父は、彼の国が今大きな損失に苦しんでいることを認めながらも、日本の降伏の可能性は認めなかった。そして新しい武器と戦術を準備しているのであり、それによって戦局は変えられるだろうと主張した。私はもし戦争がさらに日本本土に近づけば、日本が受けるであろうさらなる人的、物質的被害を強調した。最終的に冨澤神父は日本の高官にこの任務について話すことを承諾した」。
ここでこの非常にデリケートな状況のいくつかの点を明らかにする必要があるだろう。まず第一にVesselの意図は、交渉することではなく、どんな協議を行う上でも不可欠な要素であるコミュニケーションの回路を設定することにあった。さらに二つ目に、Vesselは教皇庁がいかなる形であれ介入することを望んではいなかった。つまりヴァニョッツィ猊下はあくまで個人的に行動したのであり、彼自身彼の上司にこのことを報告していなかった。
最初の点に関して、Vesselは実際には和平の条件についてほのめかしている。ヴァニョッツィ猊下に述べた条件は以下の三つである。それは日本が軍事的に占領されること、天皇がその地位を維持すること、そして領土を征服する野心はないということである。
Vesselはこれらの条件に関してはすでにワシントンにて漠然と話されていると説明した。どうも、その数週間後に天皇がその地位を保持するという日本の和平にとってもっとも重要な点が決められたようではあるが。
第二の点に関して、一見したところ和平交渉への教皇の直接介入は中立の侵害としてみなされうると考えることには矛盾があるように思われるだろう。「よき職員」を介在させる申し出は、国際法によって非中立的行動とはみなされていない。一方で、ピウス12世が交戦国の片方からの要請失くして、和平交渉には介入しないと決意していたことは事実である。教皇の直接介入に関しては、現在も多くのあいまいな点を生み出しており、そこには打ち負かされつつある国の国民のモラルをさらに衰弱させる試みへの不安も含まれる。いずれにせよ、Vessel自体は決して教皇庁が公式に彼の計画に参加することを望んではいなかった。
この状況を前にした公使、原田健の立場は決してうらやましいものではなかった。まさに国のもっとも深刻な時期に政府から孤立し、たとえどんな解決策を選んだとしても、個人的なさまざまな影響をもたらす決定をしなければいけない状況に置かれた外交官のジレンマに直面していた。彼によって降伏する可能性があることを彼の政府に伝えるべきか、否か。外交官としての信任状もなく、よく知らない人物からの漠然とした提案、しかもそれがバチカンの役人の個人的な立場のもとに、上司にも報告しないまま、この第三者の手を介して寄せられているのであり、そんな提案に一体どれほどの信頼を置けるだろうか。一体どうやってこの提案によって述べられた条件を、誤解を生むことなく、また売国行為や裏切りとしての非難にさらされることなく、電報の限られた文字数の中で説明することができるだろうか。一方で、おそらくそれがたとえ残念なものであったとしても、そうでなかったとしても、すべての状況を本国に報告することは外交官の義務ではないのか。これと同じジレンマは、原田のもとで秘書を務めていた金山政英も感じていた。
我々は外国で長年任務を経験してきた高官である原田が心の中で一体どのようなことを考えていたのかを知る術はない。しかし少し遅れて彼は東京にメッセージを送った。彼の外交官としての素質は決して間違っていなかった。というのも彼の上司たちもこの時、戦争を名誉ある形で終えるために同じ不安を感じていたのだ。
日本の首都は極限の状態であった。最高戦争指導会議は5月の11日から14日にかけて戦争の深刻な状況を議論するために開かれ、そこには内閣総理大臣、外務大臣、海軍大臣、陸軍大臣、参謀総長と軍令部総長が参加した。彼らの関心は、ソ連の仲介をどのようにしたら得られるかという点に集中していた。その計画は下位の者には知らされておらず、また6月8日の御前会議にてこの戦争を最後まで継続することが全会一致で決定された。一方でモスクワのもとでの終戦工作は放棄されることはなかったが、その兆しはいっこうに見られなかった9。
つまりもし原田の電報が6月の第1週の段階で東京に着いていたとしても、東郷はすでに和平工作はソ連経由で行うという考えを承認していたのである。またもしこのメッセージが東郷には届いておらず、その下の者にしか届いていなかったとしても、彼らは最高戦争指導会議での話し合いを知らなかったのであり、おそらくベルンでの藤村の要請が日本の海軍省の記録に残っているように、記録が残されたであろう。我々が現在わかっているのは、Vesselの報告による返答だけである。
「一体何日間原田が待っていたのかはわからないし、またどれほどのメッセージが彼から東京に送られたのか、そして誰に、または何が伝えられたのかに関してもわからない。9日後の6月13日に、ヴァニョッツィ猊下は、日本人からは特に伝えることはなく、ワシントンが東京から知りたいと思っていることはすでに伝えてあるという最終的な返答を私にもたらした。これがすべての試みの結末だった。ワシントンにこの活動に関する私の報告を送ったが、彼らから私が東京に伝えるべきいかなるメッセージも受け取ることはなかったし、日本が負けるであろうという確信のもとではそれが送られたとも思えない。ワシントンはおそらく東京からはじめてほしいと思っていた。コミュニケーション回路はあったのだ。しかし東京はそれを利用することを放棄した。おそらくこの数日の外務省の状況はあまりに混乱していたのであろう」
日本人がソ連の仲介を狙う試みがなされる間に数週間が経過した。これが盲目的な作戦であることに誰一人疑問を抱かず、他の可能性を模索しなかったことなどあり得るのだろうか。バチカンに関しては、最初の段階ではすっかり忘れられていたわけではなさそうである。ビュートーによると「バチカンは一番に考慮されたが、教皇の戦争に対する否定的な態度ゆえに、援助を求めることなど潜在的に不可能だと考えられた10」という。この著者はそれ以上の説明はしていない。
一方で、バチカンにもっと熱心に要請することを放棄したワシントン側の責任でもあるだろうか。アメリカの軍司令部は、まだあまり知られていない原爆を含む新しい武器の実験を行うために最後まで戦争を続けることを強く求めていたと主張する人もいる。Vessel自身も彼の報告書に対してどのような議論がなされたのかは知らない。「最近私はドノヴァン長官がこの重要な局面で外国にいたため、彼の代理がワシントンで、この計画に携わる任務を担当する人物が誰なのかを決めるための議論に明け暮れていたということを知った。なぜならこれが非常に重要な進展をもたらすことを信じていたからだ」
ザカライアスが非難したように、当時アメリカ側の反応がなかった原因は、おそらく「無条件降伏」というスローガンによる魅力に帰されるだろう。直前の第三帝国による「無条件降伏」を日本にも広げようとする思いがあったのだ。軍事的モットーから、このスローガンは政治的モットーとなり、それゆえ柔軟性を失くして最終的に原爆という負の遺産を残すこととなるこの戦争を長引かせた。筆者への手紙にて、当時スイスのOSSの代表であり、その後アメリカの諜報機関CIAの長官となった今は亡きアレン・ダレスは、ワシントンは当時交渉を考える余地もない状態にあったのだろうと述べている。ダレス自身、数年前に彼にバチカンでのアメリカ人のイニシアティブに関する報告書について聞かれた時に、何も知らないし、この計画が存在することを疑うと述べている。
「1945年にスイスのバーゼルの国際決済銀行を介して日本人からもたらされた交渉に私は関わっていた」と1964年6月17日にワシントンで書かれた手紙に書いている(これは先に述べた岡本の試みのことである)。「この日本人による交渉は日本の多くの出版物の中ですでに取り上げられている。当時の状況を考えれば、アメリカ合衆国が1945年に日本との交渉をはじめなかったのではないかと疑っている。もしこれらの交渉がなされなかったというのが事実であるなら、その試みが日本側からもたらされたことの方がよりもっともらしいと感じられる11」
最終的にいまだ解答がだされていない問題とは、教皇庁の介入を求めることに日本もアメリカも気乗りしていなかったことである。日本人に関しては、この態度は1942年にバチカンと外交関係を樹立していることと矛盾する。おそらく日本人の心の中には未来に対する何らかの期待があったのだろう。天皇も「戦争をはじめることは簡単だが、終わらせることは容易ではない」と述べたことはよく知られていることである。東京が結局バチカンとのつながりを使用することを放棄したのは、政治的理由によるものであろう。一方のアメリカに関しては、ザカライアスが述べていたように国務省側の核心、すなわちアメリカの国民が「ローマのカトリック教会の助けによって和平を結ぶことを認めないだろう」という確信の後ろに一体いかなる真の弁明が存在するのだろうか。これがアメリカ政府の側からのVesselの計画を利用しなかった理由ではなかったと思いたいものである。
[原田亜希子訳]
2 Secret Missions: The Story of an Intelligence Officer, New York, 1946, 364.
3 Ivi.
4 L. Farago, Burn After Reading, New York, 1961, 295.
5 Foreign Relations of the U.S.: Diplomatic Papers, 1945, The British Commonwealth, The Far East, vol. VI, Washington, 1969, 475 ss.
6 R. A. Graham S.I., Spie naziste attorno al Vaticano durante la seconda guerra mondiale, in La Civiltà Cattolica, 1970, I, 29-30; ivi, 1948, II, 311-315参照。
7 上記の論文はNew York Timesなどアメリカの新聞の切り抜きを集めたものであり、1941年以前のものから、1944年以後のものまでが含まれている。バチカンに関しては明らかにヴィルジリオ・スカットリーニによる作り話をもとにしたものである。
8 ドノヴァン長官に対して1944年6月28日にピウス12世は特別謁見を行っている。
9 便宜上ここではビュートーの年代記述に従う。Op. Cit. 88-91. しかし日本の外務省によって日本語で出版された終戦後の関連年表と比べると、彼はすべてを、また年代順には記述していないようである。
10 Ivi. 87.
11 著者は1962年にロックフェラー財団の奨学金によって行った研究活動にてVessel計画の最初の資料を発見、1966年にOSSのエージェントが誰なのかが判明。その後も彼の話を聞き、データを確認するまでには時間を要した。
イタリア総選挙
LE ELEZIONI POLITICHE IN ITALIA
イタリアの首相に女性として
初めて指名されたジョルジャ・メローニ氏は、 極右政党「イタリアの同胞」(FDI)の党首。
ウクライナ問題も含め、
その動向が気になるEU各国ですが、
この選挙結果を導くことになった
政治的背景や、イタリアが国として
抱える諸問題を指摘、
今後の課題を含め、
わかりやすく解説しています。
La Civiltà Cattolica, 2022, IV, 105-111
2022年9月25日の選挙の結果によって、中道右派連合が過半数の議席を獲得した。ジョルジャ・メローニ率いる「イタリアの同胞(Fratelli d’Italia)」は上院、下院ともに26%の得票率を獲得し、両院での右派連合が獲得した票数の半数以上となる大勝利を収めた。中道左派連合の得票率は26%ほど(下院では26%強、上院では26%弱)であり、ここに二つの主要勢力の距離が大きく開くこととなった。また単独で参加した「五つ星運動」は両院で約15.5%であったのに対し、マッテオ・レンツィ率いる「イタリア・ヴィーヴァ」とカルロ・カレンダ率いる「アツィオーネ」による政党連合は7.8%を下回った。
中道右派の勝利は、政党連合に有利となる選挙システムから、十分予想されていた。次期政府が挑むべき挑戦は山積みである。戦争によって新たな資源の必要性が急激に加速し、エネルギー危機がグローバル化の動きを破壊して経済危機を引き起こす一方で、ヨーロッパはコロナからゆっくりではあるものの徐々に立ち上がり、「再興・回復のための国家計画(PNRR)」の新しいステージに取り組まなければいけない段階に入っている。さらにもう一つの課題は人口問題である。イタリアは高齢化が進み、出生率に対する適切な政策をいまだ見出せていない。さらにここに、国の構造上の深刻な問題も加わる。人口問題は数年のうちに福祉国家としてのイタリアを支えきれなくなり、インフラへの投資がなければ南部と他の地域との間の格差はさらに広がっていくだろう。そして若者の活用の問題である。現在多くの若者が国外に移住する傾向にあるが、彼らなくして国の未来の展望は持てないであろう。
この新しい政府がどのような形を持つようになるのかを目にするのを待つ間に、視野を広げ、この新政権の各勢力を理解するためにもいくつかの点について考察してみたい。
投票率の低下と挙国一致内閣の終焉
36%のイタリア人が投票に行かなかった。これは史上最悪の数値である。投票率は2018年の前回の選挙と比べて9ポイント下がった。
このデータが、市民が政治から離れている証拠であることは否定できない。政治への参加、それがもっとも顕著に表れる投票率の低下は、人々の無関心と失望を示しているのであり、これは民主主義国家にとっての深刻な問題である。
このようなネガティブな傾向の理由としてまず第一に、以前は相いれないことを表明していた政党同士の連立政権と、マリオ・ドラギによる挙国一致内閣の任期を待たずした解散によるものであろう。この歴史は非常に混沌としたものだった。マッテオ・サルヴィーニの「レーガ」と「五つ星運動」に支えられた第一次コンテ内閣、その後「五つ星運動」と「民主党(PD)」、中道左派の連立のもとでの第二次コンテ内閣、そして「イタリアの同胞」以外のほぼすべての政党が参加した挙国一致内閣が相次いで発足した。
2022年7月21日の決議の結果、17か月にわたるドラギ政権が幕を閉じた。この非常に独特な結末は、この政権のあいまいさが表れたものだった。信任投票では95票の信任票を集め、反対票は38票だった。しかしドラギ政権を支えていた連立主要政党である「五つ星運動」「フォルツァ・イタリア」「レーガ」は、政府への反対票を表明しないために棄権している。この3政党は連立の代償を払うこととなった。
多くの国民にとって、さまざまな政党の同意のもとに効果的に行われていた政権を終わらせることになった理由を理解することは難しかった。確かに2023年の見通しはバラ色ではなかったとはいえ、国際通貨基金の評価によると、イタリアの国内総生産は2022年に3%と、ヨーロッパの主要国経済に比べても大きく増加するだろうという。もしこのデータが確認されれば、政府は経済システムをコロナ前の状態まで押し戻したことを意味するのであり、これは欧州連合国の中ではフランスしかまだ到達していない目標である(M. Fortis, Quanto è cresciuta l’Italia durante il governo Draghi?, in www.ilsole24ore.com 2022年8月5日)。そのうえ、首相は2022年の7月の段階で国民の60%からの賛同を得ていたのであり、また一方で彼は、欧州中央銀行の前総裁として得た高い評判を生かしてヨーロッパのパートナーからの信頼の保証となっていた(2022年9月19日にはAppeal of conscience foundation によるその年のもっとも優秀な政治家として賞を受賞)。
政党の関心への回帰と選挙の結果
ドラギを辞任させた政党の中でも、「五つ星運動」と「レーガ」の動機は似ていた。どちらも大衆の心をつかむポピュリズム的スタイルで票を獲得してきたのであり、少なくとも形の上では反対勢力に戻ることで、再び人々を惹きつけることができると考えた。数を大幅に減らした「五つ星運動」にとって、相次ぐ離党の中でもルイージ・ディ・マイオなき中で、4年にわたってそれまで敵対勢力であった政党とともに政権を担った間に、新規性をすっかり失ってしまった状態では、政権から離脱することがもはや自身のアイデンティティを確立する唯一の手段であった。一方で、サルヴィーニは「イタリアの同胞」にとってかわられた彼の政治的ポジションを取り戻す必要があった。「イタリアの同胞」は挙国一致のドラギ内閣に唯一参加しなかった政党であり、それゆえに必要な時に政府を批判したり、自身の支持者にとって有利となると思われる際には政府を支持するといった自由な活動が行えた。「フォルツァ・イタリア」は選択を迫られていた。歴史的同盟者である「イタリアの同胞」と「レーガ」に従って政府の危機を助けるのか、それとも政府に反対して新しい中道路線を進むのかを選ばなければならなかったのだ。しかし二つ目の選択肢を選ぶにはシルヴィオ・ベルルスコーニにとってあまりにリスクが高かったのだろう。彼は30年前に築いた協定を破ることはなかった。
灼熱の夏に選挙戦は急ピッチで開始された。この選挙戦で、各政党の利害が再びぶつかることになり、挙国一致は終わりを告げることとなる。
「レーガ」と「フォルツァ・イタリア」が「五つ星運動」に続いて票数を大幅に減らしたとはいえ(「レーガ」は320万票減、「フォルツァ・イタリア」は230万票減)、中道右派の陣営が優勢なのは明確だった。「レーガ」は危機の時代における昔からの伝統的な固定票は維持したが、「フォルツァ・イタリア」は後退した。しかし予想に反して、一定数を維持することには成功した。一方で大多数が「イタリアの同胞」へと流れ、580万票以上も票数を増やしている。この結果は、中道右派の布陣がはっきりしていることを示している。つまりその政治的方針を理解し、それぞれの違いを克服することに成功しているのだ。それゆえ、右派連合が投票数の44%を全体として獲得できたのである[票数は下院のみ]。
このことは、おそらくジョルジャ・メローニがイタリア発の女性首相として率いることになるだろう次期政権の保証となるだろう。この保証が、少なくとも最初のうちは、彼女を他の党首の野心から守ってくれることだろう。メローニは選挙戦の間、彼女の伝統的な路線である極右思想やEU批判をやわらげ、穏やかなトーンを保った。じきに、彼女が選挙戦の間に述べた、憲法改正の提案が進められるのか、そしてそれはどのような形をとるのかが明らかとなるだろう。
中道左派が今回の一番の敗北者である。民主党をはじめ左派はドラギ内閣の幕引きが早まったことに不意を突かれた。エンリコ・レッタの戦略とは、政府に参加することによって支持をじっくり時間をかけて回復していくことであり、また同時に「五つ星運動」との関係を構築することを目指していた。しかし「五つ星運動」は危機を前に、その道を進める可能性を絶ったのである。この陣営で動くさまざまな要素は結局まとまりを見出すことができなかった。カレンダの「アツィオーネ」はここから離れ、レンツィ率いる「イタリア・ヴィーヴァ」とともに中道路線を目指した。
こうして中道左派と民主党は同盟を広げることに失敗し、その結果敗北を喫した。今回の選挙戦に対して民主党は受け身の姿勢だった。ドラギ政権に忠実であることを唯一示しただけで、それ以外にはこれといって新しい提案をすることなく、控えめなスタイルを貫いた。にもかかわらず、民主党は2度の内部分裂(1度目は「イタリア・ヴィーヴァ」のレンツィ、そして「アツィオーネ」のカレンダ)の後、国民の同意を得られると予測し、第一党に到達するだろうと楽観していた。2018年の選挙で民主党は票数の18%に到達し、2022年には投票数自体が少なかったこと(全体としては80万票以上減少)にも助けられ19%に到達した。第二次世界大戦後のイタリアでカトリックと共産党という二つの政治的伝統の統合によって生まれたこの政党は、その起源を失った今や、アイデンティティの新鮮さという魅力を失ってしまったようである。最近では、テクノクラシー(つまり「我々は他よりもうまく統治できる」といったスローガンに翻訳できるような考え)や、急進的リベラル主義(公民権の要求を中心に据える)へと傾倒している。このような提案は今やイタリア人の大多数にとって魅力的とは言えないだろう。見通しが乏しく、直接のライバルたちによって押しつぶされてしまっている。選挙結果が出た翌日、レッタは将来のための新しい会議を招集している。
「五つ星運動」は左派に残されたスペースをうまく利用し、票数を大幅に失ったとはいえ(640万票)、第3政党のポジションは維持した。コンテは挽回路線で選挙戦に挑み、メランションのフランス左派のポピュリズムをとり、革新的路線を選択した。これらはすべて功を奏し、特に南イタリアでの成功につながった。カレンダとレンツィの中道の同盟は、リーダー主義的、テクノクラシーの路線を採用し、新ドラギ政権を提案して、「フォルツァ・イタリア」や民主党に失望した者からの票を狙っていた。これは部分的には成功し、議会に代表者を送ることには成功しているが、目標だった二桁には到達しなかった[票数は下院のみ]。
ドラギ政権の遺産に対する未来
2022年7月21日の上院での信任投票の後、首相は下院での投票の結果を待つことなく、クイリナーレ宮に行き、辞意を表明した。その後、共和国大統領によって上下院の解散が表明され、声明にて「昨日上院でなされた投票とその方法は、政府に対する議会の支持が失われ、新たに過半数を得る見込みが乏しいことを明らかにした。これによって解散を早めることは避けられないことである」と発表した。パンデミックの危機からイタリアを救い、回復を目指して挙国一致をもたらした政府は、連立与党の主要3党の支持を失ってしまっては意味を持たないだろう。大統領セルジョ・マッタレッラは、政治的危機によるデリケートな時期であることに言及し、次期政府が誕生するまで現政府が、ロシアとウクライナの戦争による経済・社会危機(ヨーロッパとの協調のもとで、国の安全に対する関心を必要とする)や、EUの補助金を失わないようPNRR計画の遂行、そしていまだ完全に克服したとは言えないパンデミックに対する対処など、現在の問題に対応することを強調している。
実際、前政権は惰性的に進んできたわけではない。その政治的活動は、EUの支援のもとにイタリアを「再興」する道筋を示すことに成功してきた。2022年の経済成長は、900~1000万ユーロを、新政府が予算法案に介入する前に、エネルギー危機による価格高騰に対応する資金として使用できるよう残した。おそらく予算法案こそが、新しい政府にとっての真の実験場となるだろう。挙国一致を経験したことで、各政党が公共の福祉のために過激化を避けるようになり、調停の途を見出せるよう節度ある行動をとることを願いたい。
[原田亜希子訳]
宮崎駿監督の映画『風立ちぬ』
“Si alza il vento”, un film di Hayao Miyazaki
Giandomenico Mucci S.I.
ジャンドメニコ・ムッチ神父
宮崎駿の最高傑作の一つとも言われる
アニメーション映画、『風立ちぬ』。
2013年に公開されたものですが、
そのテーマは深く、難解とすら言われました。
随所にちりばめられたメッセージ、
時代背景、思想を、わかりやすく解説。
一度見たことがある人でも、
改めて見たいと思わせてくれます。
La Civiltà Cattolica 2015, I, 88-90
大正時代(1912-26)、一人の田舎の少年が、飛行機の設計者となることを決意する。彼は白い雲のたなびく青い空を、風を切って飛び回ることができる飛行機をつくることを夢見た。成長した青年は東京で勉強し、日本の軍事会社の一級のエンジニアとなる。そしてその才能によって、航空業界の歴史に名を残すことになる飛行機をつくった。それが通称零戦の名で知られる零式艦上戦闘機であり、1940年から3年間、世界でもっとも優れた戦闘機であった。
夢と現実のはざまで
2013年のヴェネツィア映画祭で上映された『風立ちぬ』は、2時間以上にわたる長編アニメーション映画である。監督の宮崎駿氏は名作を輩出したあのスタジオジブリの創設メンバーであり、当時72歳だった彼は、この作品を彼の最後の長編アニメ作品と発表した。この作品には彼の人として、そして芸術家としてのあこがれが詰まっている。そしてそれが実在した堀越二郎という人物の伝記として、飛行機の設計に関わる技術的データの点では非常に事実に忠実でありながらも、風と空想にたなびく色彩鮮やかなさまざまなイメージの創造の点では自由な形で表現されているのだ。
二郎が幼少期から青年期を過ごした時代はまさに停滞期である。1923年の関東大震災、世界恐慌、失業、貧困と結核、ファシズム、言論の自由の抑圧、そして相次ぐ戦争の時代であった。二郎が飛行機の設計にいそしむ中、日本は破滅へと向かっていた。
監督は、この映画を通じて、大正から昭和の初期にかけての日本の青々とした素晴らしい景色を表現したかったと述べている。当時空はまだ澄み渡り、小川の水は透明で、今のように産業廃棄物がそこかしこに重ねられているようなこともなかった。ある意味、主人公の半生を描く中で、映画は三つの異なるイメージを織りなしている。
まずは夢の人生だ。小さい頃から二郎は飛ぶことを夢見ていた。布団の中で寝ている時にも、彼は鳥のような翼を持った不思議なエンジンのついた飛行機に乗って家の屋根の上を飛び回っている。雲の間を飛ぶうちに、彼は恐ろしいものを目にする。それは爆弾を詰め込んだ巨大な飛行船であり、それが空を暗くすると、爆弾を落としていくのだ。夢の中で二郎はジャンニ・カプローニ伯爵に出会う。彼はイタリアの航空機の誕生以来、世界中で一躍有名となったイタリア人設計師だ。伯爵は二郎の未来の技術の進歩に対する夢を膨らませると同時に、この「日本の少年」に飛行機が死を招く運命を帯びていることをも思い出させている。
日々の仕事の様子は、簡潔に描かれているが、ドイツへの視察など、ところどころ鮮明な情報もみられる。二郎が同僚たちとドイツの飛行機を見に行った際には、当時のドイツのスパイシステムとの衝突は避けられず、日本の客人の視察を歓迎するのではなく、むしろ妨害しようとしている様子も描かれている。この危険な状況を際立たせる真っ黒なシーンは20年代のドイツの表現主義映画に対するオマージュともみなせるかもしれない。
もっともとんでもない出来事
この作品では避けられない戦争の様子は、覚えておかなければいけないが、決して褒められるものではない何かとして遠くから映し出されている。日本ではこの映画は物議をかもし、監督は大日本帝国への懐古主義者として批判された。
これほど間違ったことはない。宮崎監督は、戦闘機の知識のみならず、第二次世界大戦時に使用されていたあらゆるタイプの武器に関する知識を持っているが、この戦争での犠牲者の数が2千万人以上にも及ぶことも記憶にとどめている。間違いなく、この戦争は人類史上もっともとんでもない出来事であったのだ。
日常生活のシーンは、素朴で落ち着いたシーンから構成されている。二郎は、光る知性を備え、苦痛を感じるほどに目標に向かって集中し、上品で優美であるが、内気でもある。人づきあいがよく、教養もあり、時にやさしさが爆発することもある。美しく、そして恐ろしく描かれた地震のシーンでは、傷ついた女性を助け、彼女を肩に担いで家まで送っていく。その傷ついた女性の脇には、菜穂子がいる。彼女は美しく陽気な女の子であり、その10年後に再び二郎に出会い、恋に落ちるのだ。この二人の間に生まれた物語は感情的であり、無邪気なものである。
菜穂子は絵を描くことが好きな少女であり、そして結核を患っていた。離れて暮らすことができなかった二人は、非常に魅力的な結婚式を家で行い、結婚する。彼女が寝ている時、彼は彼女の右手を握った。しかし夜は働かなければならなかったために、彼は左手だけで定規を使える術を身に付けていく。彼女にとってよくないとはいえ、彼は煙草を吸い続けた。彼女はその美しさがしおれ始める前に、山の上の療養所に入院する。菜穂子の病気や、二郎との別れのシーンでは、トーマス・マンの小説『魔の山』が反響する。
この映画のもっとも特別な点は、風の存在である。それは目に見えることはないが、さまざまな瞬間に感じられる。単に二郎が小さい頃から大人になっても常に飛ぶことを夢見ていたということからだけではなく、髪の毛やこうもり傘、その他のものが飛ぶことによって常に感じることができる。まるで風こそがこの映画の真の主人公のようである。菜穂子との最初の出会いでは、風がまるで愛の伝達者として現れ、菜穂子が風で飛ばされた二郎の帽子をつかむ。またある時には、それぞれのバルコニーから投げた紙飛行機が二人の間を飛び交い、甘い愛のフレーズを思わせるのだ。
[原田亜希子訳]