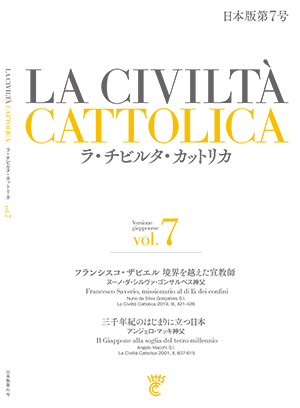La Civiltà Cattolica
日本版
(公財)角川文化振興財団バチカンプロジェクトから刊行!
ローマで発行された最古のカトリックジャーナルが史上初、日本版で刊行されました。
日本版7号
フランシスコ・ザビエル
境界を越えた宣教師
Francesco Saverio, missionario al di là dei confini
Nuno da Silva Gonçalves S.I.
ヌーノ・ダ・シルヴァ・ゴンサルベス神父
日本に初めてキリスト教を伝えたとして有名なフランシスコ・ザビエル。
その想いや、日本人への理解などが、多くの手紙などによって残されています。
インド、マカオ、そして日本や中国といった、当時の辺境の地への宣教に命を懸けた、
イエズス会の宣教師たち。
改めてその熱心さ、知見の深さに敬意を表します。
La Civiltà Cattolica 2019, III, 421-426
はじめに
1970年11月29日のマニラでの説教にて、教皇パウルス6世は次のように述べている。「私はローマからこれほど遠い国にまで来ようとは決して思わなかったことでしょう。もし私がキリストとあなた方の救済という二つの根本的なことを断固として信じていなかったとしたら」。さらに彼はこう付け加えた。
「目的地が遠ければ遠いほど、そして私の宣教が難しければ難しいほど、それは至急必要なことなのです」1。これと同じ言葉を、聖フランシスコ・ザビエルも述べたことであろう。彼にとっても、彼を突き動かしていたものはキリストと、人々の救済であった。それゆえ彼はもっとも遠く、そしてもっとも難しい目的地こそ必要であるということに恐れを感じることはなかった。彼は熱意をもって、インドや、マラッカ、モルッカ諸島、そして日本に福音を伝えたのであり、最後の宣教活動の地として夢見ていた中国に入る直前に彼を襲った死の瞬間まで、その活動を続けたのだ。
ザビエルはまず第一に、自分自身を神の道具と感じていた。それゆえ彼は次のように書いている。「我々の主、イエス・キリストが彼の信仰を異教徒たちの中に確立するために私というちっぽけな道具を使う恩恵を私に授けてくれることを信じています」2。また同時に、彼はこの「ちっぽけな道具」がポルトガル王ジョアン3世の要請のもと、聖イグナチオ・デ・ロヨラによって宣教に派遣されることを知っていた。ザビエルはジョアン3世と親密な関係を築き、王に彼が直面しなければならなかった障害について知らせたり、王から受けた援助に対する感謝を伝えたりしている。
実際、フランシスコ・ザビエルはシモン・ロドリゲスとともにジョアン3世の要請を受け、ポルトガルに送られた。ジョアン3世はインドに福音を伝えるために宣教師を送ることをもっとも求めていたポルトガルの君主の一人である。ザビエルとロドリゲスは1540年にリスボンに到着したが、ザビエルが1541年に東に向けて出発したのに対して、ロドリゲスはポルトガルにとどまり、そこでイエズス会の初代ポルトガル管区長となり、後進の若きイエズス会士の教育に努めた。これらのイエズス会士の多くが後に東方のみならず、アメリカ、アフリカへと宣教に派遣されることになる。例えば1549年、ザビエルが日本に到着したのと同じ年に、ブラジルにはマヌエル・ダ・ノブレガ神父ら6人のイエズス会士が派遣されている。これは新世界に対するイエズス会初の宣教活動であった。
聖フランシスコ・ザビエルの宣教の精神
フランシスコ・ザビエルには、常により大きな実りを得るために進んで遠くへ行くことを求める宣教師像を見出すことができる。このより大きな奉仕を求める態度は、「実を結ぶ」「無限の実を結ぶ」「聖なる教会の境界を広げる」「我々の主に奉仕を行う」「我々の聖なる信仰を増やす」「我々の主、イエス・キリストの法を増やす」といったさまざまな表現の中に表れている。
彼がこれらの表現を使った状況を詳しくみていこう。これらの言葉はまさしく霊操のもとに育成された人物によるものである。
1541年、ゴアに出発する直前のリスボンで、ザビエルはイグナチオに次のように書いている。「今週インドに向けて出発します。現地に長年いた人々が私たちに伝えているように、人々を改宗させるためにかの地でなされている努力が実を結ぶよう神に願いましょう」3。
1545年にはコーチから、リスボンにとどまったシモン・ロドリゲスにもっと宣教師を送るよう求める手紙を書いている。その理由として彼はこう説明した。「多くの人をインドに送ってください。なぜなら彼らは母なる教会の境界をさらに広げることができるでしょうから」4と。
しかしザビエルの教会の境界を広げようとする想いは、インドやマラッカ、モルッカ諸島だけにとどまるものではなかった。彼の熱意は日本と中国に対してさらに強く向けられていた。それゆえ、1548年に彼はこう書いている。「ポルトガル人の商人たちの中で信頼できる者たちが、最近発見された大きな島に関する知らせをもたらしてくれました。それは日本というところで、彼らが思うには、そこでは我々の信仰を増やす上でインドの地よりもより大きな成果を得られるだろうというのです。なぜなら彼らは知的欲求にあふれているからであり、それはインドの異教徒には見られないことだからです。[...中略...]日本からやってくるポルトガル人の商人はみな、もし私がそこに行けば、彼らは思慮深い人々なので、インドの異教徒たちに対して働きかけるよりも我々の主である神に奉仕できるであろうと言います。私の魂が感じているところでは、私自身、もしくはイエズス会の誰かが、2年以内に日本に行くと思います。それがたとえ、嵐や、道中の海で略奪を行う中国人の海賊によって、多くの船が失われるほどの多くの危険を伴う旅であったとしても」5。
魂で感じたことに耳を傾けることによって、ザビエルは日本に行くことを決意した。1549年、彼はこう聖イグナチオに提案している。「私はかの地に行くことを精神の喜びをもって決意5しました。私は、かの地の多くの人々の中で、私たちイエズス会のメンバーが生涯の間にもたらせる成果を、彼ら自身のおかげで永遠のものにすることができるであろうと感じています」6。この言葉は、日本のキリスト教が宣教師の追放とキリスト教徒に対する迫害の後も、外部との接触のないままに生き残っていたことを考えるならば、真の予言とも言えるものであろう。まさにザビエルの言葉を借りるならば、「彼ら自身のおかげで」永遠のものとなったのである。
日本に到着してからも当初は、ザビエルはもっと先に進めるであろうと確信し、次のように言っている。「発見された土地の中でここ以上に多くの実りを得られるであろう場所はないでしょう。日本や中国以外に、イエズス会士が成果を永遠のものにすることができる場所など」7と。
常に宣教活動の境界を広げることを求め、そしてますます中国の重要性を感じていたザビエルは、1552年に中国へ訪れることを計画した。実際、その時にヨーロッパのイエズス会士たちに彼は次のように書いている。「1552年に、私は中国の王が君臨するところへと行くでしょう。かの地こそ我々の主、イエス・キリストの法を増やすことができる地であるのですから。そしてもし彼らが神の法を受け入れれば、それはまさに日本で彼らが信じている宗派に対する信頼を失わせるうえでも大きな助けとなるでしょう」8。
フランシスコ・ザビエルの考える宣教師の資質
ザビエルは新しい歩みをはじめるだけでなく、最高のオーガナイザーでもあった。ヨーロッパからやってきた、もしくは現地でリクルートされたイエズス会士は、新しいキリスト教徒のコミュニティーに振り分けられ、彼らがその地での任務を果たせるよう、ザビエルは彼らに細かい指示を与えた。この点において、ザビエルが宣教師に必要な資質について述べたところを思い出してみよう。
理想的な宣教師像は当然どこに行くかによって変わる。インドには、彼が1545年にイグナチオに書いているところによると、「精神力と同時に、肉体的力」が必要とされた。宣教活動は祈りを教えることや、村々を尋ね、子供たちに洗礼を施すことを中心としていたからである。そのため、それほど多くの知識を必要とはしていなかった9。
1546年、ザビエルはヨーロッパのイエズス会士たちに、そこで死ぬ覚悟で現地の人々のところに来る方が、知識よりも重要であることを説いている10。1549年、彼はその点を確信しており、イグナチオへの手紙の中で宣教師たちに不可欠な資質について次のように列挙している。「改宗のために異教徒のもとへ行く者には、それほど多くの知識は必要ではありませんが、多くの徳を持っている必要があります。すなわち、従順さ、つつましさ、粘り強さ、忍耐強さ、隣人への愛、そして罪を犯す可能性のある多くの機会に対して無垢であることです」11。
同じ年、ザビエルはシモン・ロドリゲス神父にも東洋に来るよう、そしてあまり若すぎるイエズス会士を連れてこないよう手紙を書いており、さらにこう付け加えている。「ここでは30歳以上、40歳までの神父を必要としています。そしてつつましさ、素直さ、忍耐、そして特に純粋さというすべての美徳を兼ねそなえた人物を必要としています」12。
ゴアやコーチのためには、告解を聞く能力にたけていて、霊操を与えることができるイエズス会士を求めていた13。そして東洋のポルトガル人の要塞都市には、現地のさまざまな集団に教理を教える能力のある説教師を求めた14。
一方で日本や中国に派遣するべき宣教師に関しては、ザビエルはある特別な能力を求めている。これら二つの国に送られる宣教師は、かなりの知的素養を持つ人物でなければならないというのだ。それは「中国人や日本人のように知的な異教徒たちがする多くの質問に答えるため」15であった。
日本に派遣するべき宣教師には、特に迫害を経験したことのある人を勧めており、さらにこう付け加えている。「良き哲学者が望ましいし、また討論の中で日本人の矛盾を突くことができる優れた理論家も悪くないでしょう。さらに天体のことに関して知っていなければなりません。というのも、日本人は天体の動き、日蝕、月の満ち欠けを知ることや、雨水がどこからきているのか、雪やひょう、雷、稲光、彗星、その他の自然現象について知ることにたいそう喜びを感じるのです」16。
宣教師の資質に関して1552年に出した勧めのもとに、ザビエルは東洋で過ごした期間、常にそうしていたように、多くの道を開き、それは後の多くのイエズス会士によって引き継がれることとなった。実際、彼の活動は、さまざまな場所、時にはもっと遠いところを訪れ、ザビエルをモデルとした次世代の宣教師たちによっても引き継がれている。
この急速な拡大は、イエズス会士やキリスト教をゴア、マラバール、日本、中国に定着させ、そして宣教師たち、とくに東洋へ渡った宣教師たちは多くの世代のイエズス会士たちに魅力的に映った。それこそまさに1540年に教皇パウルス3世によって承認されたイエズス会の会則の中ですでに定められていたことである。すなわち世界のどこにでも喜んで派遣されること、「インドと呼ばれる地域にいる異教徒たち」17のもとに派遣されることを喜んで受け入れることだ。
この心持ちは、1583年から1770年にかけて書かれた16000通にも及ぶ手紙の中によく示されている。これらの手紙は現在ローマのイエズス会文書館に保管されているが、この中でイエズス会士たちは総長に自分を宣教に派遣してくれるよう求めているのだ。
1552年、フランシスコ・ザビエルが亡くなった年に、イタ8リアのマチェラータではマテオ・リッチが誕生した。彼は北京に初めて居を構えたイエズス会士である。まさにこれは1552年の段階では統合できなかった大きな出来事である。ザビエルが計画し、中国に到達できると思っていた矢先の死によって中断しなければならなくなった宣教の旅を、その約50年後の1601年に、リッチがついに成し遂げたのだ。
[原田亜希子訳]
2 聖フランシスコ・ザビエル、『ローマ在住イエズス会士への手紙』1542年9月20日
inID.,Dalleterredovesorgeilsole.Lettereedocumentidall’Oriente1535-1552,Roma,CittàNuova,2002,91s.
3 ザビエル『イグナチオ・デ・ロヨラ神父とジョヴァンニ・コドゥリ神父への手紙』(リスボン、1541年3月18日)inivi,75.
4 ザビエル『シモン・ロドリゲス神父への手紙』(コーチ、1545年1月27日)inivi,172.
5 ザビエル『ローマ在住イエズス会士への手紙』(コーチ、1548年1月20日)inivi,208-210.
6 ザビエル『イグナチウス・ロヨラ神父への手紙』(コーチ、1549年1月12日)inivi,239.
7 ザビエル『パオロ神父への手紙』(鹿児島、1549年11月5日)inivi,343.
8 ザビエル『ヨーロッパ在住のイエズス会士への手紙』(コーチ、1552年1月29日)inivi,372s.
9 ザビエル『イグナチウス・ロヨラ神父への手紙』(コーチ、1545年1月27日)inivi,163参照。
10 ザビエル『ヨーロッパ在住のイエズス会士への手紙』(アンボイナ、1546年5月10日)inivi,191参照。
11 ザビエル『イグナチウス・ロヨラ神父への手紙』(コーチ、1549年1月14日)inivi,245.
12 ザビエル『シモン・ロドリゲス神父への手紙』(コーチ、1549年2月2日)inivi,272.
13 ザビエル『イグナチウス・ロヨラ神父への手紙』(コーチ、1545年1月27日)inivi,164参照。
14 ザビエル『シモン・ロドリゲス神父への手紙』(コーチ、1548年1月20日)inivi,226参照。
15 ザビエル『ポルトガル王ジョアン3世への手紙』(ゴア、1552年4月8日)inivi,419.
16 ザビエル『イグナチウス・ロヨラ神父への手紙』(ゴア、1552年4月9日)inivi,422s.17イエズス会会則、第3条
三千年紀のはじまりに立つ日本
Il Giappone alla soglia del terzo millennio
Angelo Macchi S.I.
アンジェロ・マッキ神父
2001年に書かれた記事ですが、
第二次世界大戦以後の日本が
どう形成されてきたかを、
冷静な視点で辿っています。
決していままでも平坦ではなかった道のり。
敬意、感受性、希望、
という3つの言葉をキーワードに解説、
しかしながら、円安、物価高、
そして日本の最後の砦とも言える治安までもが
脅かされている昨今、
20年前に世界は日本をどう見ていたのかを振り返ります。
La Civiltà Cattolica 2001, II, 607-615
日本の歴史は、第二次世界大戦(1939‒45)に敗北した後、大きな転換を迎えた。真珠湾に停泊していたアメリカ艦隊への奇襲攻撃(1941年12月7日)が合衆国を参戦に追いやったが、同国こそヨーロッパにおいても太平洋においても勝利に決定的な役割を果たした。そして、日本の抵抗は戦慄すべき新兵器により打ち負かされた。1945年8月6日と9日に広島と長崎にそれぞれ投下された原子爆弾である。1945年9月、日本は降伏し停戦協定を結んだ。日本政府が自由主義と民主主義の価値観に基づいた国政改革をなすまで、占領軍として合衆国軍が日本に駐留することが認められた。1947年5月3日から施行された新憲法は、議会制民主主義に基づく君主国として日本を形作っている。天皇の地位は国民の意志に基づくものであると宣言することで、現人神としての天皇を放棄したのだ。また、国家間の対立を解決する手段としての戦争を永久に否定し、全国民の基本的人権を保障したのである。
国制は権力分立の原則に基づいている。天皇は「日本国の象徴であり日本国民統合の象徴であって」、際立って国家を代表し象徴する機能を果たしている。国権の最高機関は直接普通選挙により選出される国会であり、参議院(上院)と衆議院(下院)から成る。国会は立法権を行使し、政府の活動に政治的統制を効かせている。執行権は首相が長となる内閣に委ねられるが、国会が首相に信認を与える必要があり、国会はこれを撤回することができるのである。司法制度は英米法の影響を受けながら大陸法に基づいている。
新たな日本は憲法により戦争と軍事力を否定しているが、自衛権は排除されていない。このため、合衆国より物心両面での支援を受けている約25万人の自衛隊を有しており、合衆国は独自の軍事基地を日本に維持している。1992年と1994年に国会は、2000人の隊員を国連平和維持活動に派遣し、有事に巻き込まれた国民を救出するための自衛隊の海外派遣を認める二つの法律を決議した。
日本は1951年9月に合衆国と講和条約を結ぶと、1952年4月28日、合衆国が1972年に返還することになる沖縄諸島を除けば、その領土における完全な主権を回復した。原子爆弾がもたらした破壊により人々の間に広まった反米感情にもかかわらず、日本政府は、日本を合衆国に次ぐ世界第二位の経済大国とすることに資した、長期にわたる包括的な同盟関係を合衆国政府との間に築いた。
経済状況
日本は資源に乏しい。原材料を輸入し高度な技術による完成品を輸出してきた日本の製造業は、海外に販売網を張り巡らせてきた銀行と製造業が結合した金融・産業複合体が中心となっている。国際市場における成功をもたらした力は、高度な科学技術だけでなく、無数の中小企業との協働にも基づいている。こうした中小企業では、脆弱な労働組合により人件費や諸費用の顕著な抑制が容認されている。日本製品への際立った高い評価は国際経済における多額の投資策を容易にしており、現在、日本は世界でも有数の金融力を有している。鉱物資源およびエネルギー資源に頼ることができないので(ただし銅鉱床は無数にあるが)、日本は電気エネルギーを生産するために、原子力分野に力を入れるのと同時に大規模な化石燃料の輸入を行っている。鉄鋼業(これもまた原料の輸入に大きく依存している)は、第二次世界大戦後に再編され強化されたが、造船(世界的に主要な地位を占めている)と自動車分野での活動を活発にしてきた。後者に関しては80年代、日本は合衆国の長く続いていた国際的優位に追いつくどころかほとんど追い越さんとしていた。だが、成長著しい分野は電子機器(パソコンや通信機器)であり、精密機器(光学機器、工作機械、ハイファイ音響、航空機器)に関して最高品質の製品が追求されている。また、肥料とプラスチック素材に関する基礎化学で存在感を増しており、繊維業(人造繊維)、製紙業、食品産業(輸出の多くは水産加工品)でも有名である。
農業は、耕地可能面積(国土の16%しかない)が極めて細分化されていながら肥料と品種改良により食糧需要の三分の二を賄っているが、長期的には国民所得に占める割合が低下している(3%)。最大の作物は常にコメであり年間約1500万トン生産されるものの、国内需要を賄うのに十分ではなく、日本は大量のコメを輸入している。他に食品生産の中でも代表的であるのは、穀類(小麦と大麦)、ジャガイモなど野菜類だ。また、茶と柑橘類の生産もよく知られている。養蚕が盛んであり(中国に次いで世界第二位)、絹産業を支えている。漁業も非常に重要であり、日本は世界でも首位を占めている。最新の船舶を備え、あらゆる海域で活動し、大規模な輸出を行っている。日本は天然・養殖の真珠生産でも主要国である。森林の被覆は国土のおよそ三分の二であり、木材生産も優れている。
現在の人口は1億2616万人に達している。人口動態は自然増が近年ではゼロに近い状態が続いていることが特徴的だ(1992年より1997年まで0.3%を超えることなく頭打ちとなっている)。
平均寿命は世界でももっとも高い状態にある(男性は77歳、女性12は84歳)。1997年の統計資料によれば、生産年齢人口は6686万人であり、その41%が女性である。一人当たりの国内総生産は4万940ドルに達している(合衆国は2万8020ドル、イタリアは1万9880ドルである)1。
過去50年間を通じて日本にこれほどの大きな成果をもたらした道のりは直線的ではなく、景気後退および他地域での金融危機による影響や国内事情による浮沈を伴うものであった。例えば80年代、日本経済は実に強固な成長を記録した。国内消費を抑え、海外市場、とりわけ合衆国で日本製品の競争力を高めるための税制と財政政策を通じて政府がこれを支えたのである。だが、90年代の初め、合衆国での深刻な景気後退が即座に日本経済へ波及すると、工業生産は4.5%低下し、年間GDP成長率は勢いを失い0.8%を記録した。80年代の日本政府の経済政策は輸出を拡大させ輸入を減らす方向にあり、貿易収支の顕著な黒字をもたらしていた。1986年には820億ドルに達していた。合衆国は、当局が「保護貿易主義」と呼ぶところの政策について、日本政府を繰り返し厳しく批判した。1986年、(円がドルに対して強くなっていたにもかかわらず)輸入が2.4%の増加に対し輸出が19%も拡大していたことは明白であり否定できなかったので、日本政府は、輸入品への関税を下げ輸入手続きを簡素化することで、輸入を拡大するための「行動計画」を打ち出した。こうした措置が功を奏し、合衆国よりは少ないにしても西欧やアジア諸国からの輸入は増大した。1987年、日本の輸入は18%の増大を示したが、輸出もまた10%増えていた。このため、貿易収支の黒字は高い水準を維持していた(790億ドル)。
90年代初頭に始まった不況は10年にわたり続き、まさしく景気後退の特徴を示している。例外的な要因(金利の引き下げと公共事業への多大な資金注入)によりGDPが3.7%の成長を示した1995年を除いて年間成長率は1%程度であり、1997年にはGDPが2.5%減少してすらいる。失業率は5.4%まで上昇したが、これは1953年以来最大である。そして、金融危機が状況をさらに悪化させた。1995年に最初の危機が生じ、大和銀行を巻き込んだ。大和銀行は、ニューヨーク支店の職員がなした債権の不正売買により10億ドルを超える損失を負っていた。彼は累積した損失を隠ぺいするために書類を偽造していたのである。合衆国政府は、大和銀行の米国支店の閉鎖を命じた。続く数年間のうちに、いくつかの金融機関が破綻し破産宣告を迫られた。こうした破産の社会的影響を緩和し、破産が連鎖することを防ぐために、日本銀行は5830億ドルを支出したことを明らかにしている。政府当局は、暗に軽率であることを認めながらも、銀行への介入と監視を強めるための法的措置の導入を急いだ。他方、堅実な大銀行は互いに合併し、困難な状況にある中小の銀行を吸収する機会を得たのであった。
外交政策
合衆国との特別な関係のことを差し引けば、日本の外交政策は東アジア・東南アジアの安定の維持を第一の目標としている。実際に日本は、経済にとって重要な原料輸入を含み、貿易の三分の一を広くアジアに依存している。中国とは、1978年に平和友好条約を結んだにもかかわらず、80年代の終わりより関係が若干悪化している。これは日本が合衆国の切迫した求めを部分的に受け入れ、国防費の増額を決定したことによる。中国の人々には、かつての軍国主義を思わせる姿勢として映ったのである。天安門広場において抗議する若者たちが軍により虐殺されたことは、日本を外交関係の停止へと追いやった。しかし、3年後には再開され、1994年には中国が日本の最大の貿易相手国となるほどに関係は改善した。
韓国との関係は本質的には良好であっても、1992年まで若干冷えていた。この年に日本の宮澤首相は、公式にソウルを訪問し、第二次世界大戦中の日本軍が韓国の女性を虐げたことを公的に謝罪した。とはいえ、韓国政府が求める犠牲者のための賠償については手を付けていない。また、1999年の夏には、日本と韓国は初めて合同での海上訓練を行った。
北朝鮮とは依然として公式な外交関係を結んでいないが、日本は中国に対する共通の利害を有している。北朝鮮が地域の平和と安定に好意的であるという保証を得ると、日本政府はミサイルおよび核開発計画の凍結を条件として、軽水炉建設のために40億ドルの借款を約束した。
ソ連とは1956年に国交を回復した。しかし、ロシアが占拠する諸島についての対立が未解決であるため、平和条約は結ばれていない。ロシアは、クリル列島を委ねるとしたヤルタ協定(1945年)に基づき領有権を主張するが、日本は、合衆国の支持を受け、問題の諸島はクリル列島に属していないとして返還を求めている。
国内政治と政党
第二次世界大戦における敗北の後、政党政治は二つの極の間にあって活力を取り戻した。親米志向の自由-保守主義と、社会主義である。両者は派閥ないし党派として権力闘争を繰り広げ、激しく対立していた。1955年の選挙を転機として、自由民主党が誕生することで保守勢力(自由主義、民主主義、国民自由主義)は統一された。社会主義勢力もまた、急進派と穏健派に分裂していたが、日本社会党として一つになった。結果として1955年の選挙は自由民主党を第一党とすることになり、衆議院では社会主義勢力の158議席に対し絶対多数の298議席を得ることとなった。共産党は常に大衆的な支持を得られず、国会ではわずかな議席を占めるばかりであった。選挙での敗北は社会党を苦しめ、1960年には再び分裂し(日本社会党と民主社会党)、1993年まで鎬を削った。他方、自由民主党の勝利は長期の優位のはじまりとなり、1993年まで絶えることなく第一党であり続けた。
政府の行動は国家の経済および金融の動向について良い結果であれ悪い結果であれ責任を負わねばならないという尺度からすれば、自由民主党による諸政権が日本の奇跡的発展に貢献してきたことを認めざるを得ない。しかし、自民党政権が権力と与党内での闘争において示してきたことを思えば、日本が成し遂げた進歩はまさに驚くべきものがある。1955年から今日まで21もの政権が成立してきたが、平均すると約2年しか続いていない。与党内の政局と派閥間の権力闘争が、各派閥に閣僚ポストを配分するべく政権の再編を決定し、常に新たな党派を形成させてきたのである。この文脈において留意されるべき政党が、新生党、日本新党、新党さきがけ、そして公明党である。公明党は60年代に結成され、仏教の在家信徒が組織した創価学会の政治運動を代表している。
首相や閣僚を巻き込んだスキャンダルによる政治危機も生じてきた。とりわけ国際的な影響も与えたのが田中角榮(1972年から1974年にかけて首相を務めた)であり、彼は合衆国からのロッキード社製航空機の購入について便宜を図った汚職により告発され、1976年に逮捕された。自由民主党の長期の優位は、単独であれ連立であれ、常に最大多数派として政権を担ってきたことによる。
こうした伝統の破壊が1993年に起きた。政権の座は日本新党の党首、細川護熙に明け渡され、彼は独自性の強かった野党7党との連立政権を成立させたのである。細川は戦後初めて首相となったカトリック教徒であった。社会党の党首、村山富市に政権を委ねる約束により、1994年にはさらなる政界再編がなされた。これはおよそ50年ぶりの出来事であった。村山は自民党より多数の閣僚を受け入れることで連立政権を成立させたが、対立してきた二大政党が協同したことは、大きな改革を必要とする構造危機の兆しであった。実際、政権を安定させかつ中小政党の代表性も担保するために、選挙制度改革がなされた。こうして下院の議席は500に縮減された。このうち300は多数代表制により、200は比例代表制によって選出されることになった。この改革を経て1996年1月に村山首相は退陣し、与党の座は自由民主党の手に再びしっかりと握られた。まず橋本龍太郎が首相となり(1996年1月‒1998年7月)、次いで小渕恵三が就任した(1998年7月‒2000年4月)。小渕が脳卒中に倒れたため政権は森喜朗へ移譲され、彼は今年2001年の4月までこれを保持した。自由民主党から野党への政権移行により生じた1994年の変化は、過去へ戻ることですぐに終わった。対立する二党ないし諸政党の間での政権交代という可能性は、自由民主党が日本社会に根付いていることから現実的ではないとしても、この支配的な政党の内部に世代交代を見出す者もいる。
この種の仮説はつい最近、森総理の辞任を機に示された。というのも、後継について、派閥の権力構造が選出をなすよりも前に、4人の候補者がテレビ討論により公の場で議論を戦わせたのである。そして、合衆国の予備選にも似た顚末を迎えた。候補者のうち3名は旧い体制を代表していたが、4人目の小泉純一郎は、過去40年間にわたって自民党と同一視されてきた慣習、経済理論、綱領やふるまいを打破する破壊者を演じたのであった。政敵を打ちのめした小泉の言葉をいくつか引用しよう。10年間日本を苦しめてきた経済危機について彼は「構造改革なくして景気回復なし」、「これまでのシステムとルールはもはや通用しない」、(旧い体制が正当化してきたことを切って捨て)「赤字を垂れ流している事業は失敗だと政府は認めなければならない」、「税制を改革しなければならない」と語った。だが、視聴者にとりもっとも印象的であったのは、郵政民営化であった。ほとんど0%の利率により預金者に報いることがないために政府は多大な利益を得ていたが、それは小泉によれば投資と消費を低下させているのであった。
テレビ討論会は小泉の爆発的な人気を呼び起こし、自民党に波瀾をもたらした。4月24日火曜日、執行部は森の後継者を選出しなければならなかったが、党の旧い有力者たちは及び腰であった。というのも、小泉は好ましくなかったが世論調査では過半数が彼を支持しており、他方、他の候補者の筆頭であった橋本元総理は20%しか支持を獲得していなかったのだ。党中央に対し反発する傾向のあった地方支部は小泉を支持しており、実際に彼へ票を投じた。総理大臣に就任すると、これまでになく大胆な内閣を組織した。5人の女性閣僚が誕生したが、田中角栄元首相の娘、田中眞紀子は女性として初めて外務大臣に就任した。小泉の所信表明演説は歴代総理のものとは異なり実に雄弁であり、簡潔な言葉と明快な内容により人々へ直接訴えかけることのできるものであった。
彼が打ち出した政策は、その新しさと継続性がともに人々の関心を引き寄せた。新しさについて言えば、首相の選出を議会から直接選挙へと移行する首相公選制や、「自衛隊」を他国と同様に、まさしく地域の安全保障に貢献できる軍隊とする提案が目を引いた。しかしこうした提案は、将来起こり得る事態について国民の不安をかきたてた。継続性としては、「日本の繁栄の基礎としてある」合衆国との特別な関係がある。新たな首相の談話への東京市場の好意的反応は、日本政治の新たな方向性に対する実業界の承認として解釈された。最新の世論調査では支持率が84%に達した。現在、選挙による政権の信認ないし不信任が待たれているが、来月7月には上院の半数改選とおそらく下院総選挙が行われるだろう。
[林皓一訳]