蛇笏賞・迢空賞
-
2025.04.18更新第59回「迢空賞」受賞作発表
-
2025.04.18更新第59回「蛇笏賞」受賞作発表
受賞のことば・選評
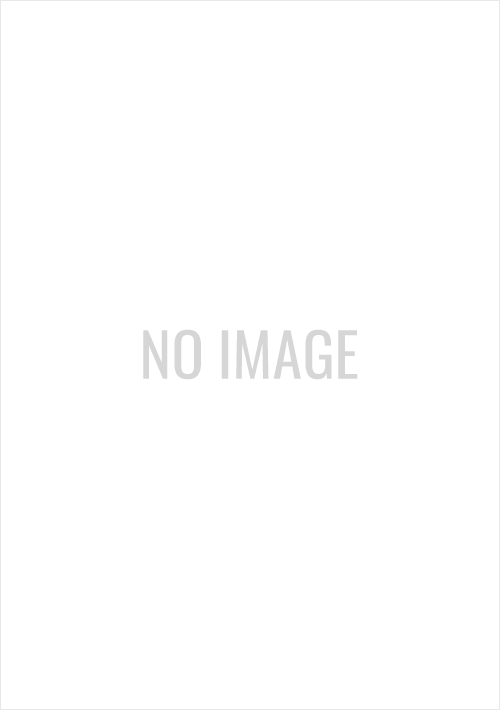
前 登志夫(まえ としお)
1926年、奈良県吉野郡下市町に生まれる。同志社大学経済学部に入学するが、1945年に応召、大学中退。戦後、「日本未来派」「詩学」等に詩を発表。1948年、小島信一らと「新世代詩人」創刊。1951年に吉野に戻る。1956年、詩集「宇宙駅」を刊行。やがて短歌に転じ、前川佐美雄に師事。1964年、第一歌集『子午線の繭』出版。1974年、金蘭短期大学助教授に就任。歌集のほかに、エッセイ『吉野紀行』『山河慟哭』ほか。
受賞のことば
前 登志夫
ことしの吉野の花はおそかった。
四月になってから霙がふり、しばらく沫雪となったりもした。さくらの蕾は、まさに花開こうとしてそのままとまってしまった。
雷鳴が幾日か峯々をとどろかせ、そのたびに雹が降った。花ひらく前の春の嵐に、山の怒りを聴いた。それでも花の息づきのせいか、どこかやさしい山の怒りであった。
迢空賞のしらせを受けたのはそんな日であった。若い日に、柳田・折口学に親しみ、それゆえに山の人生を選んで歩むことになった私には、迢空賞はいかなる賞よりも感慨のふかいものであった。しかも、熱心に銓衡討議せられたという選者諸氏が、みな敬愛する友人であることも、直接にあつい励ましを感じる。賞という厳粛なものであるよりも、先ず、しっかりやれよ!と肩を叩かれたような気がする。
さて、私はこれからどのようにしてゆけばよろしいのか。もはや一首の歌も出てきそうにないのが実感である。いつだって私はそうしたむなしさの中にいたと思う。ただ、己れをむなしうして、存在するものの声に耳を傾けるだけである。無名のひとりの木樵として、梢をわたる風のそよぎにもいのちの閃き出るを見るだけである。
たまたまこの春、吉野の花吹雪を訪ねてこられた山本健吉氏と、花の下に憩う数日があった。先生は、西行の詩の世界のユニークな(比類のない)魅力を、さまざまに話された。それは花群の下の茶店であったり、奥千本の岩間で呟やかれた。芭蕉がついに到達出来なかった西行の詩の軽みの秘密は、容易に明せるものではあるまい。私は初心に立ちかえり、歌びとの恩寵について、敬虔な感動を味わった。己れを棄てるということの深い意味を、改めて思うのであった。
今、日本の文芸の心は、浮薄な文明の嵐と衒いの中で絶えんばかりであるように思えてくる。「春風の花を散らすと見る夢は醒めても胸のさわぐなりけり」と呟き、私達は、「夢中落花」をこもごもの感慨をもって受けとめた。
そんな日、偶然、花の下に、岡野弘彦氏夫妻が立っていた。岡野夫人 は、「一期一会」とはこのことだと言ってくださった。岡野さんのうしろのさくらの幹に、迢空折口信夫がもたれているような気がした。
選評(敬称略/50音順)
「『繩文紀』を推す」 岡野弘彦
今年の迢空賞の受賞対象となる歌集の中から一冊をということなら、私は前登志夫氏の『縄文紀』を推選する。
前氏は吉野の旧家に生れ、伝統的な風土と古風な共同体意識によって結ばれた村びとの一人として、みずから民族的な生活の具現者である。しかも他方において、吉野の風土や民族を抜き出て、広い視野と鋭い個性的思考の世界を持った現代の歌人である。
「認識によつては摑へることのできない、存在としての生の流れにかたちを与へたい」というのが氏の歌にたくした願望であるごとく、前氏の短歌は、日本の村の生活の根底を貫ぬく常民の心の実体、民俗をささえる意識下の共同意識を、古くして新らしいこの日本の詩型の上にみちびきだそうとするものである。その意図は、前歌集『霊異記』よりも、今回の『繩文紀』において、よりなめらかにより香り高く成果を結んでいるものと考える。
最近、短歌のみならず小説・戯曲作品に民俗的な世界を題材にしたものが多い。そこには、優れた作品もあるが、単に語彙や気分のみが民俗的よそおいを持ったに過ぎぬものもある。そういう中で前氏の作品は、本質的な内容と、それをとらえるための新らしい表現開発の努力を示しているものといえる。
「二歌集を支持」馬場あき子
昭和三十年第一回角川短歌賞の候補作品の中に、当時安騎野志郎といっていた前登志夫氏は、「海にきて夢違観音かなしけれ不意の方位に帆柱のいづ」の一首を提出している。これが、昭和三十九年、第一歌集『子午線の繭』に収録された時は、「海にきて夢違観音かなしけれとほきうなさかに帆柱は立ち」と秀抜な改訂が加えられ、前氏の代表作とするにふさわしい甦りをみせていた。
この間、前氏は昭和三十五年創元社刊の、新鋭歌集の中に、この改作前の歌を採録してはいない。私は、この改作に至る十年近い年月の中に、前氏の自作に対する執心の熱さをみるが、この改作のことばわさにおけるみごとな変貌は、前氏がその後、自信にみちてその「とほきうなさか」ともいうべき世界を開顕してゆく重大な前ぶれであった。前歌集『霊異記』とともに『繩文紀』は、前氏でなければありえぬ人生の軌跡と詩論が、熟い一体化を迎えた時期の、重たい結実であると思う。私はまた、前氏とは別に山田あき氏の『山河無限』に、太平洋戦争を中にした戦前・戦後という、最も苛酷な昭和史を、最も苦しく生き耐えた女人のうたを見、大切な心の歴史として高く評価していた。これは、もはや今後に生まれえない歌集である。山田氏は、よく「栄誉はあなたへ、労苦は私へ」ということばを愛して口にしていられたが、山田氏の半世紀を越える短歌への深い思いと営為は、かならずまた、報いられる場をもつものと信じている。
『繩文紀』田谷 鋭
山が鳴る幾夜はありて向つ尾根人下(お)りてくる霧踏みにつつ
郭公の来啼ける山に草薙ぎて死者の憩ひに近近と寄る
霧ふかき奥干本に憩ひけりわが残桜記すべもなからむ
いかほどの煙草を喫(の)みて死にせむか吾妻はかぞふ八百萬(やほよろず)の數
『繩文紀』のこうした作品は、詩(狭義の)の世界から歌の世界へ近づいてきた人の歩みが、次第に確かに、そして独自の響きと、素材的な多様さを持ってきたことを示している。ことに注目すべきは、「山が鳴る」「いかほどの」などの作品が示すように、歌柄の茫洋とした大きさが、伝統的な叙述の形と乖離(かいり)せず完成をみせていることである。これは史的に見ても大きなことと言ってよいと思う。
郭公の作品のように意図と表現とがいくらか分離して感じられるものもあるが、これも、たとえば残桜記の作品が持つ不明な魅力と共に、前氏という一人の作家の混沌のあらわれ、それゆえに生きいきした人間の歩みと理解さるべきであろう。難解と思われる作品にも言外の語りかけがあるのが氏の優れた特質である。
「佐藤佐太郎氏の近業」上田三四二
『佐藤佐太郎全歌集』について、私には別に認(したた)めた文字がある。推薦のためのものであるからことばは美をつくしているが、それは私のこころのままで、誇張はない。中ほど、私はこう書いた。
「佐藤氏ははやく斎藤茂吉に随順してしかも固有の作風を成し、その風姿は五十年を一貫しつつ、冬の夜の、星辰の移りのごとき見事な展開をみせている。この歌人ほど持続のうちにたゆみなく新しい歌境を拓きつづけた例も稀であろう。そして前人未発の境地はことにここ数年において著しい。」
このようにいったとき、私は『開冬』を念頭に置いているが、それに先立つ『形影』あたりから、佐藤氏の歌境 は晩年に入って、闌(た)けた。そして『開冬』にはことに、水墨画を思わせる古勁のなかに、往々、凄さが添うようになった。
五十年の歌業と言わずとも、私はこの『形影』『開冬』あたりの近業を顕わして、佐藤氏に賞をうけていただきたいと思った。もし、新歌集のみを対象にするというのであれば、『全歌集』の最後にある未刊の歌集、『天眼』の一部をもってしてことは足りるというのが私の考えであった。
言は穏当を欠くかもしれないが、私は、佐藤氏に迢空賞は不要だとしても、迢空賞は佐藤氏を必要としている、と思ってきた。成らなかった今も、そう思っている。
