蛇笏賞・迢空賞
-
2025.04.18更新第59回「迢空賞」受賞作発表
-
2025.04.18更新第59回「蛇笏賞」受賞作発表
受賞のことば・選評
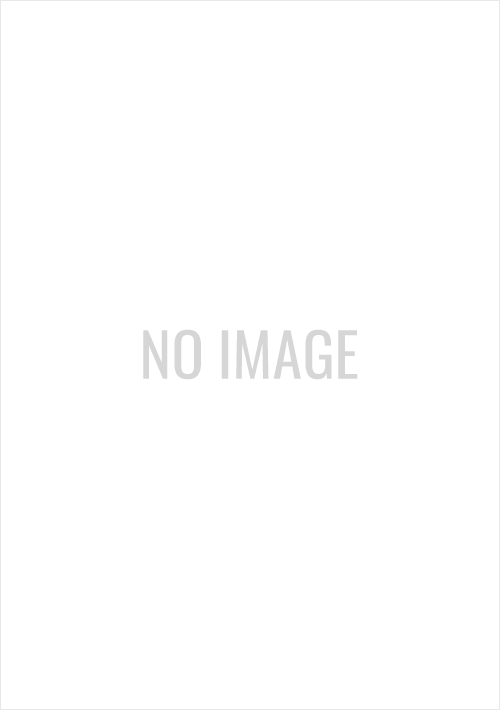
斎藤 史(さいとう ふみ)
1909年2月14日、東京市四谷区(現・新宿区)生まれ。福岡県立小倉高等女学校卒業。17歳の時、若山牧水に勧められて作歌をはじめる。1927年、「心の花」に作品を発表。1928年「アララギ」に短期間入会。1931年、前川佐美雄、石川信夫らと「短歌作品」を創刊。1934年、前川佐美雄創刊の「日本歌人」に参加。1936年、ニ・ニ六事件。父、斎藤瀏、事件に連座。1939年4月、父、瀏を主宰に「短歌人」創刊。1940年、「新風十人」に参加。同年、第一歌集『魚歌』、第二歌集『暦年』刊行。1945年、長野県安曇野に疎開。1953年、『うたのゆくへ』が日本歌人クラブ第一回推薦集となる(現・日本歌人クラブ賞)。歌集に、『朱天』『うたのゆくへ』『風に燃す』ほか。
受賞のことば
「賞をいただく」 斎藤 史
御知らせの電話をいただいたのは、春の風邪をひいたのかしら――という夕方で、背中をさむ気が絶えずかけ上り、どうにも起きているのが苦しいときであった。受話機の向うの秋山編集長さんの声が、よその世界からのように、はるかにかすかに聞えてくる。――どうも電話が遠くて――と言った。
賞というものには御縁のない人間なので、いちばんおどろいたのは、本人のわたくしだったろうと思う。
おどろいたあげくに、ぶっきらぼうな御返事をした。「御ことわりする理由もありませんし――重たいいろいろなことが無ければ、御受けします」
わたくしとしては本当で、素直な返答のつもりである。病人を抱えていては、しなければ相済まないと思うことも出来ず、自分のしたいこともすべてあきらめて見送って来た。――電話のあと、ああさむい、とふとんを引かぶった。熱が出た。
以来まだすっきりとはしない。外は、さくらが咲いてお花見だという。夏の、受賞式までには何とかなるだろう。
若くてこれからですよ――というのなら、賞を御出しになる側も御張合が多かろう。わたくしのように大正の末から今まで書いて来て、このていどの人間に下さるとは、申訳のない事である。
今度の「ひたくれなゐ」は巻末に近いほど自分の個人的な環境や日常の色あいが、素材として出てくるけれど、それは偶然そうなっただけのはなしである。人間の身辺境遇的なものは、誰にもわかり易く、同情をひきやすいけれども、その事だけを特に重く引き出して読まれるのは、少し残念なような気がする。一人の女が出あったこと――と見ていただければ、けっこうである。
ありがたく御礼を申上げ、これからも行けるところまで歩いてみます、と申上げることである。
選評(敬称略/50音順)
「予想どうりの受賞」上田三四二
『ひたくれなゐ』に票が集まるだろうという予想をもって臨んだが、果してそのとおりになった。私にも異存はなかった。
ただ私としては『高安国世短歌作品集』を推したい気持があって、『ひたくれなゐ』と同時受賞の形ででもそのことが実現すればよいと思った。この全歌集は新歌集『新樹』を含み、『新樹』は『虚像の鳩』にまで行きついた高安氏の実験的手法が『朝から朝』を折り返し点として自然再発見の安らぎの気息を取りもどし、年齢からくる観照の深さを加えている。
はじめに、山本理事長より従来のように受賞の対象を過去の全業績に及ぼすやり方を改めて、なるべく年度内の一冊に限りたいという意向が示されていたこともあり、『新樹』一冊ではやや弱いという意見も出て、賛同が得られなかった。
『沜丘歌篇』は独自の風格をもち、作者の興味の向け方が瑣末的にすぎると思われるところもあるが、中に、目を見張るような秀歌を含む。
真鍋美恵子『土に低きもの』ほか数冊の名もあがったが、審議はもっぱらこの三冊に集中し、高安·片山両氏のものが競合した結果、どちらも同時受賞が見送りになった。賞のあり方としては単独受賞が本来なので、もっとも支持の多かった『ひたくれなゐ』の単独受賞は順当で望ましい形と言えよう。『ひたくれなゐ』については他の委員から適切な評があると思う。
「新しい女歌へ」岡野弘彦
今回の迢空賞の選考は、山本健吉理事長と、新しく選者を委嘱された四名とが、あらかじめアンケートによって推薦せられた候補者を対象にして審議し、受賞者を決定するという方法がとられた。
アンケートによって推されてきた上位の三名、『ひたくれなゐ』の斎藤史氏、『沜丘歌篇』の片山貞美氏、『新樹』・『高安国世短歌作品集』の高安国世氏はいずれも、当年度に刊行された歌集の内容もすぐれ、従来、歌壇に示してこられた業績も大きなものがある。選考の過程で、今回の受賞者は複数にしては、という意見が出たのも当然のことであったと思う。
いよいよ一名を選出するということになって、私は斎藤氏を推した。氏が一貫して示してこられた、新しい女歌への情熱は、今回の歌集『ひたくれなゐ』の中にも、見事な作品となって結晶している。殊に斎藤氏の作風が、戦後に出たわれわれとほぼ年齢を同じくする女流歌人達に与えた影響は、大きく豊かなものがあったと思うからである。
選考を終って、山本氏の発案で千鳥ヶ淵の夜桜を見た。暗い濠の水の向うに湧きあがるような花の華麗さを見つめながら、さっきまでの歌について論じあっていた心の興奮が、一層さえざえとよみがえってくるのを感じていた。
「二歌集について」田谷 鋭
『沜丘歌篇』(片山貞美氏)
ばらの花うつろひはてし園に出て空にかかれる時計を仰ぐ
眠らむと暗きおのれに痒きところおりて搔ければ手ぞ大きなる
渦を巻き渦を巻きやまぬもろもろゆ人眼ひとついでて瞠く (映画)
実体に即しながら平板な写実ではない。それぞれの事実が心内で再編成され一つ一つ作者の分身となっている。茂吉の言う写生の意味を現代に受け継ぐとしたら、こうした恰好になるのではないか、そう思わすところがある。右の例歌には、都市風景の一面、感覚世界の渾沌、衝撃的な風俗などが独自の肉厚な手法でとられている。地道かつ永続的でなければ遂げられなかった仕事と言えよう。
『ひたくれなゐ』(斎藤史氏)
液汁とられしすべての芥子に傷残りかなしみ垂りてわれはゆくなり
ふたひらのわが〈土踏まず〉土をふまず風のみ踏みてありたかりしを
まだ落ちてゆく凶(まが)々しき空間のあるといふことがわれの明日ぞ
早くして高名なこの作家が、苛酷な現実と対き合って成し遂げた世界である。現実を見つめる作者個有の二重の視点が、この集(ことに後半)では違和なく一つに融け合って感じられる。例歌はいくらかは好みに傾いたが、「修那羅峠」「信濃考」など、群作としての効果のめだつ一連も集の魅力をなしている。
「独自の精神風土」馬場あき子
つゆしぐれ信濃は秋の姥捨のわれを置きさり過ぎしものたち
『ひたくれなゐ』の終末に反歌のように据えられたこの一首にもあらわれているように、斎藤さんの声調は勁く麗わしい。そして、その主題はまさに〈ひたくれなゐ〉に生きたと自認しうる女の生を総括して、把握の大きな世界をもち、ゆたかな抒情性と緻密で重厚な技巧の力をもって、熱い坩堝の中の詩のかがやきをみせている。
斎藤さんの作品は、昭和十年代のモダニズム最後の残照の中に耀いた『魚歌』や『新風十人』のあと、太平洋戦争の波に沈んでゆくが、昭和二十八年に刊行された『うたのゆくへ』以後は、きわめて深い自己認識の苦汁に染まりつつ復活し、戦後短歌の、ことに女流にとっては一種のバイブル的存在となっていた。
この度受賞された歌集『ひたくれたなゐ』によって到達された世界は、詩歌においての近代的諸要素を栄養として、まったく独自の精神風土をあらわすにふさわしい短歌の文体を完成している。
まさに現代短歌の一つの高峯を示すものと思われる。
